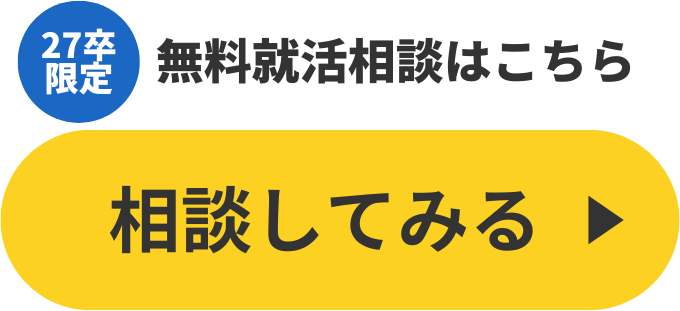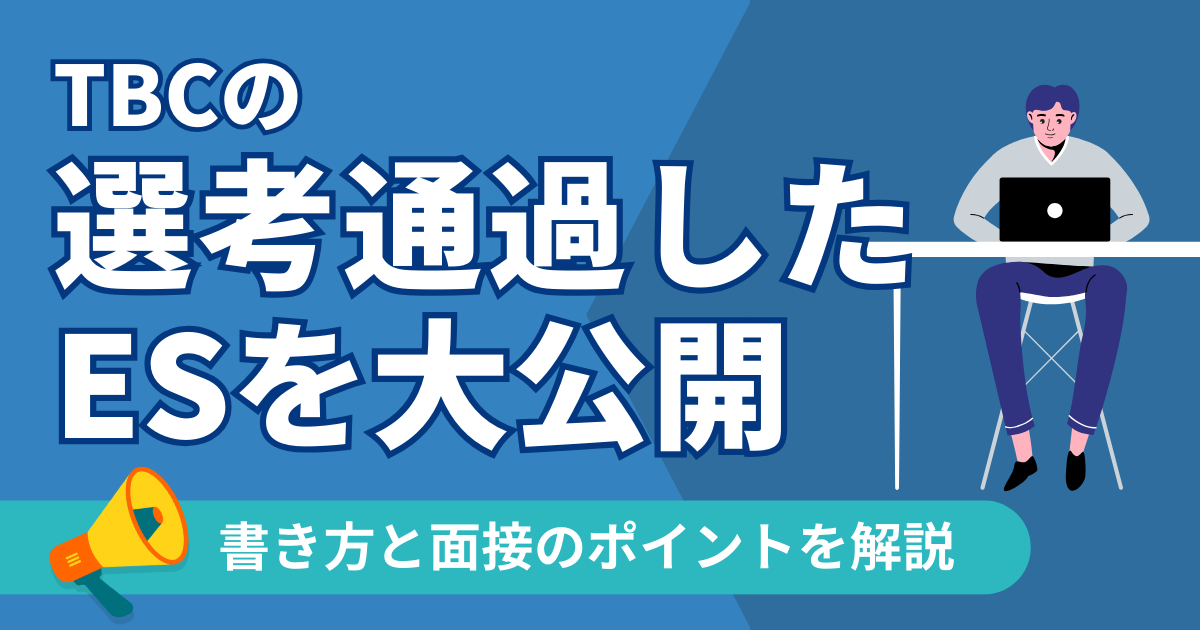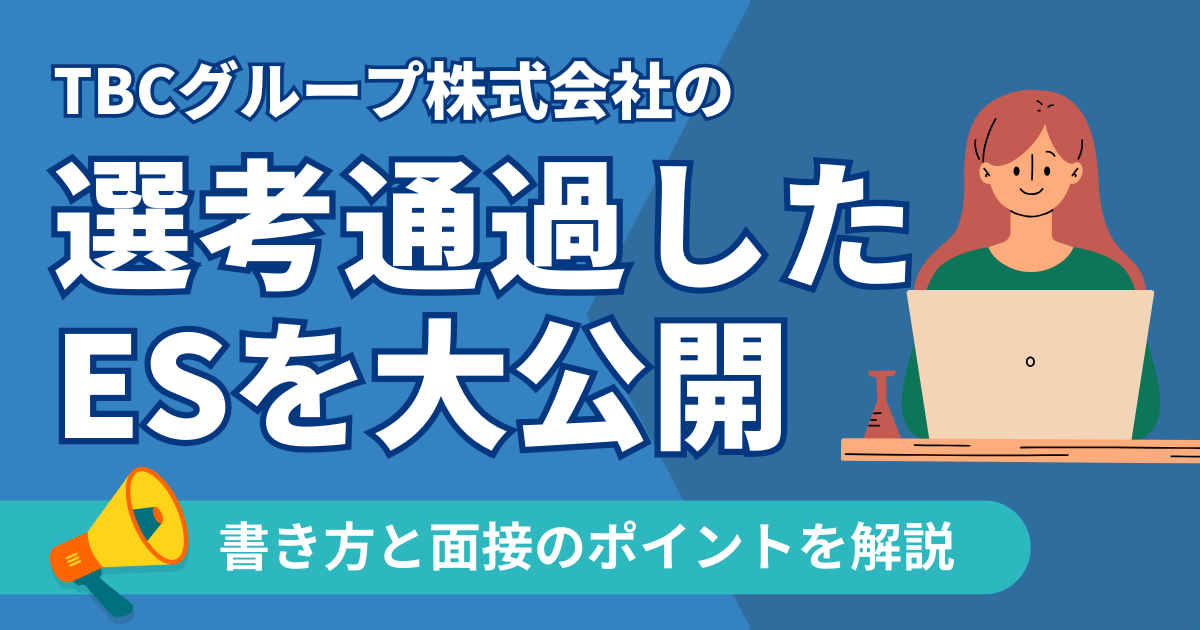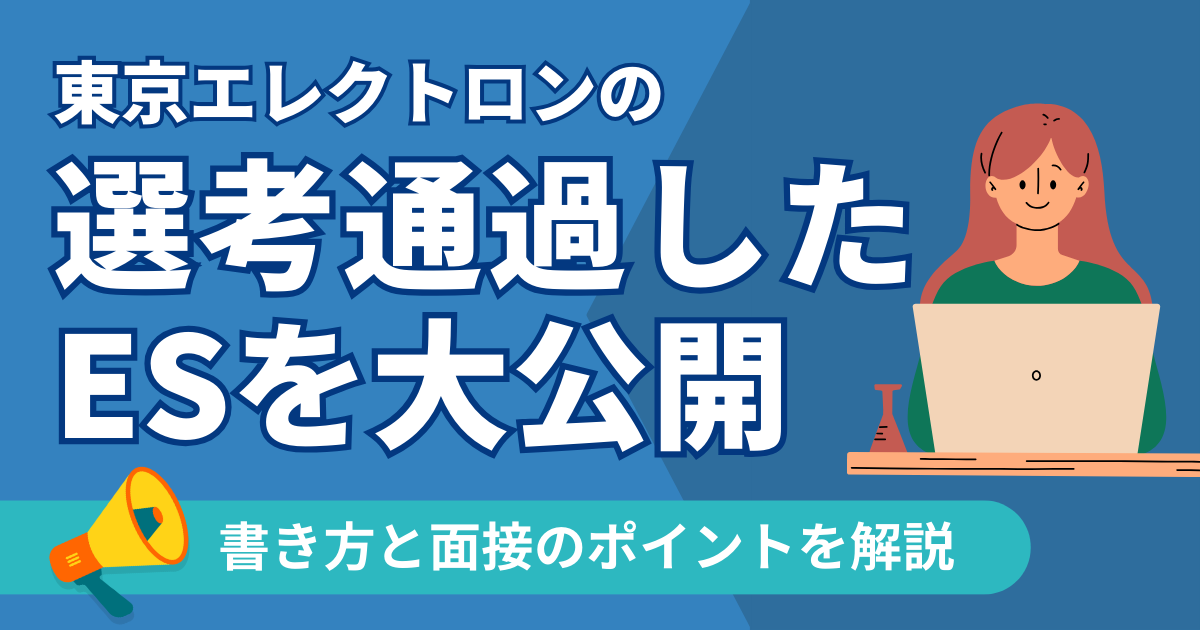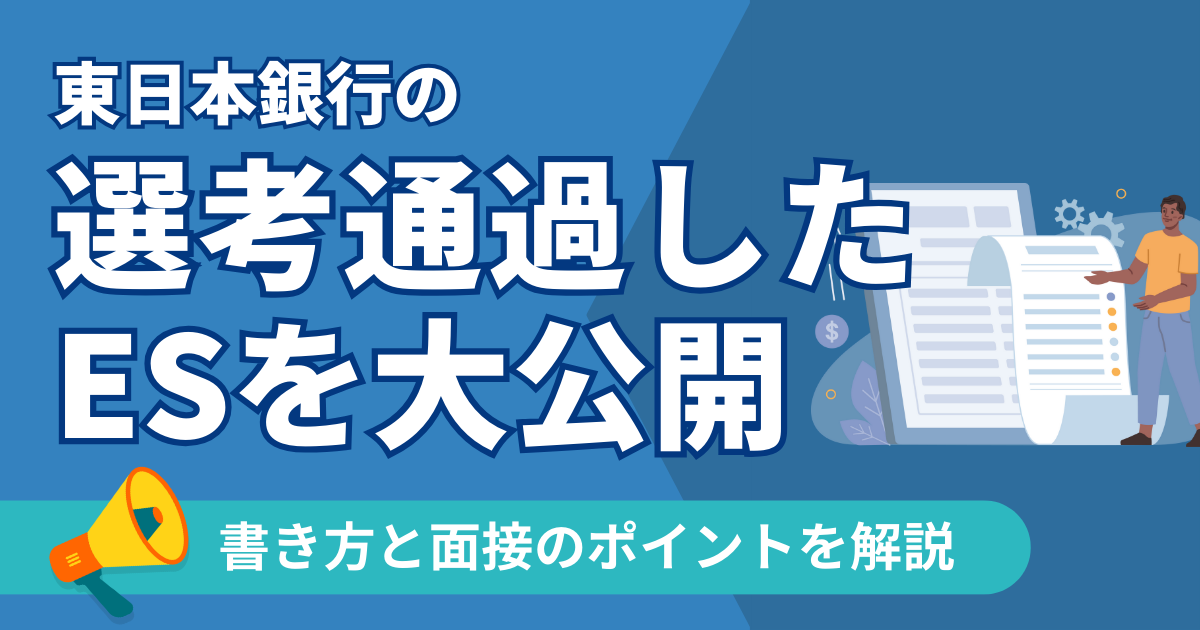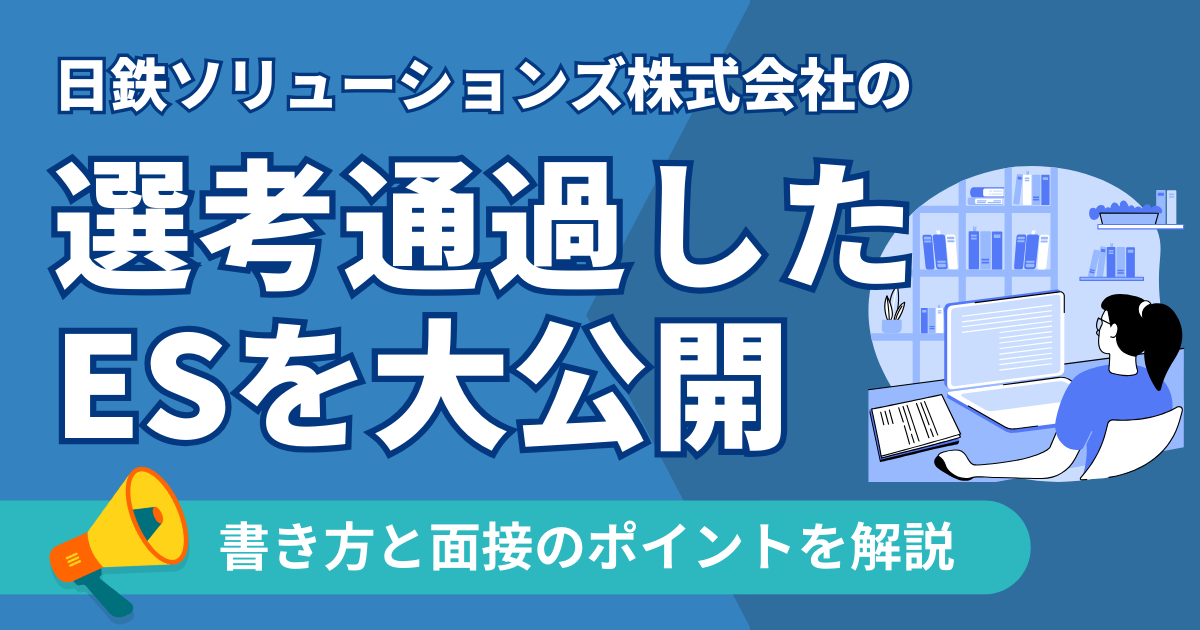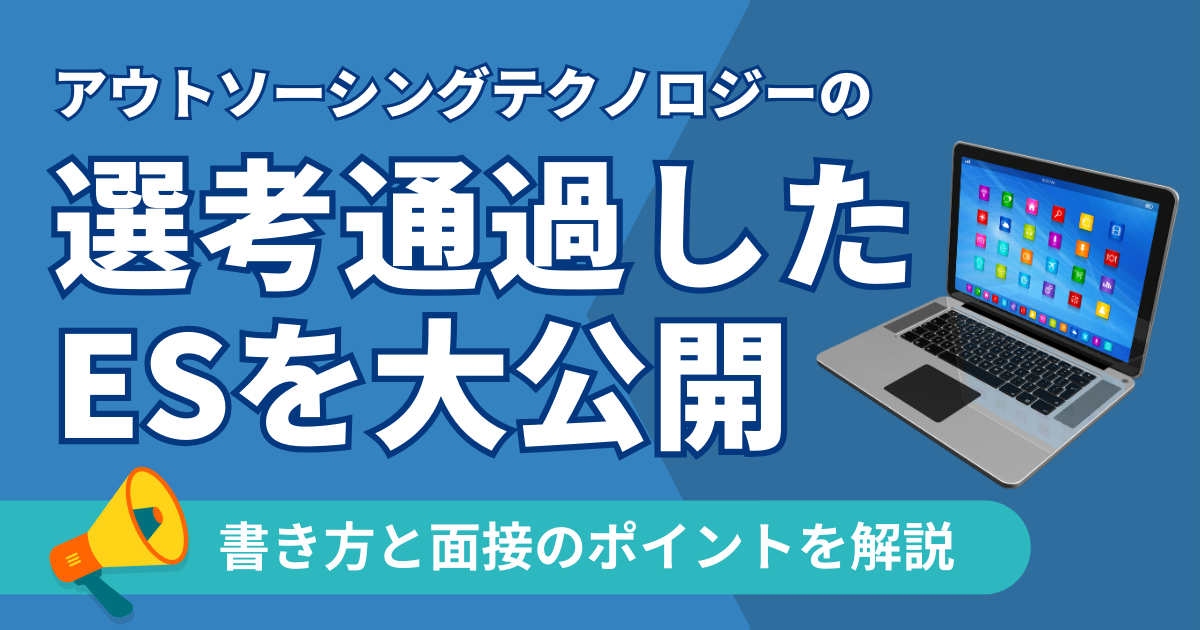PS(生産統括)
25年卒
女性
京都工芸繊維大学
ES情報
職種選択
PS(生産統括)を選択
その職種を志望する理由を入力して下さい。(200文字以内)
貴社におけるサプライチェーンの上流から下流まで全て担うPSを通して、世界に新たな価値を付加したいからです。毎日使用する消費財であるからこそ、何から何まで貴社の製品でなければ満足できない消費者を世界中にさらに増やすことに貢献したいと考えています。また、説明会を通して、貴社では若いうちから裁量権が与えられ、グローバルに新たな挑戦をできる環境が整っている点に魅力を感じました。そこで、私の強みである周りを巻き込み挑戦する力を最大限発揮し、自己成長できる場であると考えています。
あるグループに参加し、全体を率いて、必要なサポートを獲得し、卓越した結果を実現した実例を説明して下さい(700文字以内)
私は、アルバイト先である居酒屋で、バイトリーダーとして集客率の拡大に尽力しました。周囲の店舗と比べ、集客率が芳しい現状を改善したいと考えました。そこで、従業員と話し合った結果、①周囲の店と差別化が図れていない、②常連客の獲得が出来ていない、以上の2点が課題であると考えました。これらを解決するために、私は次の策を考案し、従業員を巻き込み取り組みました。
①周囲の店に出向き、それぞれどのような特徴があるのか調査しました。すると、集客率が高い店は、SNS映えするような独自のメニューが非常に多く、メニュー数も豊富でした。見た目は華やかだが価格が安く、大学生などの若い世代も入店し易いという特徴がありました。しかし、一品のボリュームが大きく、カロリーも非常に高く感じました。そこで、私たちは2軒目として訪れるのに相応しい、カロリーや量を少なく抑えられる店をコンセプトに、年齢層を幅広く設定しました。当時、私たちの店は、品質に拘っていたため、あまり安く提供できていませんでした。しかし、高い品質を保ちたかったため、地元の農家の方と綿密に連絡を取り、売るには見た目が芳しくない野菜を仕入れることで、より安く新鮮な野菜を継続的に仕入れることに成功しました。
②常連客を獲得するために、アプリを用いて各種クーポンや、入店するごとに貯まるポイント制を発案しました。SNSに注文した商品の写真を投稿することで、次回来店時5%オフクーポンを差し上げました。常連客の獲得と共に、SNS発信により新規客の獲得に繋げることが出来ました。以上の2点の取り組みにより、前年度比+10%の集客率を記録することに成功しました。
他者とともに仕事をする上で、見解の相違があっても生産的な関係を作り、保つことができたときについて説明して下さい。(700文字以内)
私は所属しているテニスサークルで合宿係長を務めました。以前、合宿は2泊3日でしたが、練習量の増加や、仲間間の親睦を深める目的で、3泊4日で行いたいという意見が出ました。しかし、費用がかさむという理由で3泊4日は実施してほしくないという意見も出ました。そこで、3泊4日の際に必要な費用を2泊3日で実施していた際とほぼ同額にすることで、全員が満足して参加することができると感じ、次の3点の解決策を考えました。まず、1点目として、宿泊先を以前のホテルから廃校になった小学校の宿泊施設に変更しました。それにより、宿泊費用を50%削減することに繋がりました。2点目として、開催地を九州から関西に、交通手段を船からバスに変更し、交通費を抑えました。電車や車を使って、自力で開催地まで来ることが可能な人はバスの乗車を控えてもらい、借りるバスの台数を減らすことで予算を削減しました。次に、3点目として、市営コートを利用することにしました。以前は、3日間宿泊先のテニスコートを利用していました。以前の合宿費の30%がテニスコート代金であり、ナイターは照明を利用することから費用がかさむことが見直す中で明らかになりました。そこで、夕方までの利用を決めました。もちろん、費用を抑えることも大切ですが、合宿の質を落としたくは無いと考え、食事は自炊にし、予算を決め幾つかのチームに分け作るなど、テニス以外で全員が交流できる機会を多く作ることに心がけました。これらの解決策を取り組んだ結果、2泊3日の費用よりもさらに安価にすることが出来、サークルメンバーの内90%が参加し、3泊4日での合宿を無事実施することができました。
あなたがプロジェクトの方向を変え、その結果、時間やコストが削減された例を説明して下さい。(700文字以内)
私は現在、研究室で、〇〇の研究を行っています。以前、チーム内で同じものを使用していたとはいえどテーマが若干異なるため別々で実験計画を立てていました。そのため、同一の実験をそれぞれが同時に行ってしまうことがあり、二度手間を踏んでいると感じていました。また、コミュニケーションをあまりとっておらず、お互いの実験データを見ても的確にアドバイスができていませんでした。限られた期間の間でデータを出す必要性があり、より効率的に実験すべきだと考えました。課題を解決すべく自身がリーダーとなり、全員の実験で共通している点を洗い出し、一度で全要因を調査できる実験を設置しました。その結果、お互い情報伝達の機会を増やすきっかけに繋がり、以前よりお互いに的確なアドバイスが出来るようになりました。さらに、他分野の事象を自身の実験に取り込むことができ、一度の実験で、多角的なデータを複数得ることに繋がりました。