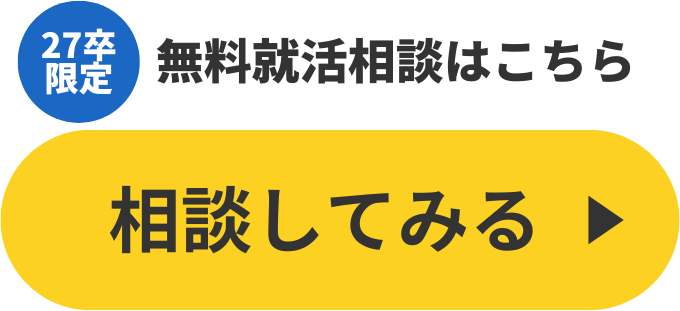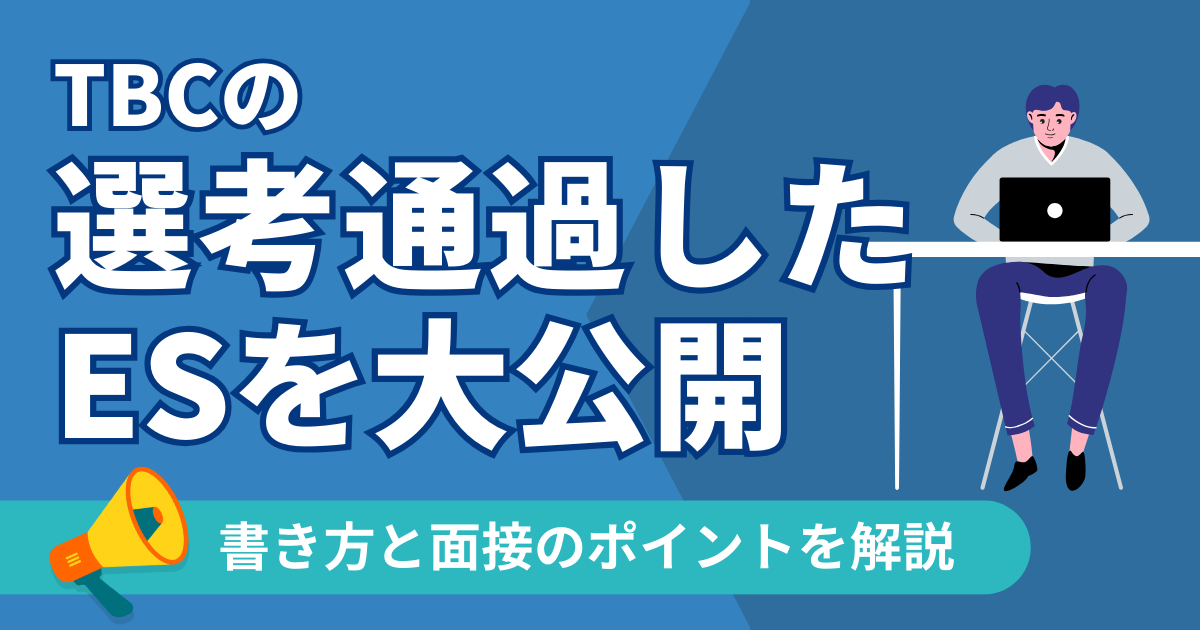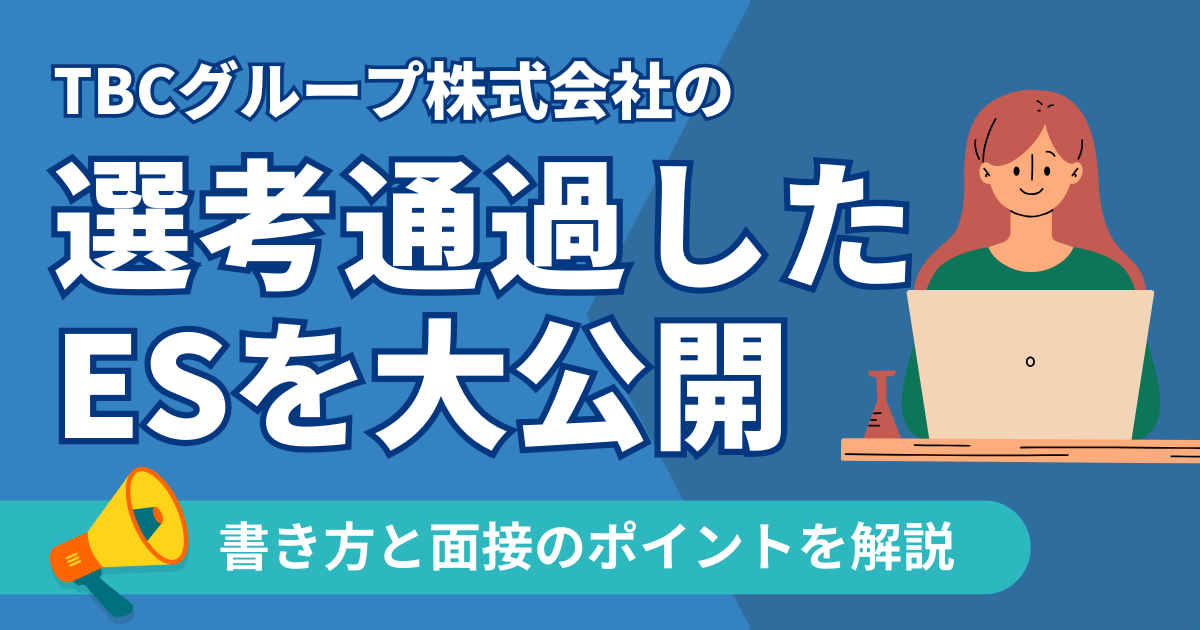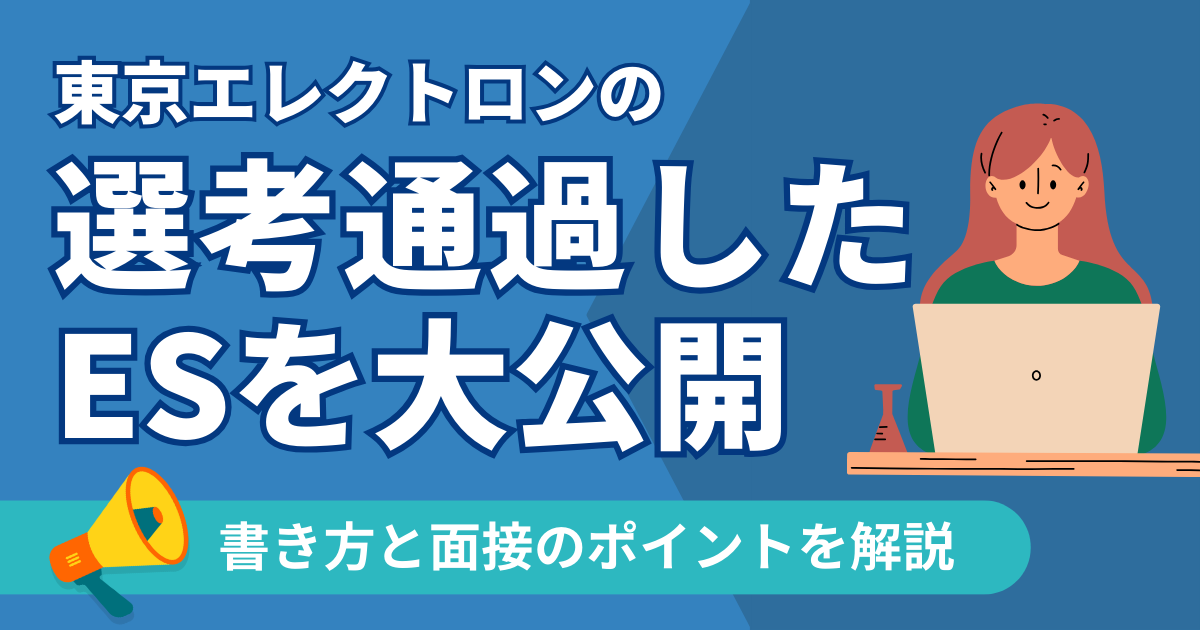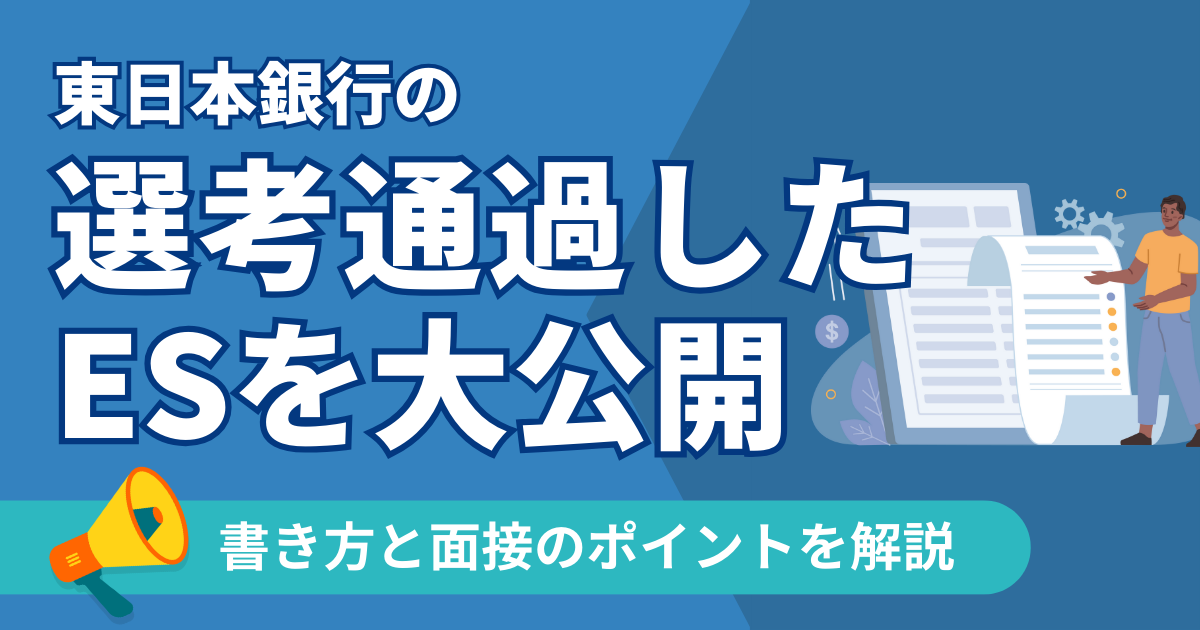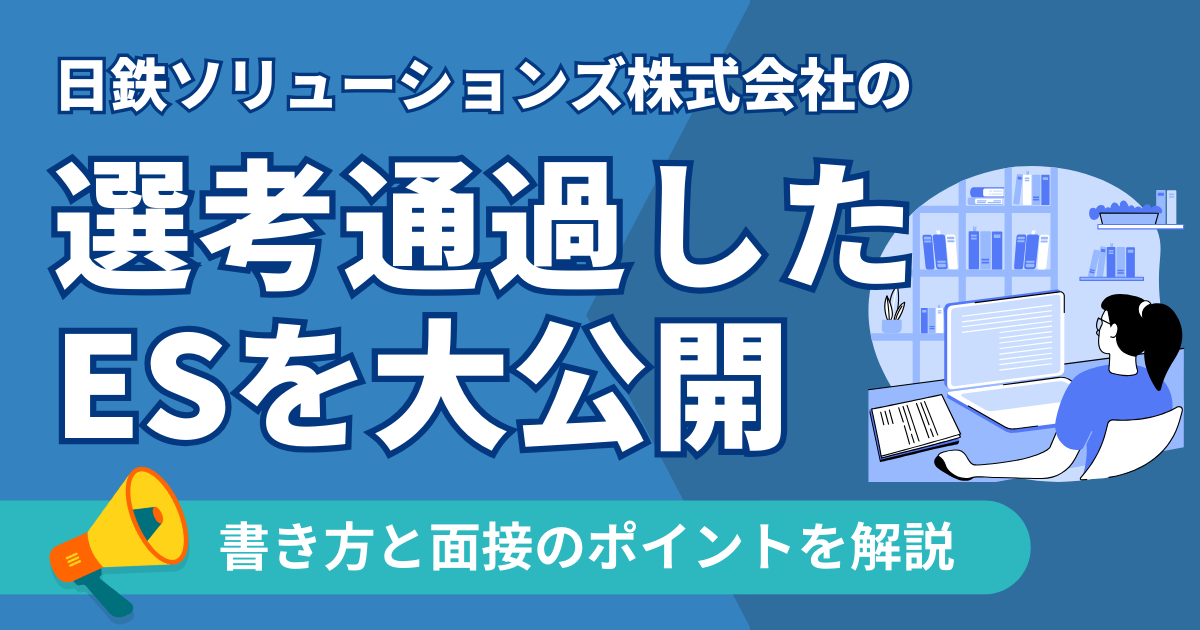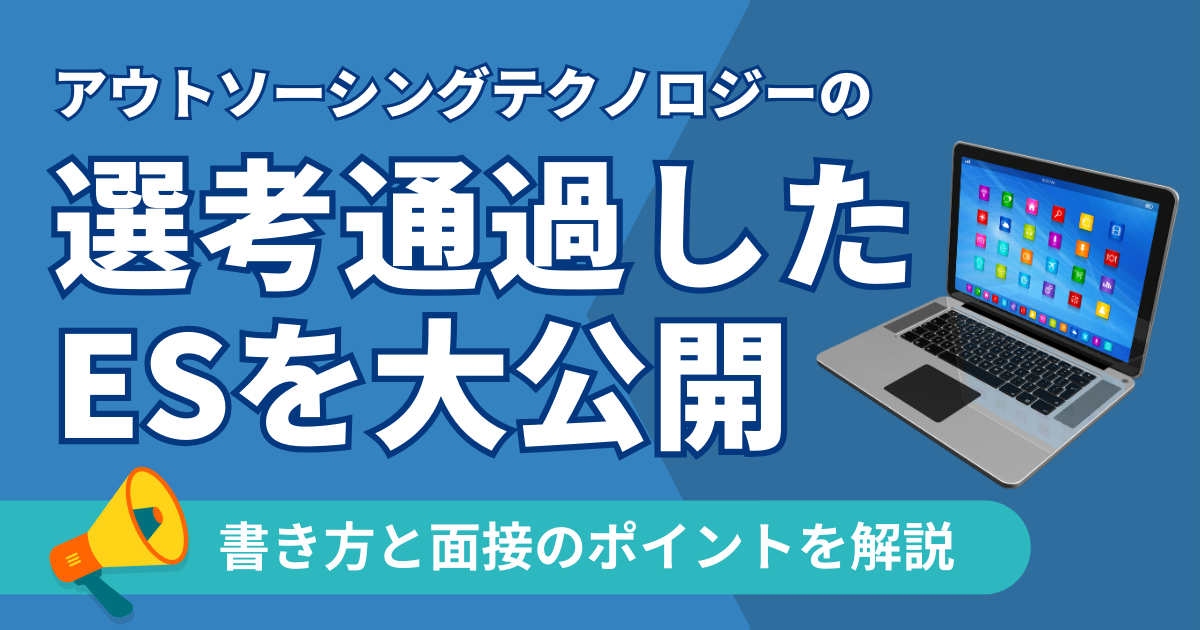25年卒
男性
早稲田大学
ES情報
自己PR
私の強みは、国際感覚と協調性である。幼少期に3年、大学留学で1年の海外生活により高度な英語力を習得できただけでなく、国民性や文化的背景の異なる友人との付き合いを通じ、異なる意見や価値観に対する理解力、寛容性が身についた。また、小中高10年以上サッカーに打ち込み、チームワークの大切さ、他者への思いやり、継続して努力することの重要性、皆で目標に向かって一丸となる事の素晴らしさなどを学ぶ事ができた。この経験は、大学のサッカーサークルでのチームの主将を任された際にも役立ったと思う。以上のような私の経験、能力は、グローバル化が進展し、ビジネスにおいて国際的な視点が求められる中、会社組織の一員として上司や同僚と協力して仕事に取り組む際にきっと役立つと考えている。
ガクチカ
サッカーサークル最大の大会でチーム主将としてチームを率いた。まず、チーム統率のために各人の現在地を知る事が必要と考え、面談の機会を設けた。その結果、活動へのコミットメント不足からモチベーションに差がある事が判明した。私は主将として以下の三点を実行した。
1.全員が同じ方向に向かうための「目標の共有」。
2.2名1組で互いの課題を指摘し合う「バディ制度」の導入。この狙いは他人の評価を聞き内省を促す事である。
3.制度を実質的に機能させるため、意見交換をライングループ上で行うこととした。
この結果、練習メニューを提案する人が出てくるなど、意識の変化が見られ、ベスト32という好成績を得る事ができた。
大学時代、あなたの行動や考え方に最も影響を与えた講義を教えてください。
留学中に受講したジェンダー論の授業である。40人程度の少人数授業であったがその40人それぞれが異なった価値観を持つ事を肌で実感した。授業中、トランスジェンダーという言わば少数派の人が自信を持って意見を発信している姿は私が自分らしく生きようと考えるようになったきっかけである。
どのような業界や会社を志望していますか。
「島国である日本の人々の安定した暮らしをグローバルな視点を持ち支えたい」「世界における日本のプレゼンスを向上させたい」という考えから海運業界や商社を志望している。
たくさんの企業の中から当社を志望する理由や想いを教えてください。
日本の輸出入のほぼ全てを担い、人々の暮らしや社会を支えることができる海運業界に魅力を感じている。中でも貴社は海運輸送を中心として事業展開をしており、LNG船保有数が世界1位である事から海というフィールドの中で最も存在感を出せるのではないかと考え志望する。また、LTIFが業界トップレベルで少なく、2022年度では0.19であった事は貴社の安全性に対する強い思いを感じ取れ、社員全員がプロフェッショナルとして意識高く、それぞれの役割を全うしている組織で働き、貢献したいと強く感じている。
あなたが、他の多くの人たちとは異なる見解を持つことがらについて教えてください。それはあなたのどのような価値観に基づいていると思いますか。
日本において英語力がある=発音がいい事だと考えられている事だ。最近SNSでインフルエンサーが英語で話す場面をよく見かける。それに対するコメントを見ると「発音が良い」という言葉をよく見る。これは褒め言葉のつもりなのかもしれないが、私は留学の経験の中で発音は全く英語力に関係ないと感じた。実際に様々な人種と話す中で発音に触れられた事は一度もない。それよりも自分の意見をはっきり伝えられるかどうかが英語力の有無に直結すると感じる。これは私の「自分らしさを大事にする」という価値観に基づいていると感じ、他者との違いはある事が当たり前であるため、対話を通じて理解しようとする姿勢を私は大事にしている。
職場の上司に渡すための「あなた自身の取扱説明書」を作る場合、あなたの特徴や注意事項をどのように記載しますか。
私は「寄り道しがちな登山家」だ。目標を高く設定しそれに向かって地道に努力を続ける一方、その過程で直接的にそのゴールに結びつかない事でも興味が湧くと立ち止まる。例えば大学3年生でTOEICで980点を取得したが、これは入学直後から約2年半、英語力の向上に努めた結果である。通常、試験で高得点を取るためには問題集を何周もする事が効果的だが、私は問題集にプラスして英語のニュースを毎日視聴し、疑問に思う事をノートに書き留めていた。この取り組みの中でニュースの内容に興味を惹かれ、問題集を疎かにする事が多々あった。現在は、より細かく目標設定する事で寄り道を防いでいるが、仕事ではこまめに進捗を報告するように心がけたい。