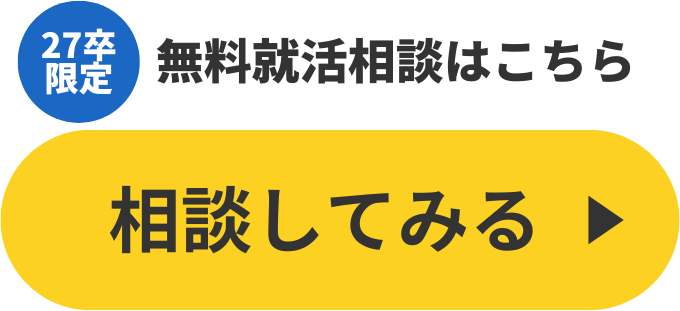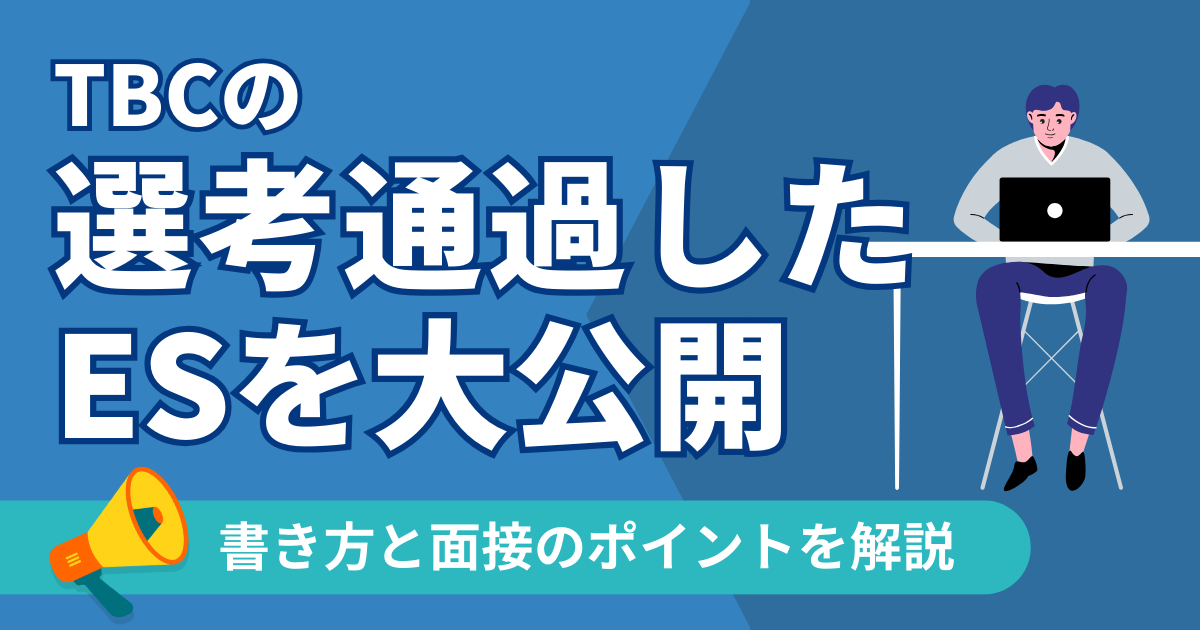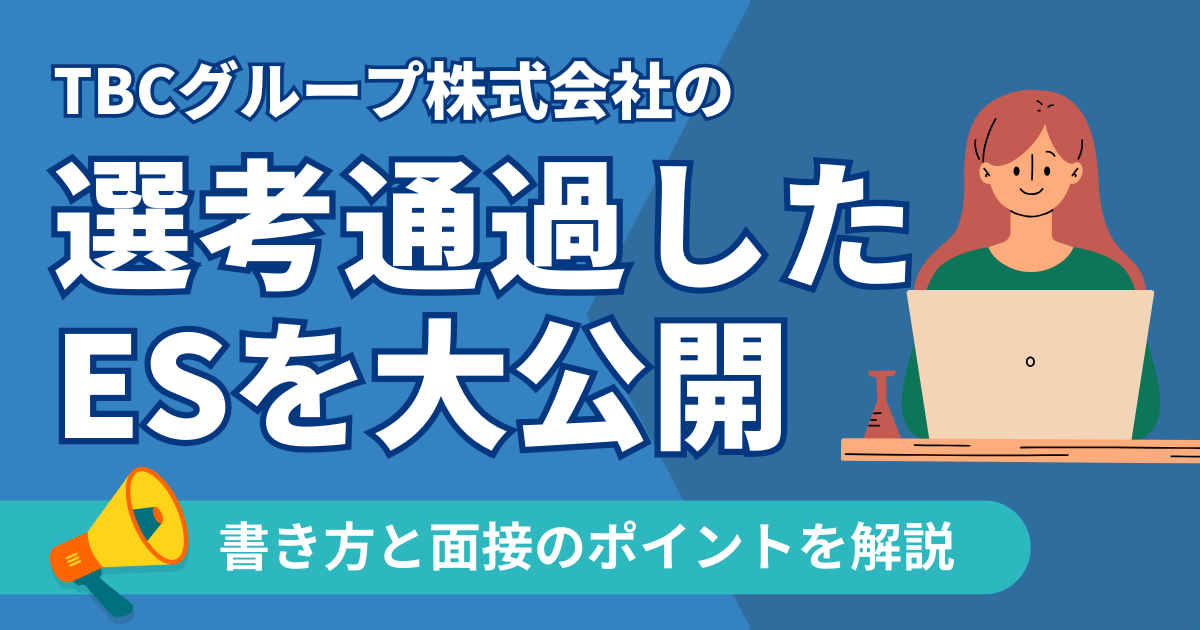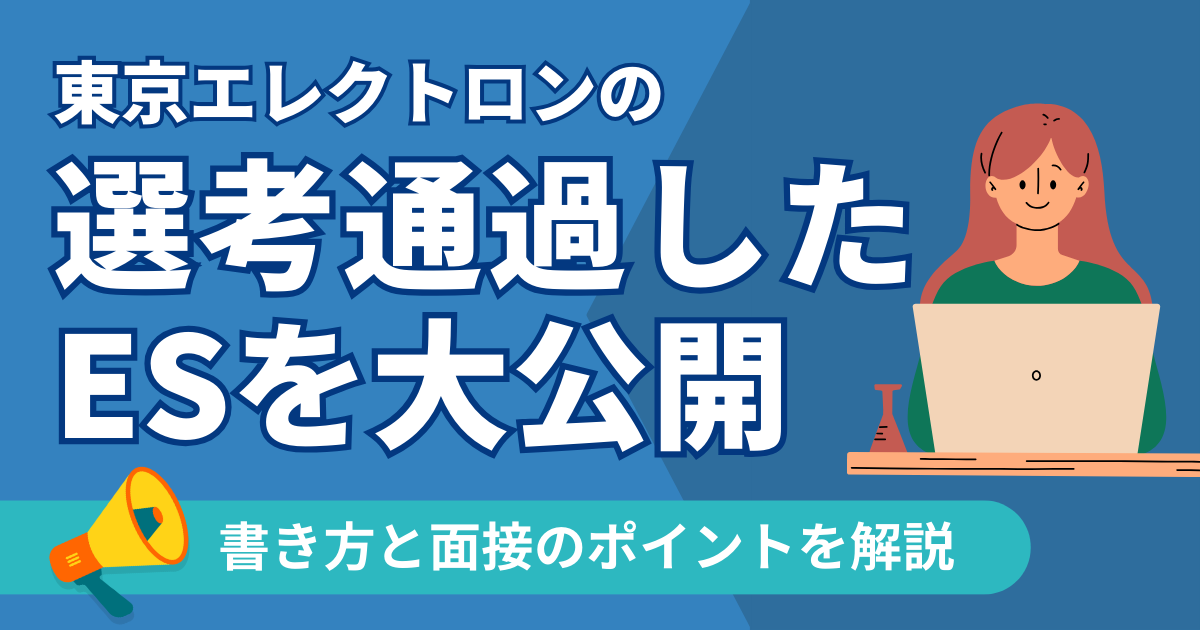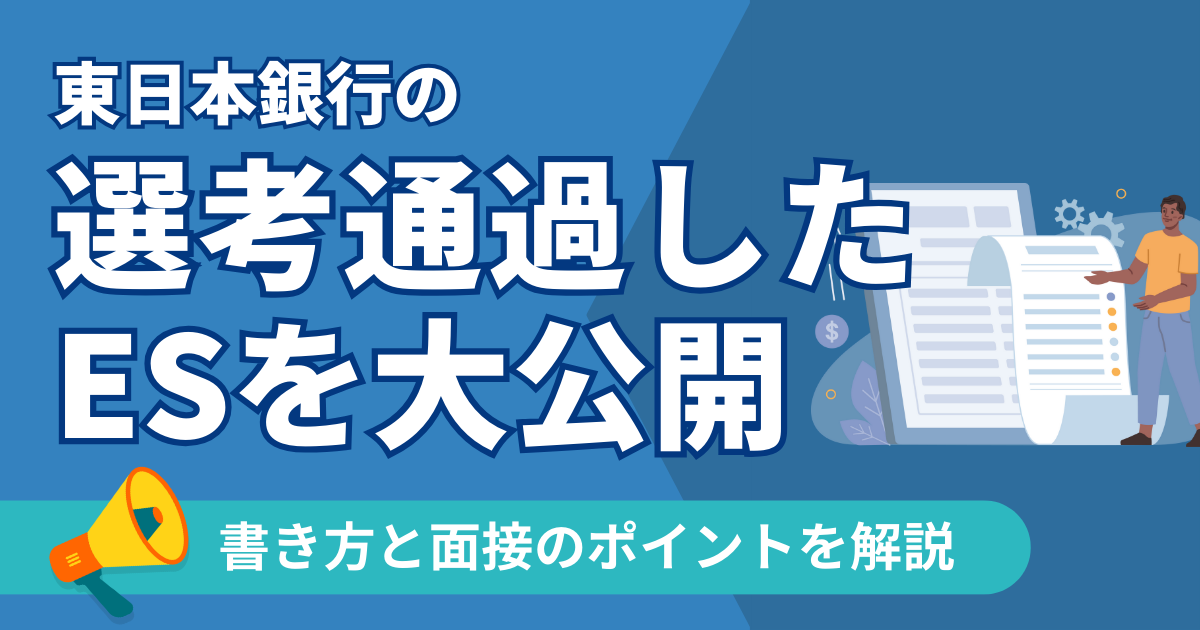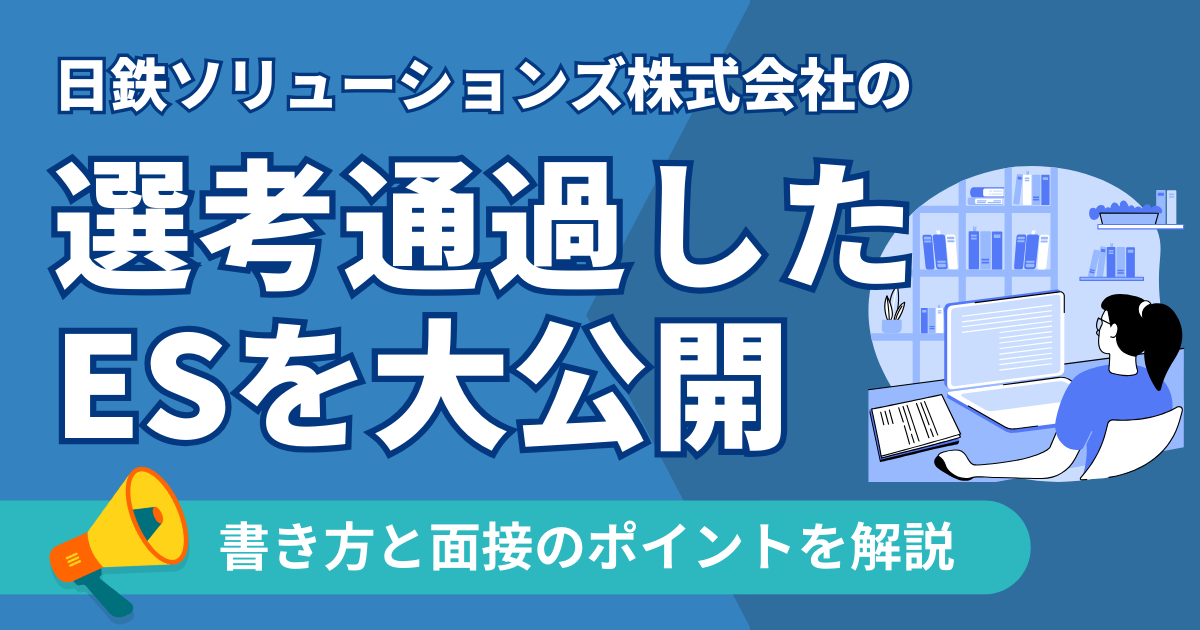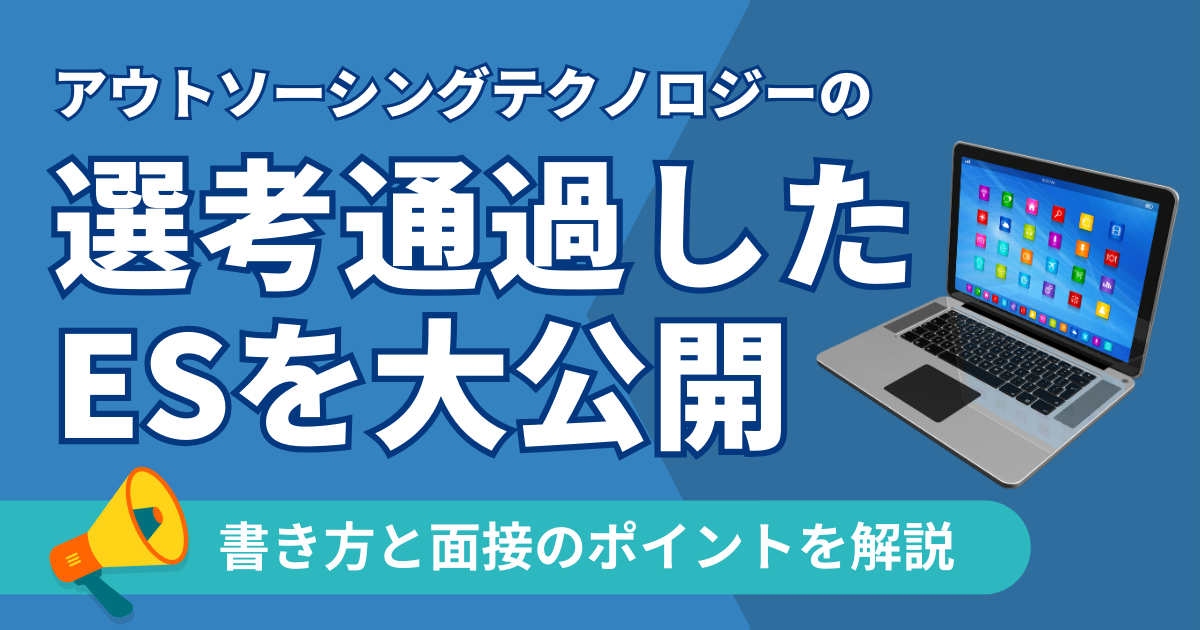最終面接
基本情報
| 場所 | 本社 |
| 時間 | 40分 |
| 社員数 | 1人 |
| 学生数 | 1人 |
| 結果通知時期 | ー |
| 結果通知方法 | 電話 |
質問内容・回答
①自己紹介
大学名、学部名の〇〇と申します。大学時代は社会学を中心に学んでおり、ゼミナールで○○ゼミに所属しジェンダーのことについて主に研究していました。サークルは○○研究会と○○の会に所属しており、課外活動としては高校三年生から外資系メーカーでショッパーマーケティングの業務に、昨年の9月から保険を扱っている企業でビジネスディレクターの業務に携わらせていただいています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
【深掘質問】
インターンシップは何で取り組もうと思ったのですか。
【深堀質問回答】
高校生の時に周りの人がやっているのを知って、楽しそうだから自分もやってみたいと思ったからです。また、学生でありながら社会人の方と一緒に仕事をできる経験はなかなかできないと思ったので自身の成長のきっかけになるとも思いました。
②学生時代に力を入れたこと
大学二年生になる春休みに所属している○○研究会の新歓を担当したことです。「新入生に勉強会を楽しんでもらうこと」を目標とし、クイズ形式を要素ごとに盛り込んだ形式にしました。その結果、勉強会後のアンケートでは「楽しかった」という声を沢山いただくことができ、また入会員数も昨年の130人から150人へと増やすことができました。
【深掘質問】
なぜ新歓の担当を行おうと思ったのか。
【深堀質問回答】
新入生100人ほどの前で勉強会を開催できる機会はなかなかないと思い、挑戦してみたいと思ったからです。また、憧れの先輩から声をかけてもらい、先輩の期待に応えたいと思う気持ちもありました。
③志望動機
人や企業の挑戦を後押しできるという点に魅力を感じたからです。昔から周りの人が笑顔でいられる、やりたいことに挑戦できる社会の実現に貢献したいと考えており、その点が損保と関連性があると思い志望しています。そして特に貴社を志望している理由は社員の方々が常に挑戦している姿勢を一番感じられたからです。人や企業の挑戦の後押しをする要素を持っている損保を扱うからにはそこで働く人も挑戦している必要があると考えています。貴社はその挑戦の姿勢が一番強いと感じ、その点が魅力に感じています。
【深掘質問】
周りの人が笑顔でいられるとか人の挑戦を後押ししたいということでしたが、学業などでもそのような活動に取り組まれていたりするのですか。
【深堀質問回答】
ゼミナールの個人研究で「時代による化粧品を通した男性の自己表現と受け入れられ方の変化」を研究しています。化粧に昔から興味があったのですが、今の世の中は男性が化粧をしづらい傾向にあるのかなと感じています。それに対してどのようなアプローチができるのかという研究を行っています。
④長所と短所
長所は周りをみて行動できることです。一年生の時に参加したビジネスコンテストで、途中からメンバー間で情報に対する理解度の差が生まれてしまいましたが、それに対して自分なりにメンバーが理解できていないところを言語化して伝えてみたりと行動していました。
短所はこだわりが弱いところがある点です。自分が定めた目標までは達成しようと頑張れるのですが、それを達成した瞬間違うことに興味がわいてしまい、なかなか一つのことを極めることはできていないことが多いです。
面接詳細情報
| 面接官の社員の特徴 | 社員 男性で40歳前後。スーツ(営業職の男性だからかもしれません |
| 面接官の印象 | ー |
| 学生の服装 | スーツ |
| 面接の雰囲気 | 終始フランクな感じで進められました。最初に「緊張しているかもしれませんが、面接は対話なのであまり緊張せずにありのままを話してください。」と言われ、進められ方もかなり会話のような形でした。時々面接官の方がメモをとっていて間が空くことはありましたが、それ以外は社員訪問のような雰囲気で進められました。 |
| 評価されたと感じたポイント | 自分の軸をもって一貫性がある行動をしている点だと思います。また、企業の風土として「挑戦する姿勢」というのを推していることを説明会などを通して感じていたので、その点に合わせるように行動力をもって様々なことに挑戦している姿勢を表現できるようにしていました。 これは相性もあるかとは思いますが、笑顔でどれだけハキハキ話せるかということも重要だと感じました。今回面接を担当してくれた方が営業の社員さんだったのでその点も重視されていたのかと思います。 |
| 対策やアドバイス | 企業の風潮に合わせたアピール方法をすることだと思います。一次面接と違って二次面接以降はその企業に合っているか、そこで働いている社員さんと雰囲気が似ているかということも見られると思うので、企業研究を行ってどのような点をその企業が押しているのか、ということを意識しながら話すことが重要だと思います。 |