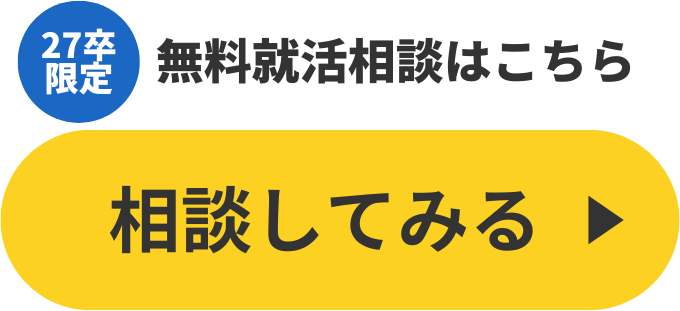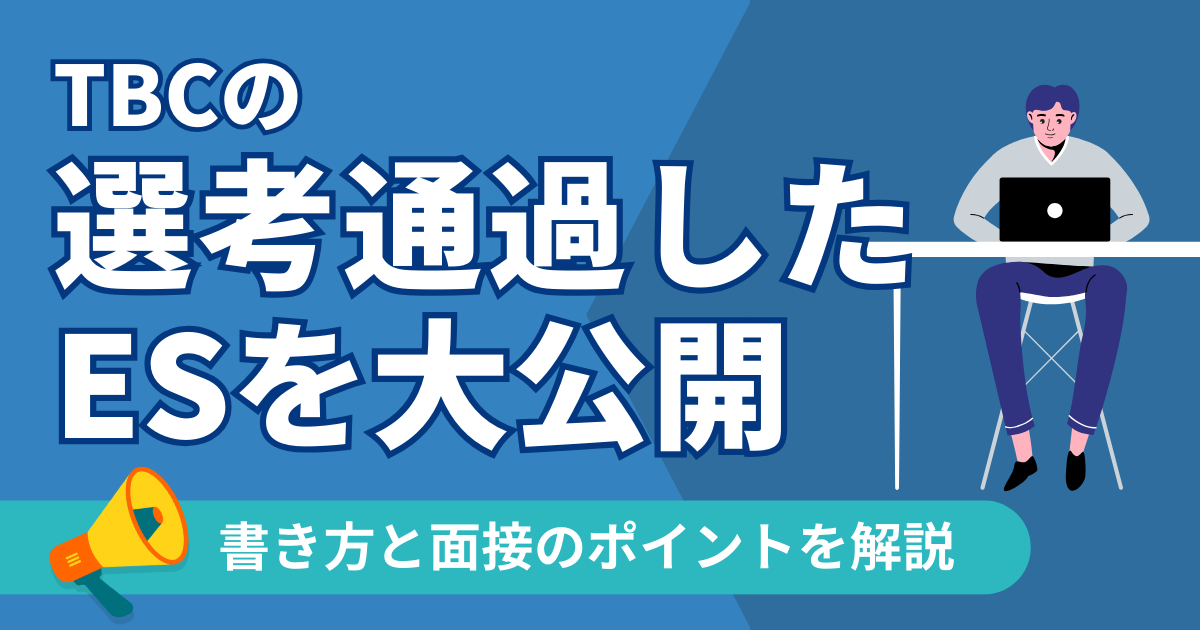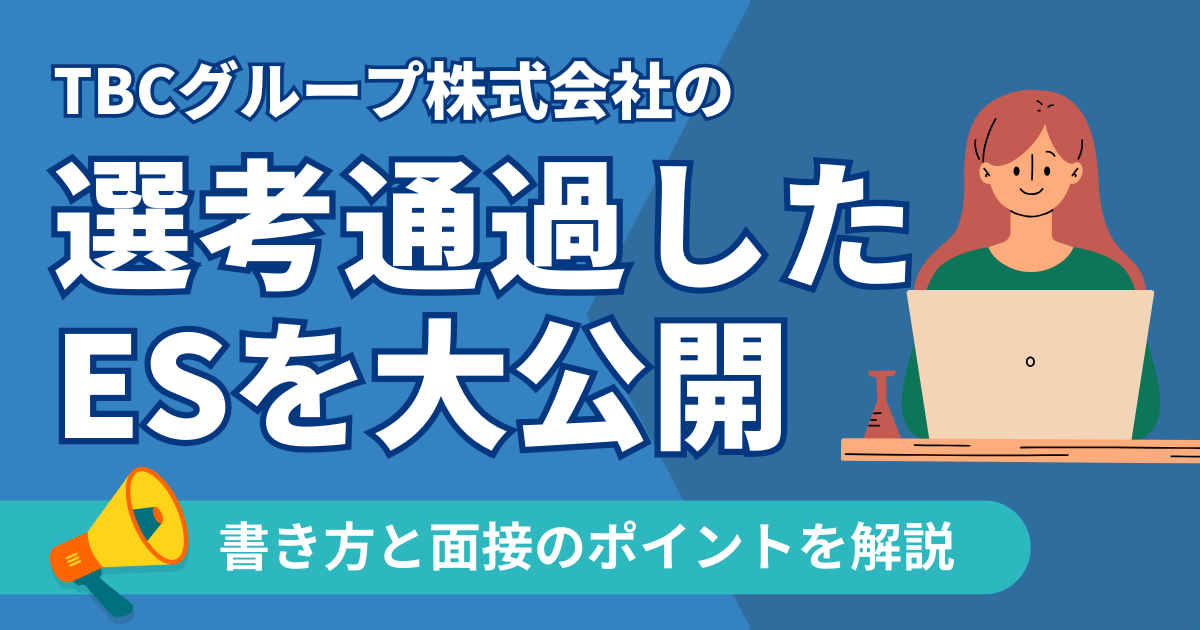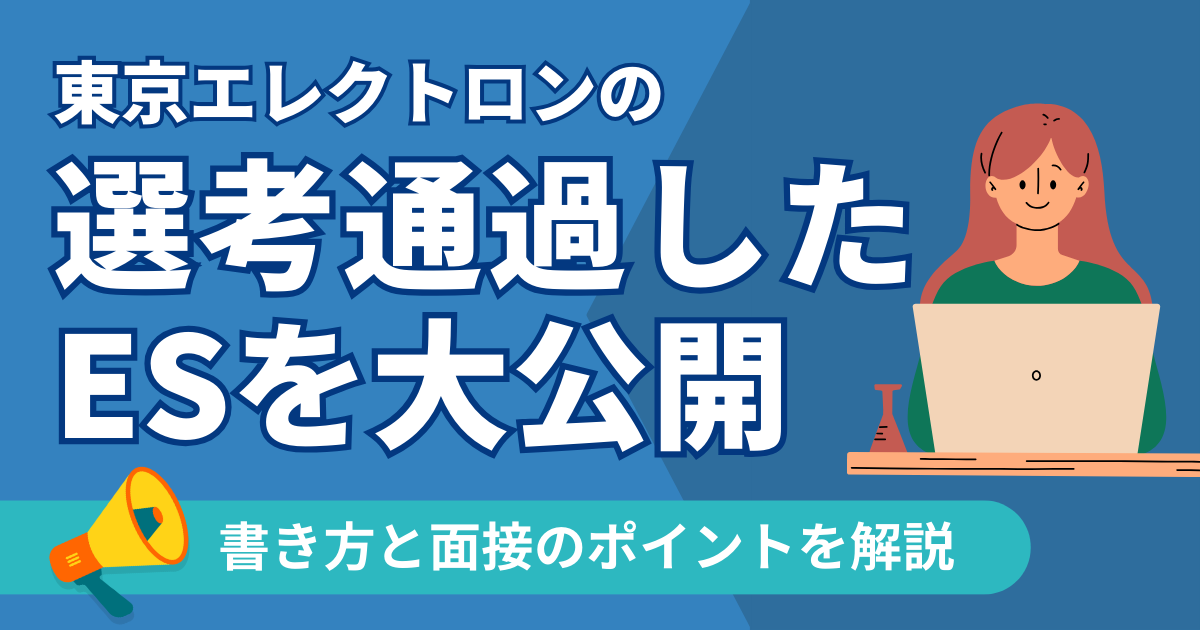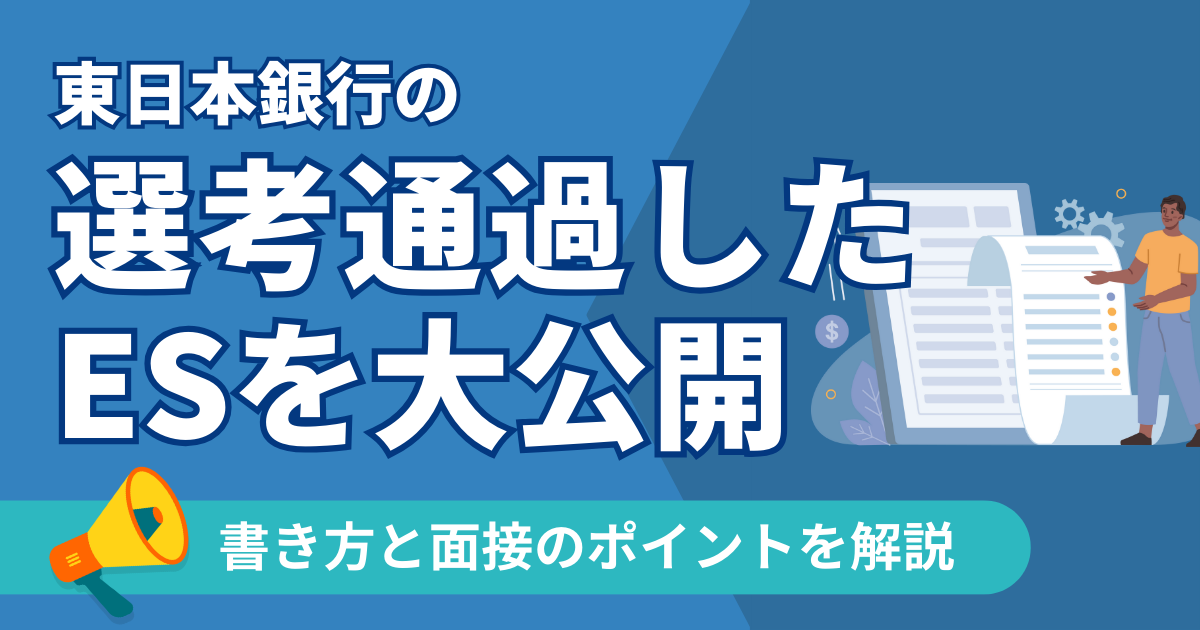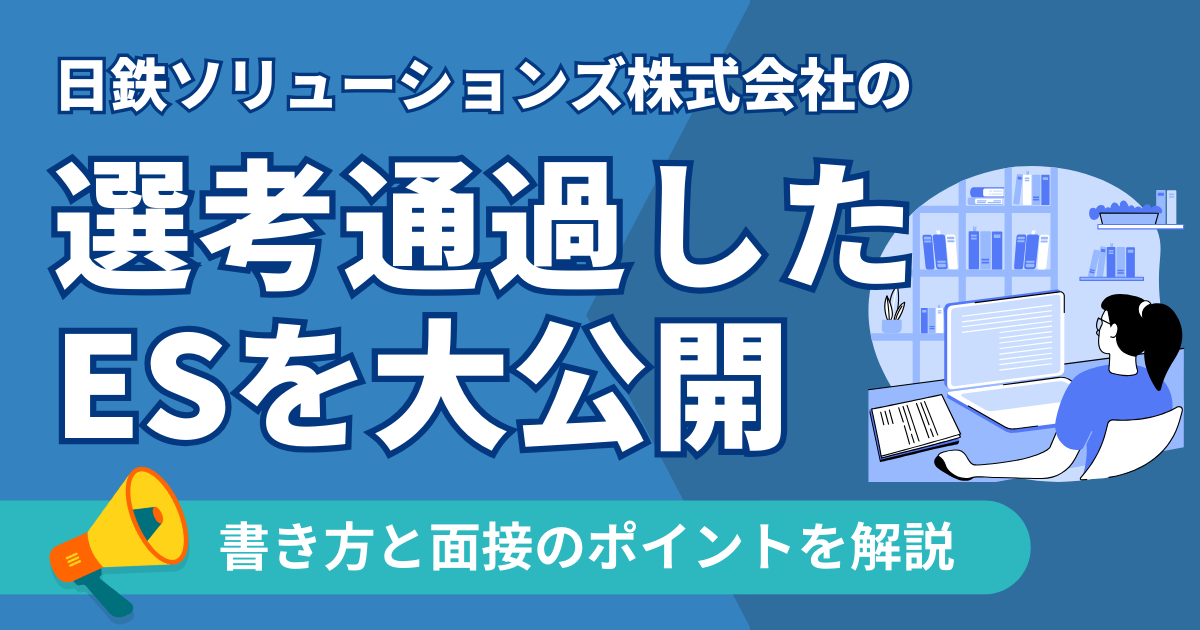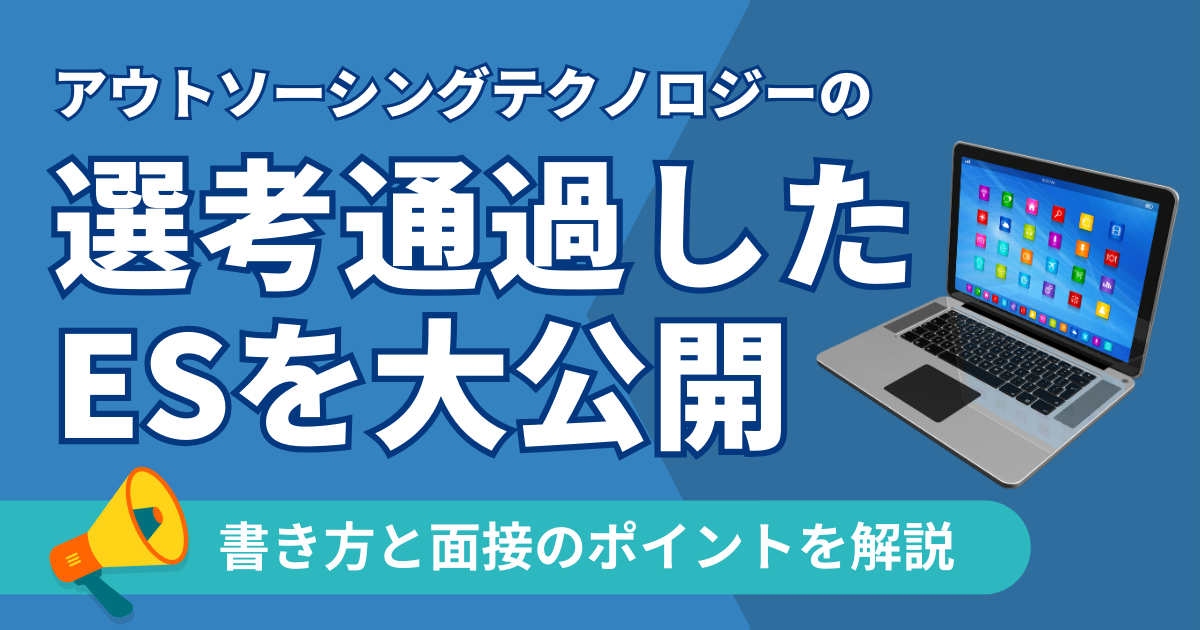ソリューションエンジニアを志望している理由をご記入ください。(600文字以内)
技術力を持って課題解決を行う事で、企業や社会に新しい価値を提供したいからです。アルバイトで業務が自動化されたことによって従業員の負担が減り、本来時間を割くべき業務に注力できたことから、ITは新たな価値創造の手助けになると実感しました。また、3年間生徒の大学受験をサポートした経験を通して、人に寄り添い、成長を支えることにやりがいを感じました。その際に私が意識していたことは未知の分野においても自ら学ぶことです。実際に医学部志望の生徒を担当した時、特殊な医学部受験について学ぶため、本やインターネットだけでなく、知り合いの医学部生から情報収集することや、医学部志望生徒対象の面接練習会に参加し、知識や指導技術を身につけました。医学部受験がなくとも生徒からの信頼を得ながら指導し、医学部合格に寄与することができました。これらの経験から確かな技術力を有するシステムエンジニアとして、企業や社会の課題を解決し、持続可能な社会へと貢献していきたいと考えています。貴社は「日本を強くする」を目標に、国内市場のDX化の促進に貢献しています。私が関心を持つ日本の医療や教育の社会問題に挑む最適な場所だと考えました。マルチベンダーとしてソフト、ハードともに多様な商材を扱うという利点と自身の強みである「課題解決への粘り強さ」を掛け合わせることで、お客様に最適なソリューションを提供していきたいと考えています。
学生生活で力を入れたことを1つ以上、最大3つまでご記入ください。(30文字以内)
アルバイトで生徒の面談出席率を向上させたこと。
研究で失敗を繰り返していた操作を成功させたこと。
サークルでコロナ禍の活動としてSNS投稿リレーを行ったこと。
学生生活の取り組みの中で、自信を持ってやり遂げたと言えるエピソードは何ですか
。その背景と、あなた自身が取った行動、その結果をできるだけ具体的にご記入ください。(600文字以内)
アルバイトでグループ面談の生徒出席率を向上させました。この面談はスタッフ1名と生徒数名で毎週行っており、校舎内の複数グループで生徒の面談欠席が課題となっていました。自身の受験経験から、校舎の生徒全員にとってモチベーションを維持できる環境が必要だと考え、5名チームで改善に取り組みました。分担して普段の面談の様子を見学したところ、面談のルーティン化による参加意欲の低迷と、グループ内で生徒同士の関係性構築が不十分であることが原因だと考え、2つの策を実行しました。1つ目は面談に変化をつけることです。生徒を飽きさせないためには毎週違う話題の提供が必要だと考え、メンバーと検討した面談のトークトピックをもとに毎週資料を更新し、全グループで活用してもらいました。2つ目はグループ対抗ランキングです。グループ内に連帯感を生むため、面談の出席率や勉強の進捗率を得点化し、ランキングを競うイベントを実施しました。私は、チーム内の役割決めとチーム外のスタッフとの折衝を担いました。校舎規模でイベントを実施し、生徒全員に影響を与えるためにはスタッフ40名全員の協力が不可欠でしたが、一部反対意見もありました。そこで感情と利益の面から説得することで徐々に協力の輪を広げていき、スタッフ全員を巻き込むことができました。以上の2つの策によって、校舎の面談出席率を平均50%から70%へと向上させることに成功しました。
富士通の「パーパス」を踏まえて、あなたが富士通で挑戦したいことをご記入ください。(600文字以内)
ヘルスケア領域のDXを推進し、地域全体ひいては日本全体で連携した医療体制を実現したいです。理由は2つあります。1つ目は患者と医療従事者の負担を減らすことができるからです。現在は個々の医療機関で情報管理されており、別の病院を訪れた際には病状の説明や検査で二度手間が生じています。実際にかかりつけ病院で親知らずの抜歯ができず、大病院を紹介してもらいましたが、検査や手術日調整のため抜歯までに3回の診療を要しました。この経験から患者の情報を電子化し、複数の病院で共有することで、患者の来院タイミングの減少や医者同士の診療方針の連携など医療の効率向上に繋がると考えました。2つ目は少子高齢化問題があるからです。特に地方では医師不足の課題も生じており、医療機関以外の組織との連携も求められます。地方で暮らす祖父が入院した際、同時にひとりで生活する祖母も心配になりました。この時、病院と自治体や介護サービスが連携し、入院患者やその家族までもサポート可能であれば人々の安心な生活を守ることができると考えました。以上のことから、貴社が有する電子カルテのノウハウや多くの地方自治体との連携を基に地域医療ネットワークを築き、貴社が目指す持続可能な社会の実現に貢献したいです。自身の強みである「観察力」と「課題に対する粘り強さ」は、地域医療における課題を的確に捉えた解決策提案に活かすことができると考えています。