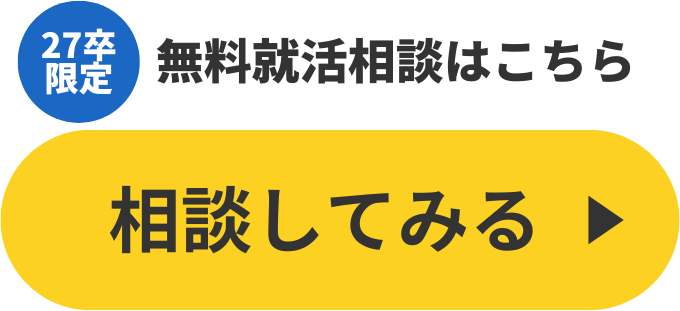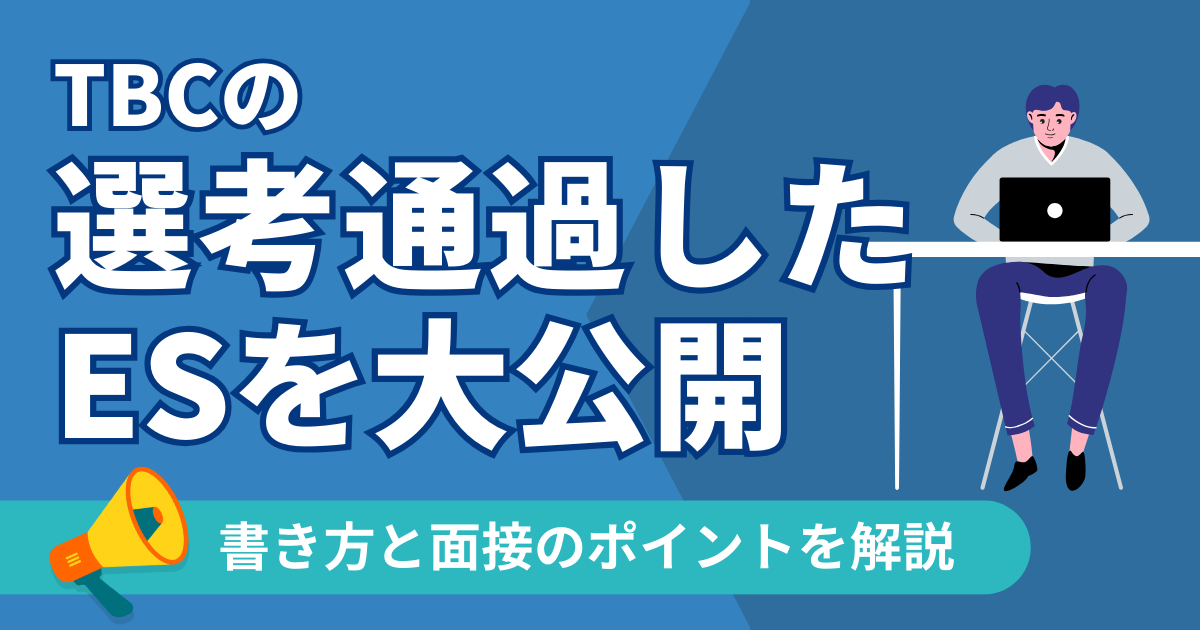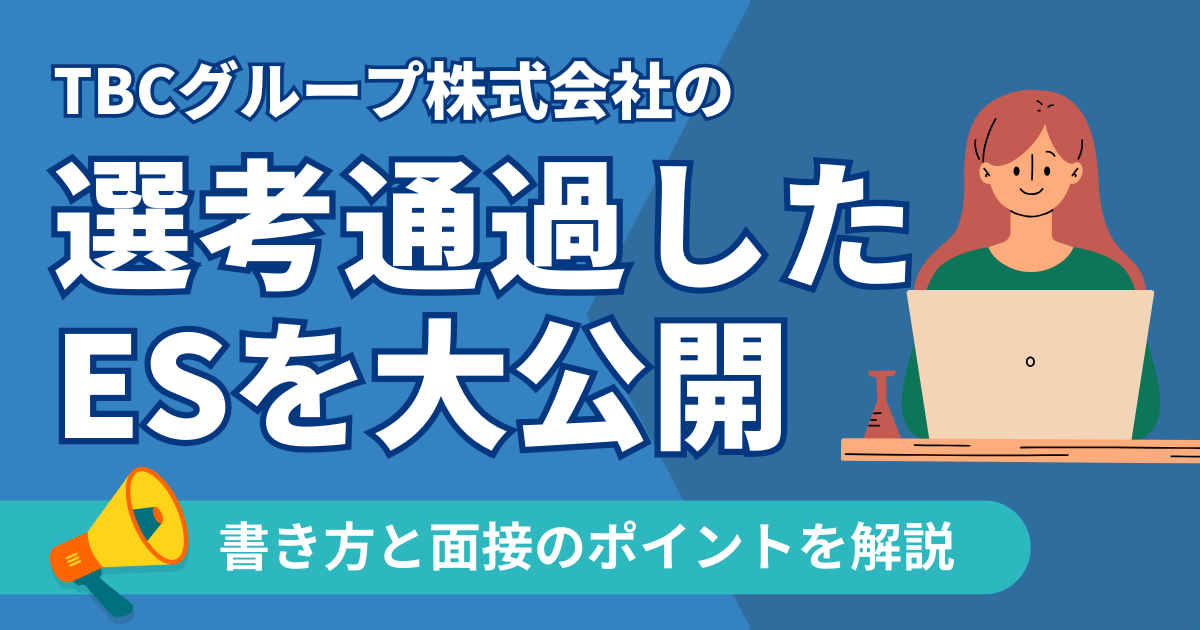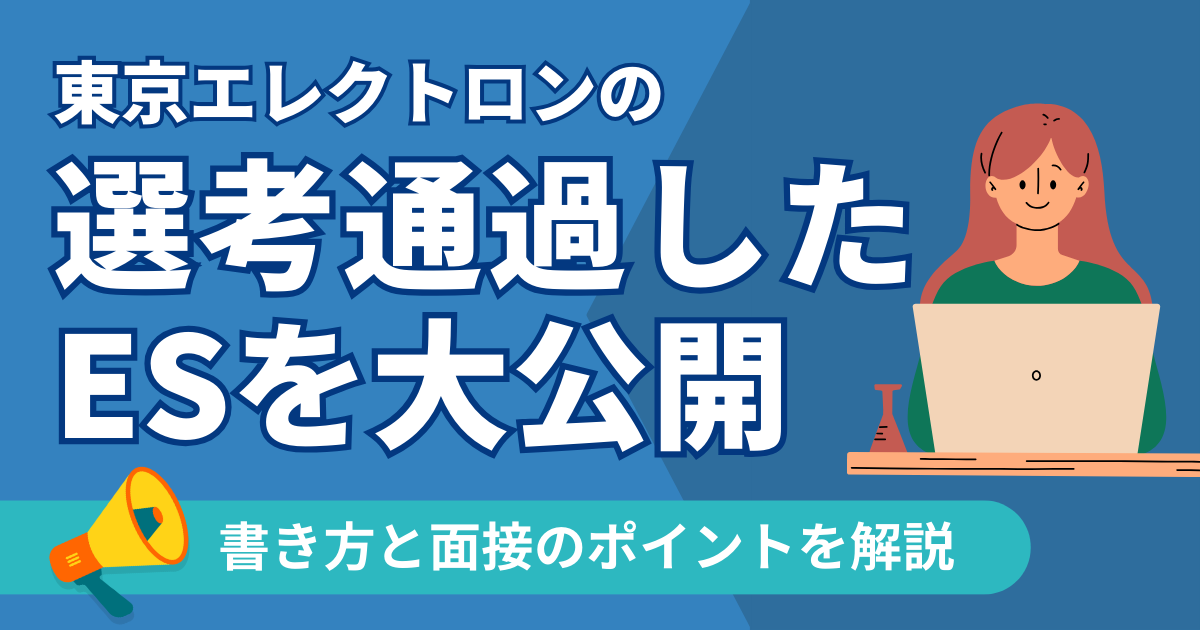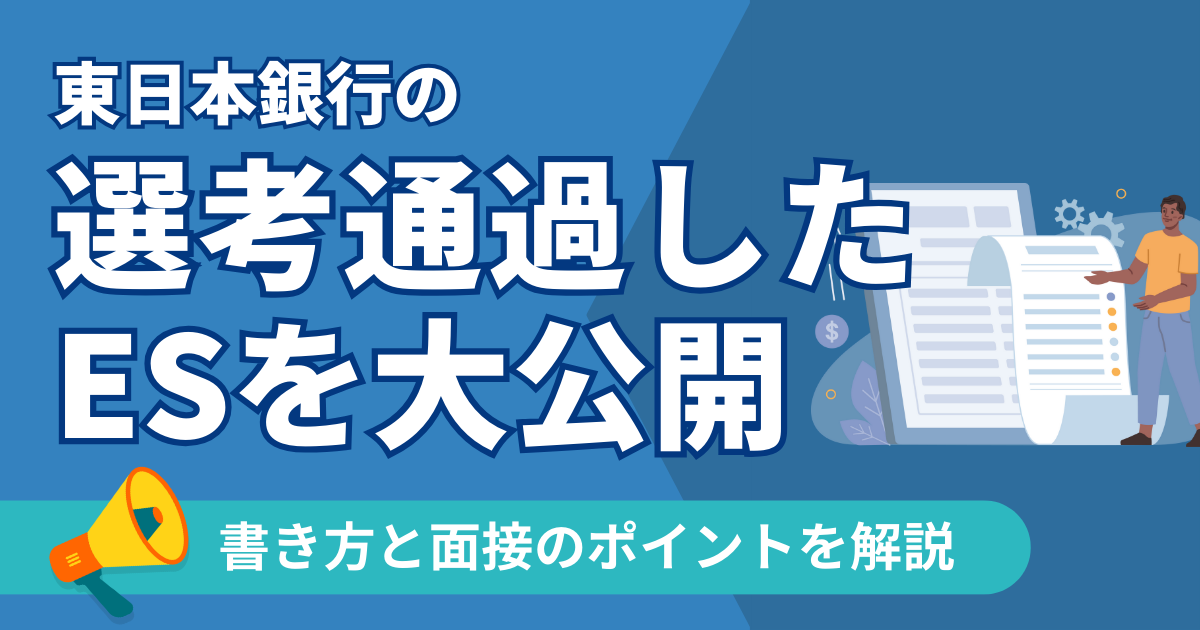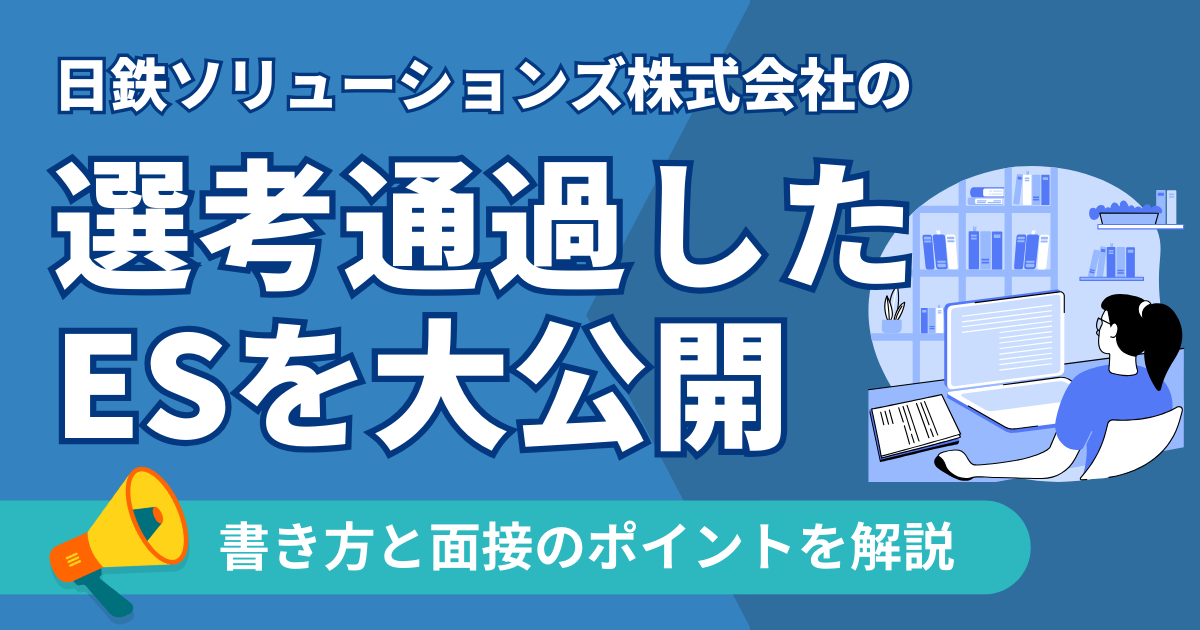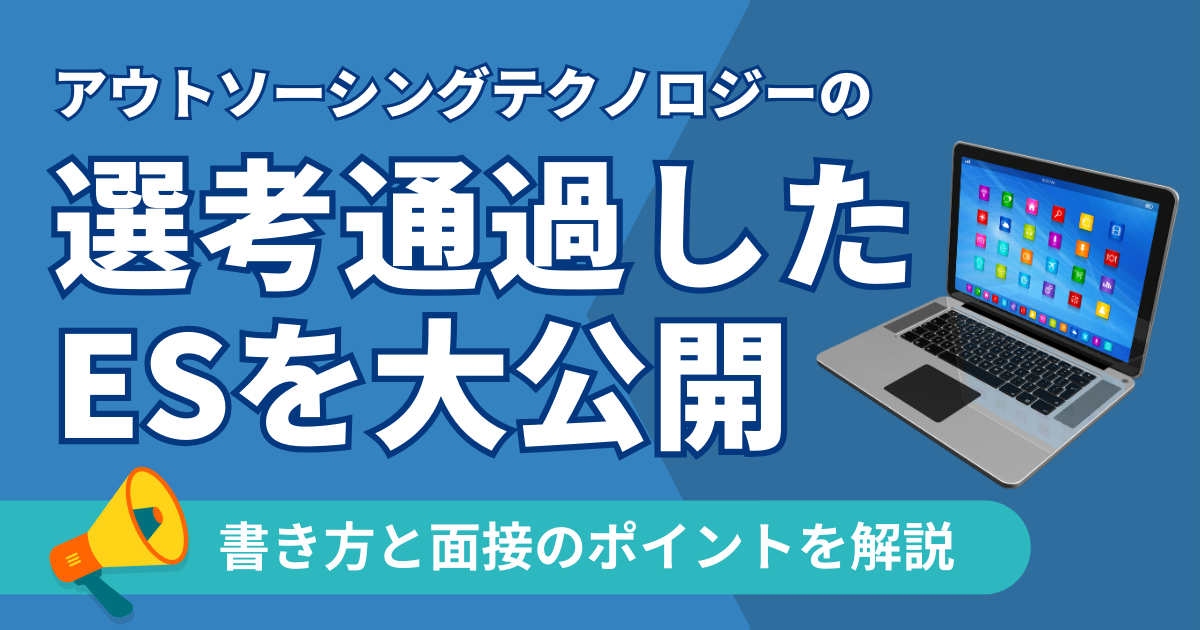25年卒
女性
成蹊大学
ES情報
学業、ゼミ、研究室などで取り組んだ内容(250以上400以内)
学業では、主に○○を学んだ。特に必修科目である「○○」という講義に注力した。この講義では毎週、難易度の異なる3問の○○課題が出された。最高難易度の3問目を諦める受講者が多い中、私は技術向上のために挑戦した。作成したい○○のフロー図を描く、エラー文の意味を調べながらデバッグする等の工夫を重ねて勉強することで、3問目をクリアできるようになっていった。その結果、最高評価のSを取得することができた。研究室では、テレビやラジオの収録時に発生する△△である「△△」の◇◇を用いた自動検出をテーマに実験に取り組む予定である。現在はこの実験に向け、参考文献集め等の準備を進めている。
今までで一番困難だったこと、苦労したことは何ですか?また、それをどのように乗り越えましたか?(250-400)
○○学習のオンラインインターンシップでチームリーダーを務めた経験である。ミッションという5段階の課題が与えられており、我々は全メンバーのミッション3クリアを目標とした。しかし私は、チームにとって質問し易い雰囲気を作り出せずにいた。そこで、以下の2策を実施することにした。(1)個人チャットでの連絡:グループチャットでの発言が憚られている可能性を考慮し、個人チャットでメンバーに質問が無いか逐次確認した。(2)ZOOM勉強会の開催:文章だけでは伝え辛い質問が存在することを認識し、画面共有を活用しながら口頭で質問できる環境を整えた。またチームで共に作業し、親交を深めることも狙った。これらの対策の結果、1日0通だった質問が1日1通以上届くようになり、目標も達成できた。さらに、日報提出時に当日感謝を伝えたいメンバーを1人選出する制度があり、その最多選出者である私は「チームMVP」として表彰された。
ご自身にとって「チャレンジだったな」と思う活動(250-400)
研究室でのPCの組み立ての取り組みである。教授がPCの組み立てに興味がある人を募り、参加を希望した。しかし希望者は私のみであった。そこで、参加者を集めるため研究室メンバーに交渉することにした。その間、研究室では卒業論文のテーマ決めを個々で行っていた。テーマ決めが煮詰まっている人に「気分転換にどう?」等の声掛けをすると、声掛けした四人のうち二人のメンバーが参加を希望してくれた。それからは、私含めた三人が組み立て係、説明書を読む係、インターネットで調べる係に分担し、知識を深めながら作業を進めた。また、参加していないメンバーも時々様子を見に来てくれるようになった。結果、四日間の活動で組み立てを完成し、問題なく動作することが確認できた。また参加メンバーからは、「参加してよかった」という言葉をもらうことができた。この経験から、積極的にコミュニケーションを図って協力を求めることの重要性を学んだ。
自己PR(250-400)
私の強みは、共感力である。高校時代、各高校の調理部が独自で考案したクッキーを競う「クッキー甲子園」というイベントに参加した。私は部長と仲が良く、部活後の作業を手伝う中で部長の悩みを知った。それは、30人以上の部員全員の士気向上が難しく、部長自身も兼部の忙しさから調理部に全て注力出来ないというものであった。そこで部長の気持ちに寄り添い相談に乗り、部長の思いを部員に伝えた。また部員の悩みも聞き、部長と相談して解決策を提示した。すると部活に参加しなかった部員たちも徐々に参加するようになり、全体の士気が上がった。結果、我々は「○○親善大使賞」という優れたプレゼンテーションに贈る賞を受賞することができた。この経験から、私は人の気持ちに寄り添い理解する共感力を得た。そしてこの共感力を駆使して、クライアントのニーズを汲み取ることが出来ると自負している。