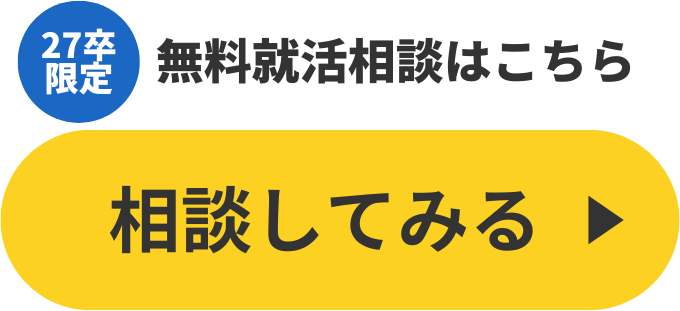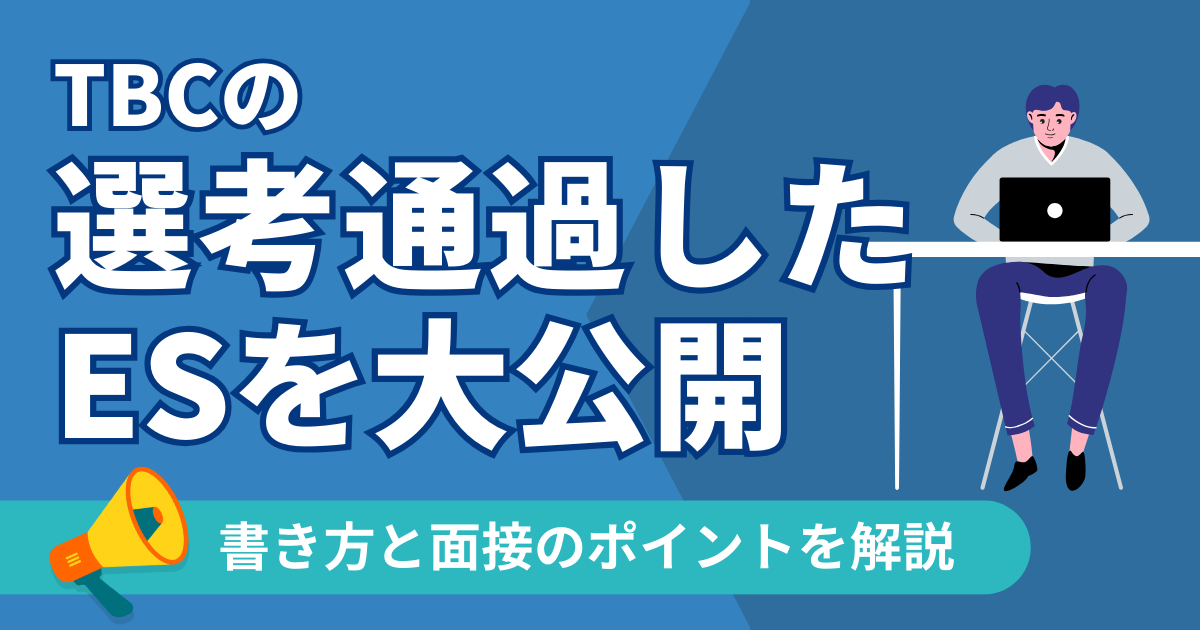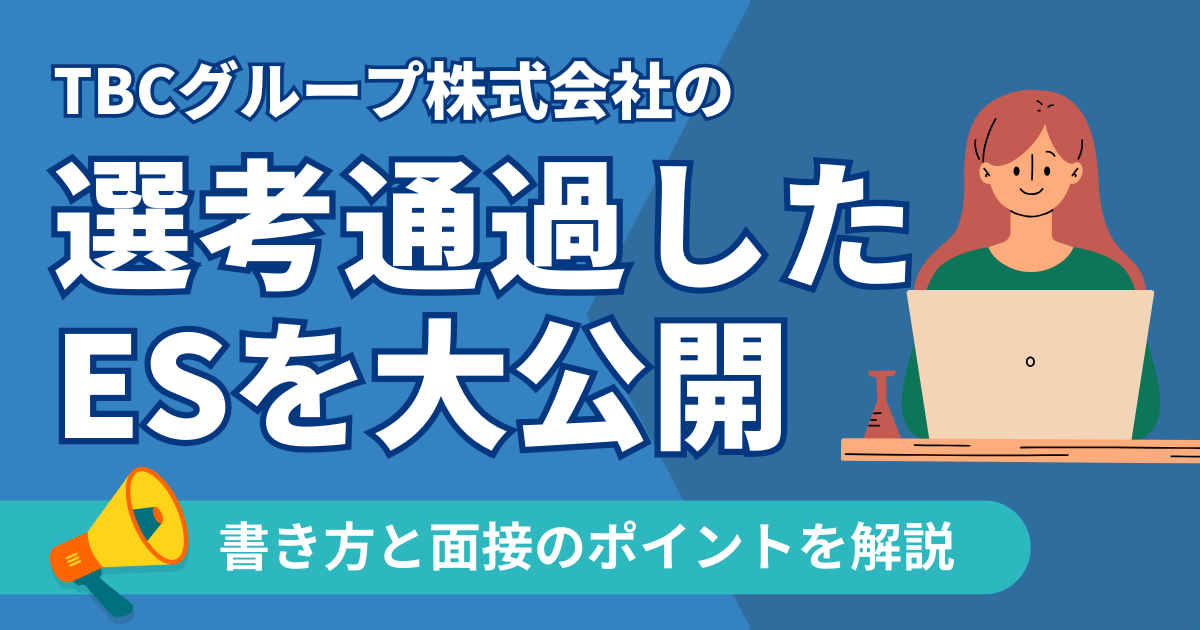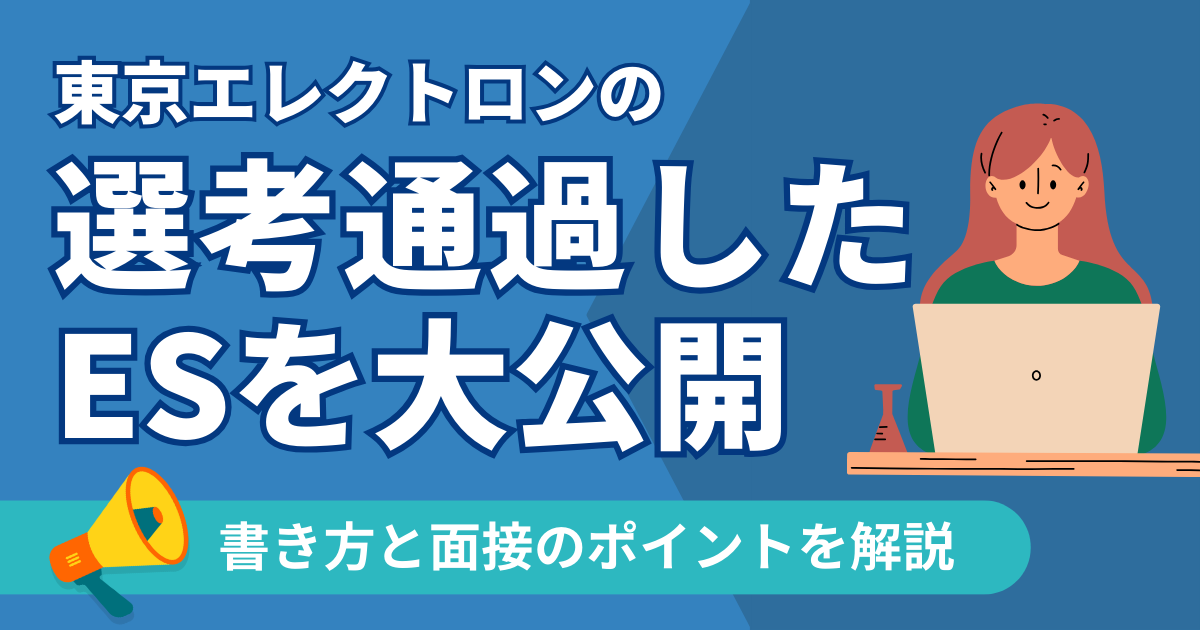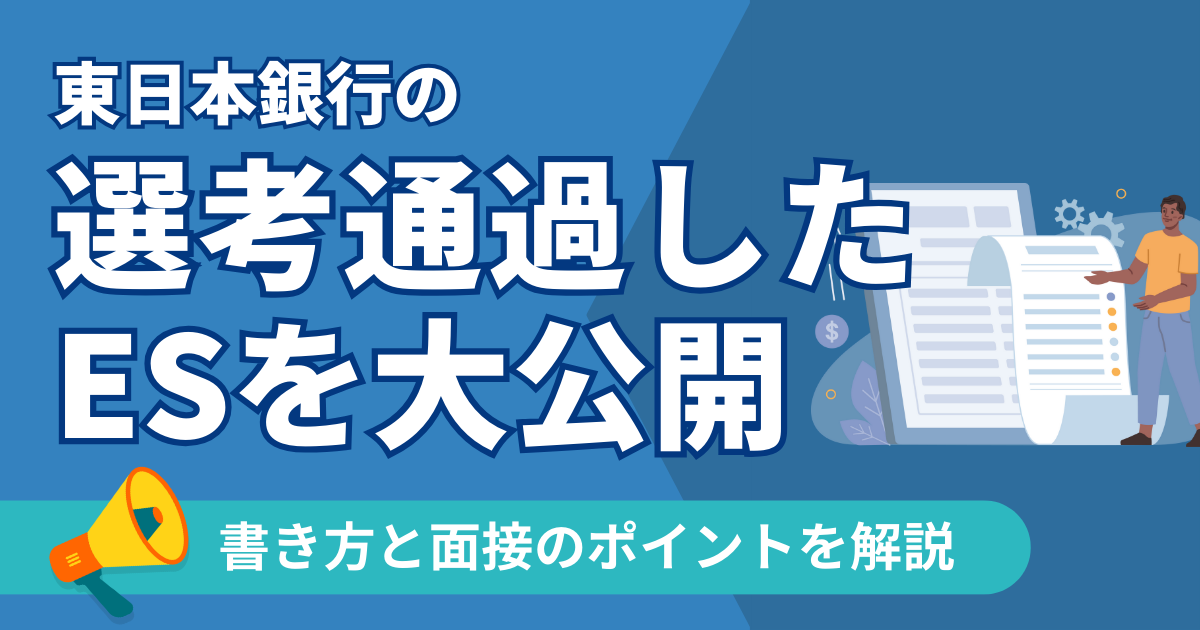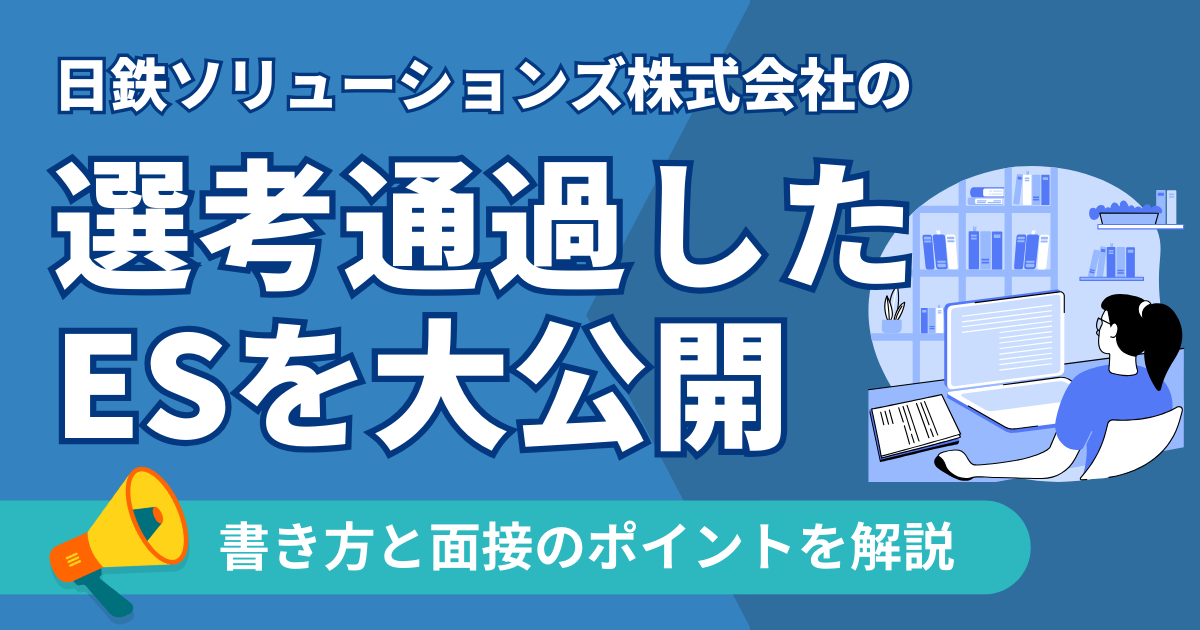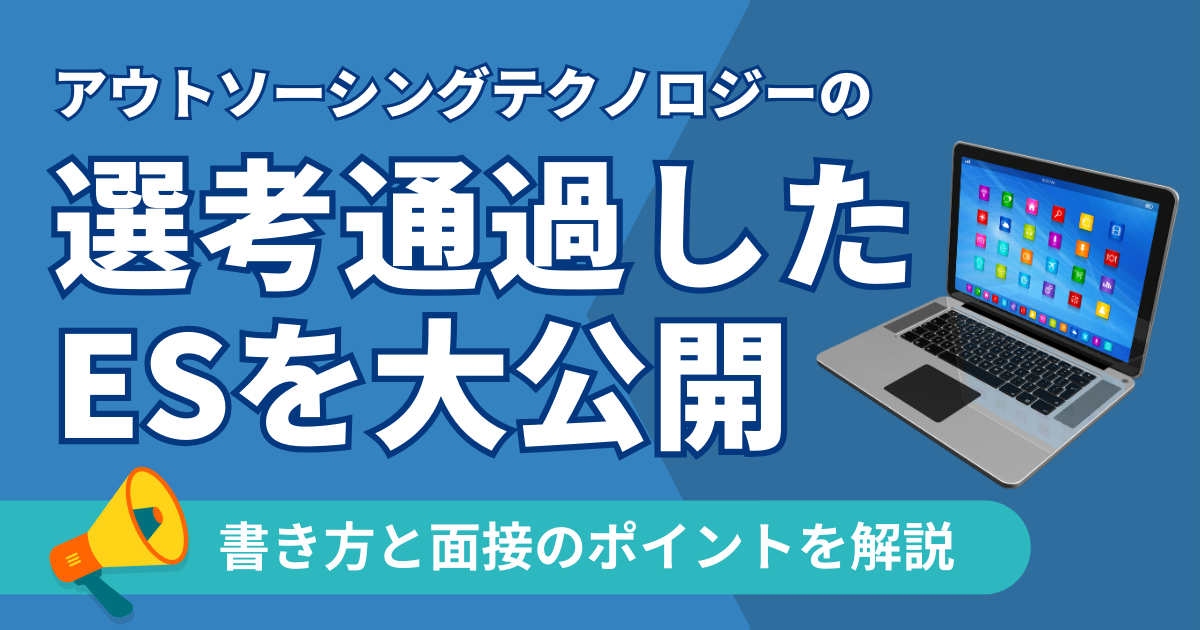25年卒
男性
慶應義塾大学
ES情報
厚生労働省を志望する理由
私はこれまでの人生の経験から、「誰もが安心して自身の幸せを追求できる社会」の構築に寄与したいと考え、人々の一生を支える制度を所掌する貴省を志望します。
私は低出生体重児として障害を持って産まれる可能性があった、と何度も両親から言われて育ちました。そのため、幼少期は漠然と障害などの生きづらさを抱える人々のために働きたいという思いを持っていました。その後私が大学に進学した後に、兄が精神疾患を患い、勤めていた会社を退職することになりました。
それまで自分より前を歩く存在だった兄がそのような状況に陥ったことで、人々の生活上のニーズに応じて様々な支援を行う社会保障や、人々が自身の能力を活かし社会につながる労働環境の整備の重要性を痛感しました。入省後は、政策に関わる様々なステークホルダーとの総合調整を通じて、多角的な視点から人々の生活を支えるための厚生労働行政に尽力していきたいと考えています。
厚生労働省に入省して実現したいこと
少子高齢化が進み地域の担い手不足が指摘されるなかでの「地域共生社会」の実現には、多様なアクターが積極的な役割を果たせるような公的な支援が重要であると考えています。
具体的には、以下の2点が挙げられます。
①労働者協同組合の活動の促進
地域のニーズへの柔軟な対応には、労働者協同組合の活動への支援が必要です。令和6年度から実施されたモデル事業から得られる知見を活かし、行政からの委託事業の有効性を示しつつ、設立したい事業者への積極的な周知広報も行い、裾野を広げていきたいです。
②コミュニティソーシャルワーカーの活動の支援
自分からは公的な支援を求めることが難しい人々へのアウトリーチでは、地域におけるコミュニティソーシャルワーカーが重要な役割を果たしています。各地域で行われている好事例を全国に周知広報しつつ、重層的支援体制整備事業を通じた財政支援を進めたいです。
厚生労働行政の関心分野(複数可)
重層的支援体制整備事業、労働者協同組合活用支援、障害者雇用
自己PR、長所、短所等
私の長所は強い情熱を持ち、周囲を巻き込みながら物事を進めることができる点です。
大学では福祉に関心を持ち、学内の障害を持つ学生の支援スタッフを、プロジェクトの開始当初から現在まで勤めています。講義等での直接の学生の支援だけでなく、キャンパス全体を見渡した包摂的な環境づくりをする必要があると感じ、教職員と学生を対象に障害支援の重要性を伝えるイベントを主催しました。広報用のポスター作製や内容の決定等を、私を含む4名の学生のみで行う必要がありましたが、各々の得意な分野を活かし準備を進め、無事開催しました。
短所としては、一つのことに集中するあまり、時として視野が狭くなってしまう点です。そのようななかでも、意識的に物事の優先順位をつけ、必要なことを着実に行えるように気を付けています。
困難に直面した際の具体的なエピソードとそのときにとった対応
予備校でのアルバイトで、生徒たちが自身の夢と志望校への思いを綴る作文の作成を推進するリーダーになった際に挫折を経験しました。
担当に就いた1年目では、自身の情熱のみでプロジェクトを推し進めてしまい、他の職員との連携がままならず、作文の提出率が低く留まってしまいました。その挫折を活かし、2年目に再度担当に就いた際には、他の職員の協力を仰ぐため私が作成したプランについて全員の意見を仰ぐ場を設けつつ、スタッフ一人ひとりの能力を把握し、校舎全体で取り組みが行えるような体制の構築に力を注ぎました。その結果、全国で達成したのは2校のみである、作文の提出率100%を実現することができました。
その経験から、他者と協働することで大きな成功を収めることができること、そして時には冷静に事態を見極め、有効な手立てを打つ必要があることを学びました。