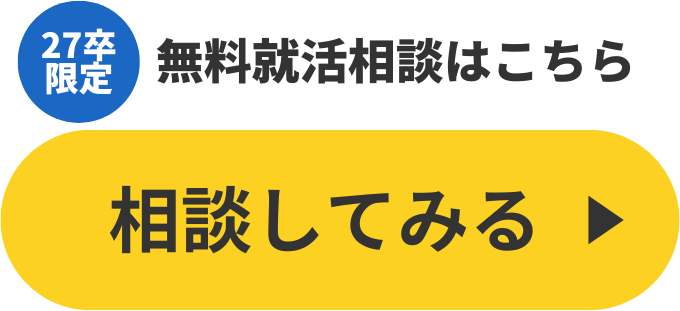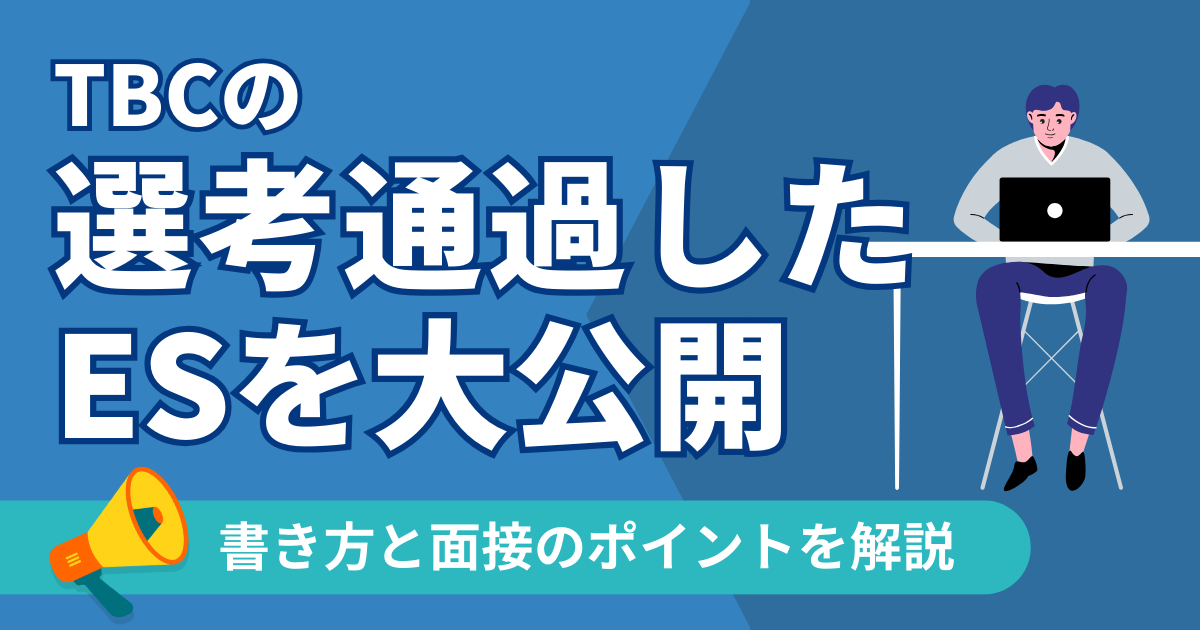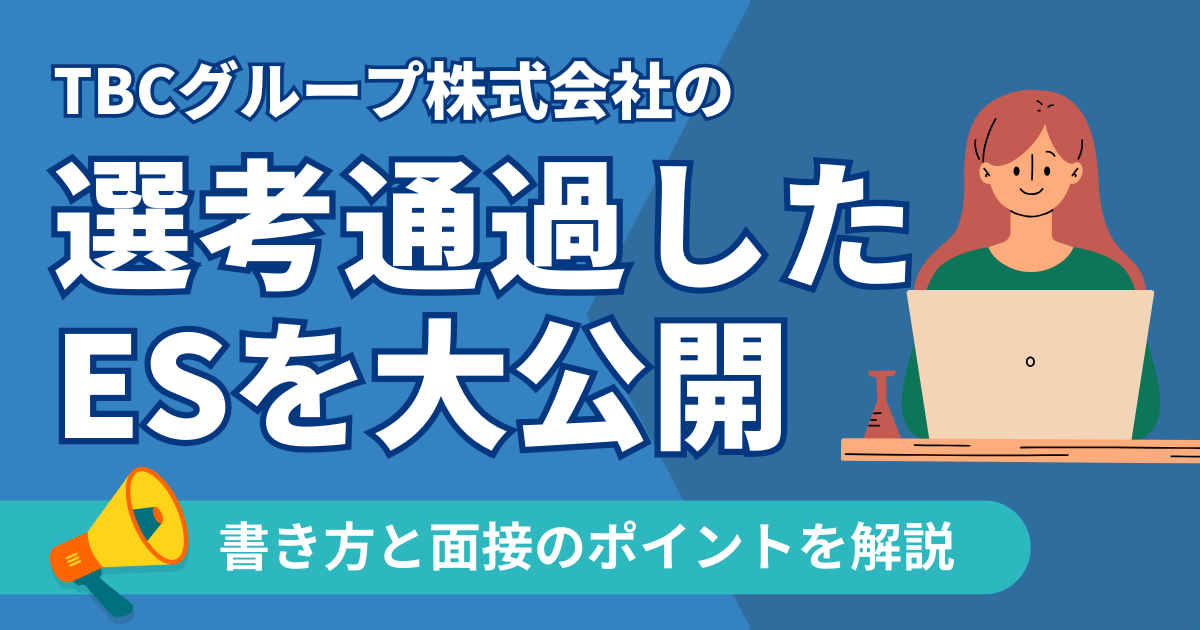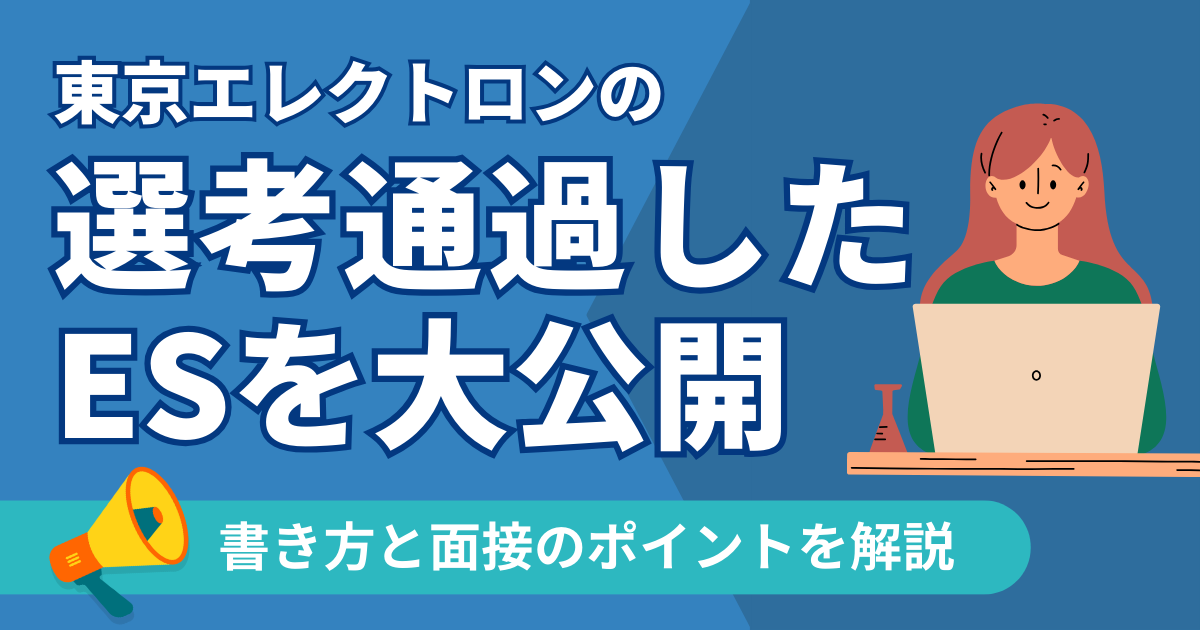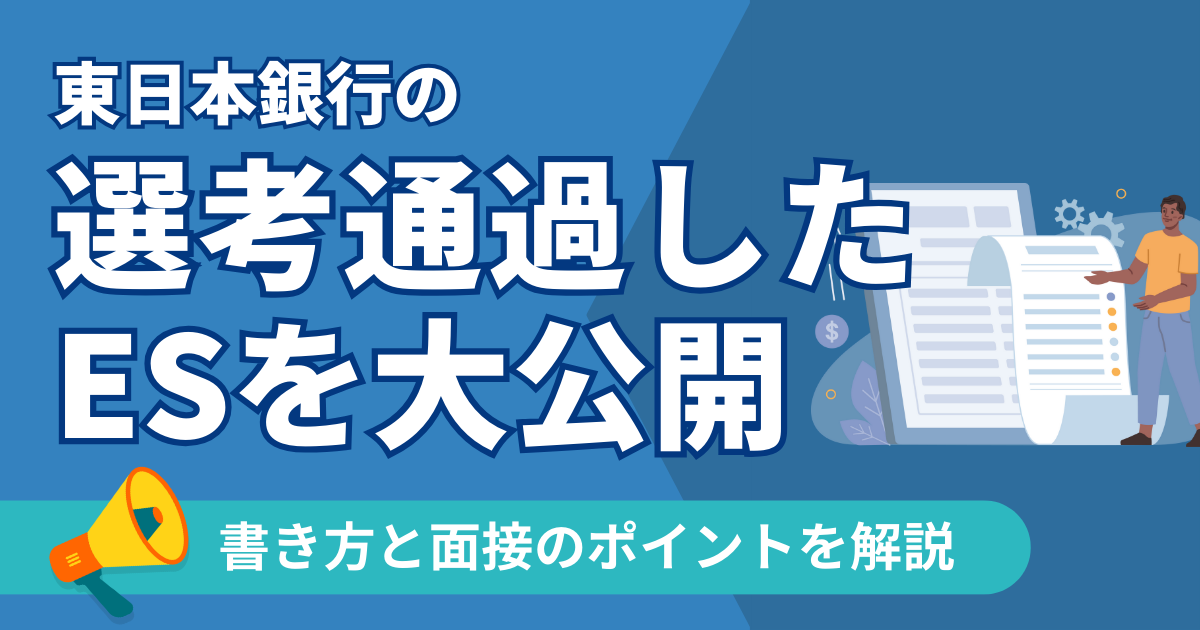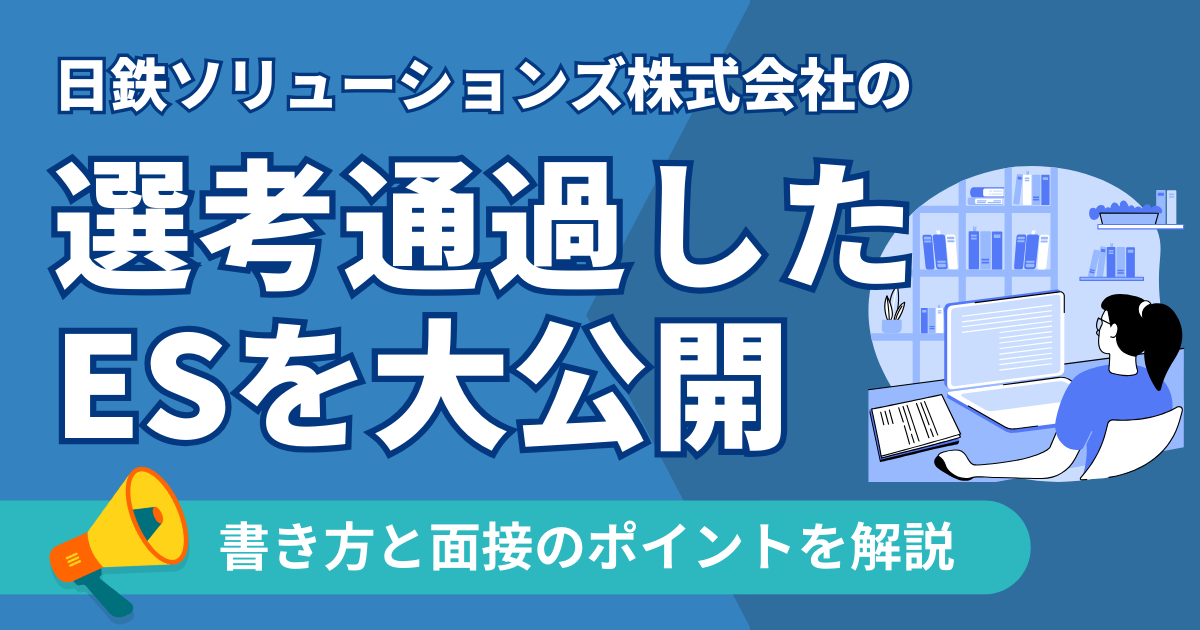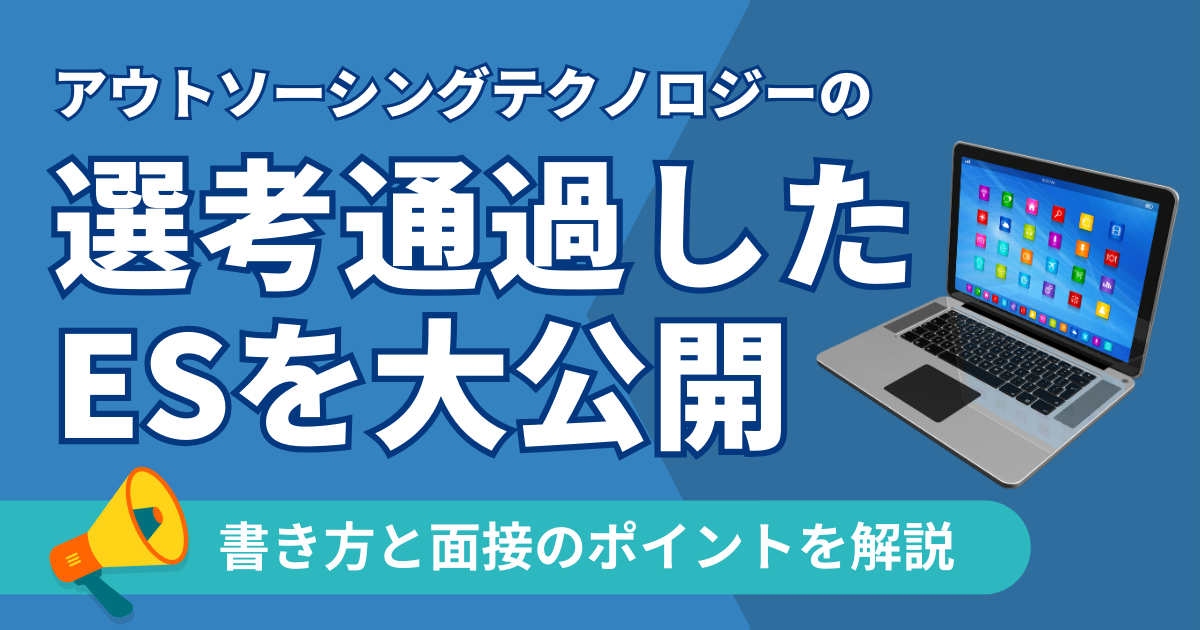学業、ゼミ、研究室などで取り組んだ内容
「日本の大学における推奨電子機器の特性と傾向」の研究を行った。全国の大学の電子機器推奨スペックを分析し、〇〇大学〇〇学部の貸与電子機器の妥当性を検証することを目的とした。データ形式が統一されていないため、評価軸の設定に苦労したが、主成分分析とクラスタリングを用いて、学部ごとの傾向を客観的に可視化した。
結果として、貸与電子機器の性能が全国平均より低いことが明らかとなり、学内提言を行った。この経験から、データ分析を通じて情報を整理し、課題の本質を構造的に捉える視点を学んだ。
自己PR
「誠実な努力」
飲食店でアルバイトをしていた。今ではキッチン業務とホール業務をこなし指示を出す立場となっているが、入りたてはキャベツとレタスの違いも分からないほどできの悪い新人だった。その時の課題として、以下の2点があった。1.10分以上お客様を待たせてしまっていた。2.盛り付けがきれいではないと先輩から注意を受けていた。
そこで、次の取り組みを行うことで課題解決を目指した。1.忙しい時間帯にも入ることで、ミスの出やすい環境下で考えながら動ける力を鍛えた。2.先輩の動きを細かく確認し、改善した。
例えば、ドレッシング類をよく使う順に並び替えておくことやより無駄のない動線に変えた。その結果、お客様から「素早い提供にも関わらず盛り付けがきれいだ」と声を寄せていただけるようになった。この経験のように、目立たない改善であっても真摯に向き合い、地道に努力することが私の強みだ。
学生時代に最も打ち込んだこと
「生徒の成績を上げ、やればできるという自信を持たせてあげること」
授業についていけない生徒を対象とした教育施設でアルバイトをしている。そのため、私が学生時代に抱えていた悩みとは別のポイントで躓く生徒が多く、わからないポイントの把握と教え方に悩む瞬間が多くあった。
そこで、課題解決を目指して次の取り組みを行った。1.コミュニケーションの時間を多くとることで、信頼関係を構築する。2.わかる部分だけ説明してもらい、生徒にできた部分があることを実感してもらう。3.フローチャートを用いて整理してあげられるように、参考書で勉強し直した。その結果、担当した生徒の多くはやる気を持って授業に来てくれるようになり、ある生徒は〇点から〇点まで成績を伸ばすことに成功した。
この経験を通して、相手に真摯に向き合い小さな躓きを一つずつ解消していく姿勢が、本質的な課題解決と信頼関係につながると実感した。