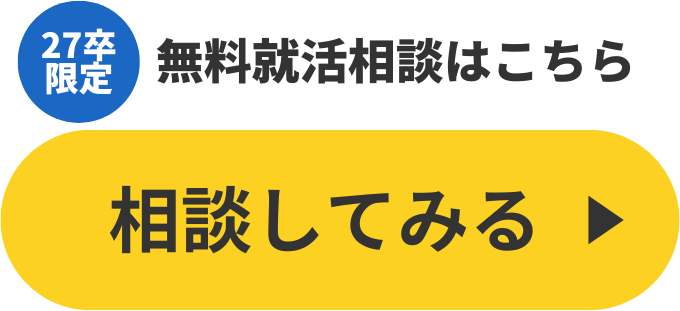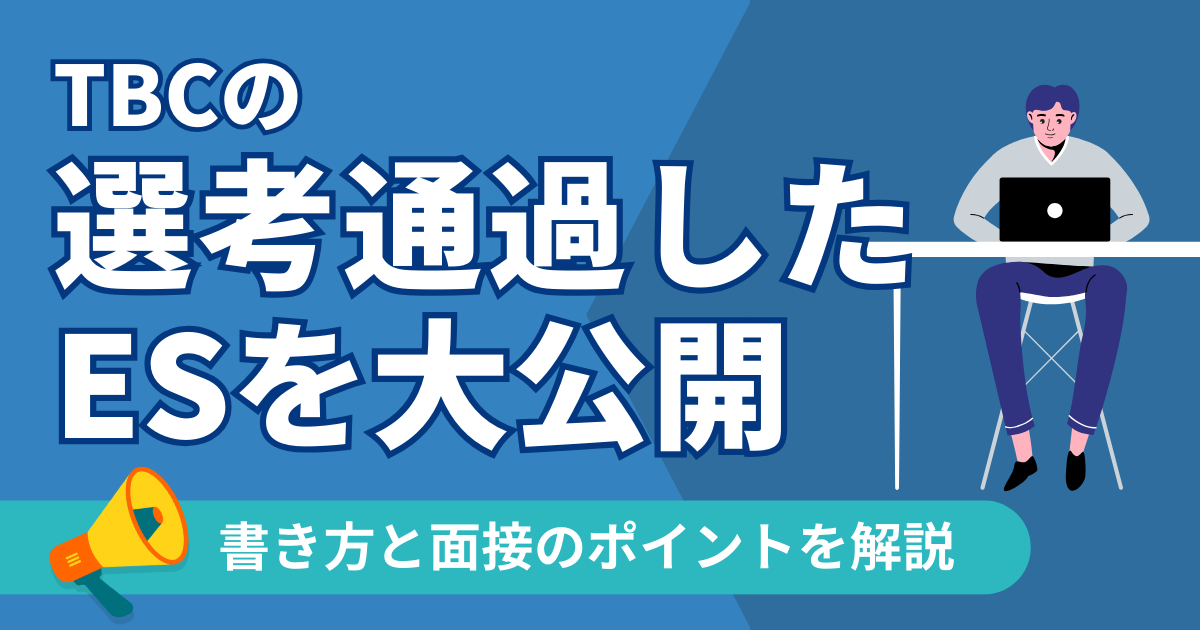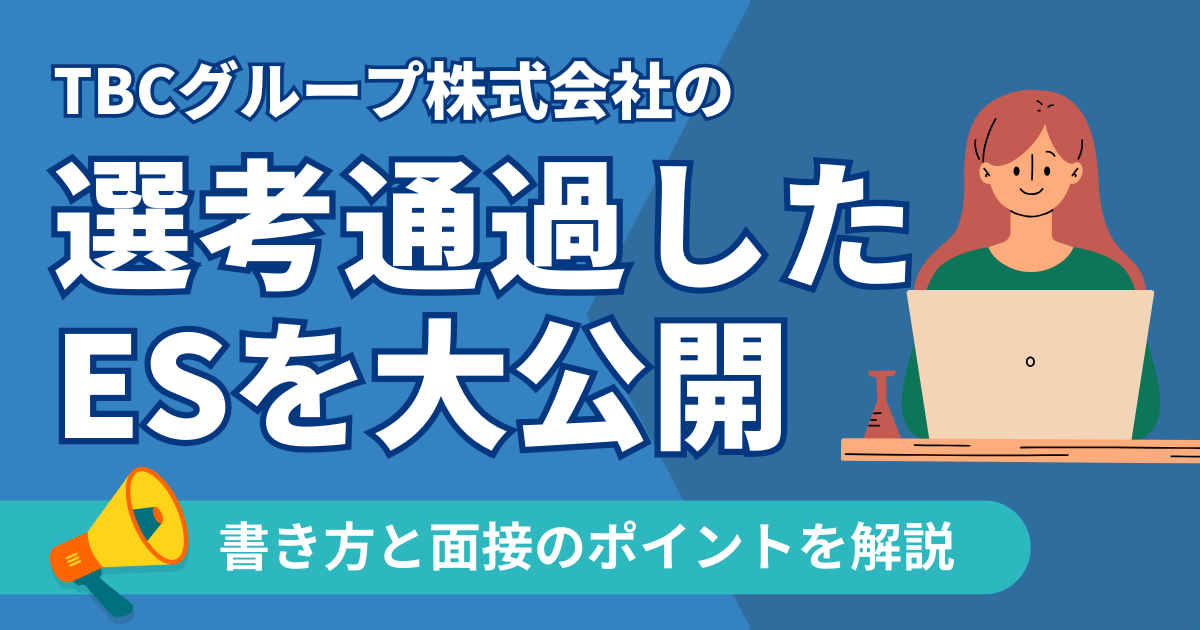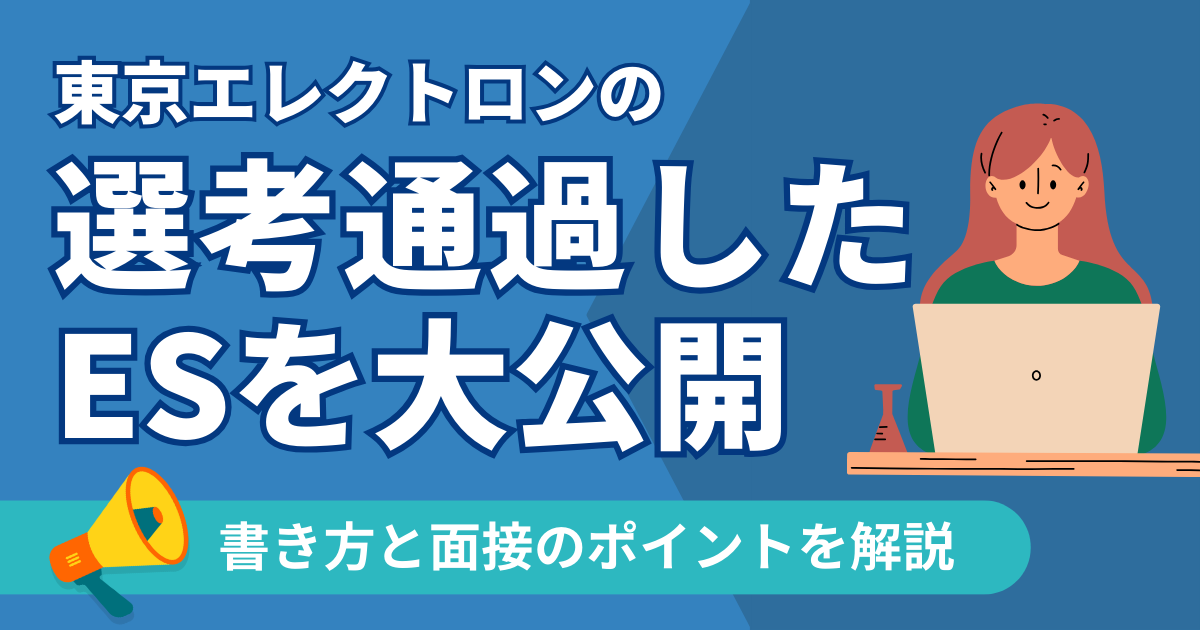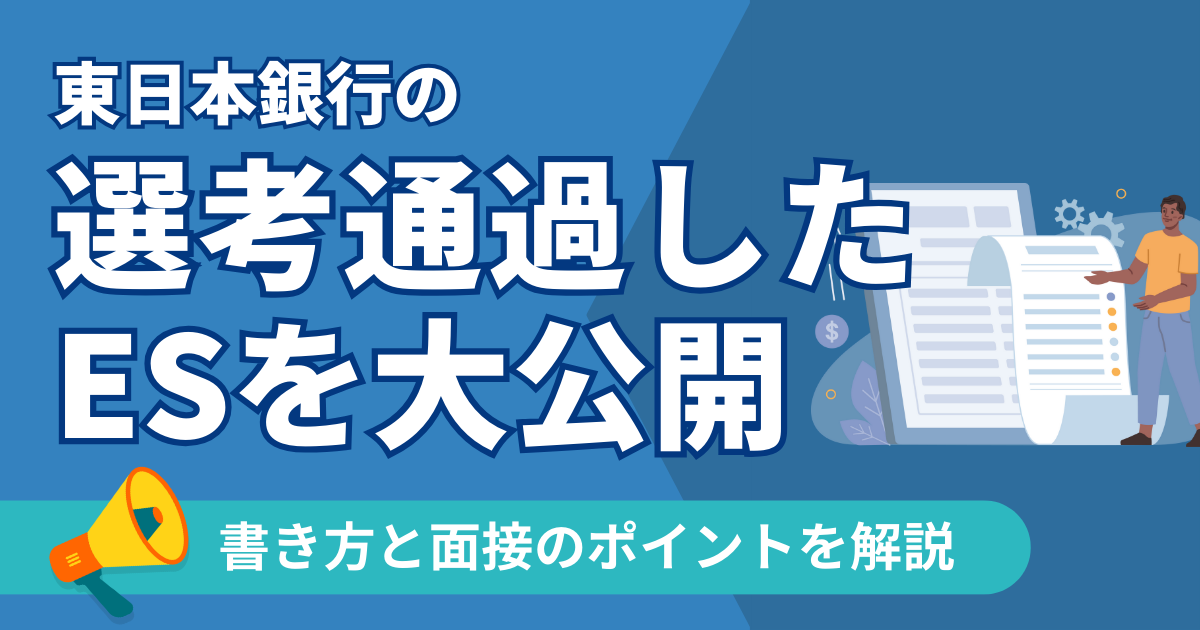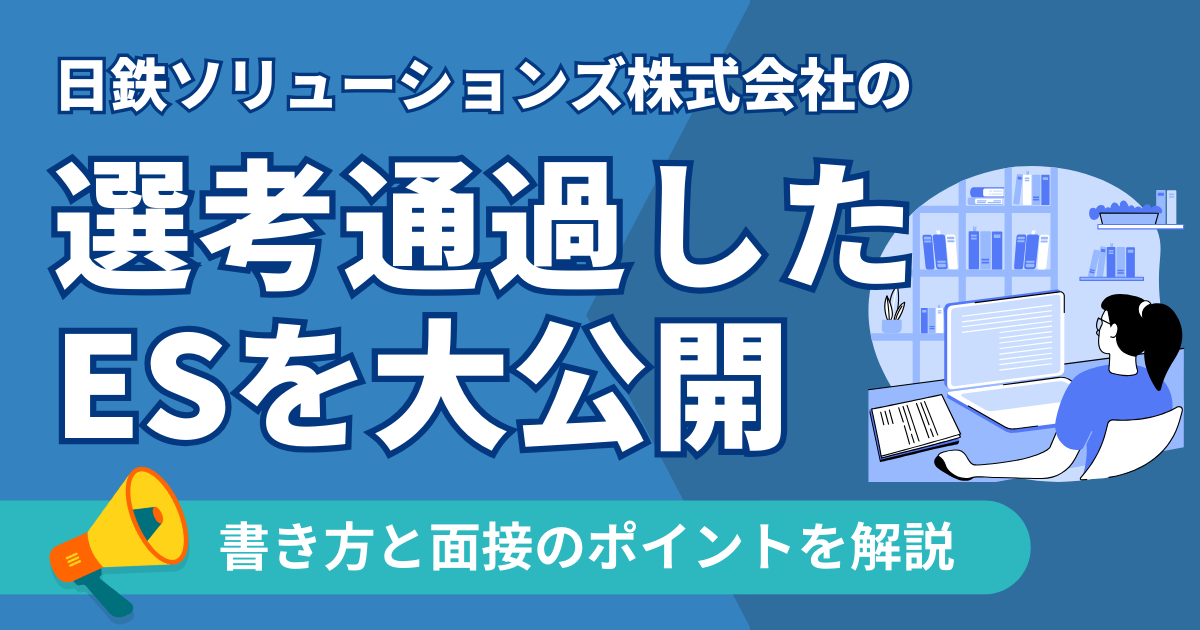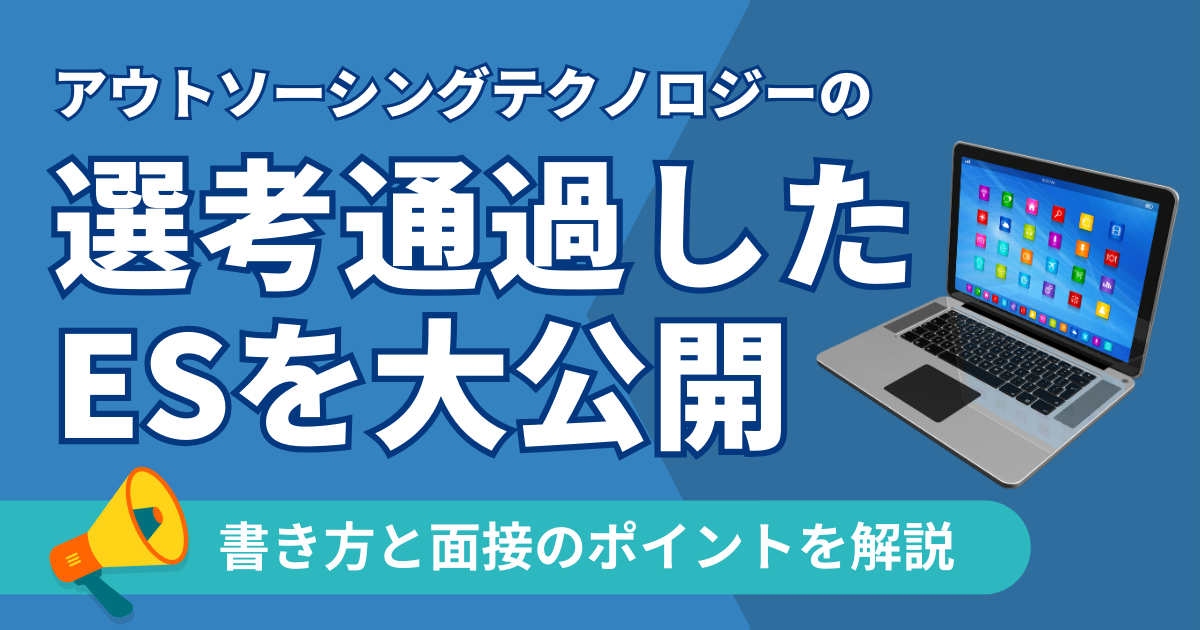25年卒
男性
芝浦工業大学
ES情報
選択した課外のうち1番アピールできる活動を一つ選んで、活動経験から学んだ事を記入してください。(100字以内)
選択内容:○○
この活動を通じて他者への理解と思いやりの大切さを学びました。また異なる学習ニーズや背景を持つ生徒たちと接することで、柔軟性や適応力が向上しました。
選択した分野/デバイスの中で、最も興味のあるものとその理由を記入してください。(100字以内)
選択内容:○○
センサは様々な環境のデータを収集し、集めたデータは多くの分野に応用できます。そのため、センサを使用した新しい技術が今後さらに発展する可能性が高いと考え、私はセンサに興味を持っています。
最も力を入れたクラブを記入してください。(100字以内)
中学校から高校までの6年間、陸上部に所属していました。高校では副部長を務めており、短距離専門の練習メニューの作成及び指導を行いました。その結果、後輩と信頼関係を築きながらお互いに成長出来ました。
学校の授業・演習課題・研究以外であなたが長期間かけて制作した物に関して、具体的な規模や期間、あなたの担当箇所・役割を記入してください。
◆制作期間
2023/4〜2023/7(3ヶ月)
◆制作したモノの担当箇所や役割を記入
ArduinoとProcessingを用いて、4人チームで自動車運転シミュレーションを作成しました。私はジャイロセンサのデータを取得し制御するプログラミングの作成と、映像制御のプログラミングの結合を行いました。また、進行を円滑に行う為、適切なタスクの分担や進捗管理表の共有と管理を行いました。
◆具体的な内容や規模について記入
大学のイベントで展示できる作品制作を目標にし、4人チームを立ち上げました。まず初めに、チームでどのような作品を作るか話し合いました。当時、自動車事故のニュースが話題になっていた事もあり、車を運転している時に突然飛び出してきた人を、轢かないように避けるシミュレーションを作成する事にしました。次に、制作に必要なタスクの洗い出しと役割分担を行い、各タスクの期限をガントチャートで管理しました。私の担当は、車のハンドルを動かした事を検知する為に必要な、ジャイロセンサの制御プログラミング作成と、メンバーがProcessingを用いて作成した運転画面を制御するプログラミングの結合といった2つでした。1つ目のタスクは、MPU6050というジャイロセンサを使用し、Arduino IDEの開発環境を用いてこのセンサを制御しました。また、2つ目のタスクであるプログラミングを結合する際、このセンサは16Bitでデータ値を取得するのに対して、ArduinoとProcessingのシリアル通信では8Bitのデータしか送る事が出来ず、作業が難航してしまいました。しかし、仲間の協力によって上位Bitと下位Bitに分けてデータを送ることでこの問題を解決する事ができました。このように、チームワークを発揮する事で無事シミュレーションを制作し、イベントで披露する事が出来ました。
あなたがこれまでに経験した最も困難な技術的課題と、その解決のために行動レベルで挑戦した内容とその経緯、技術的解決策を具体的に記入して下さい。
ゼミの課題として、オペアンプを用いたオーディオスピーカーの作成に挑戦しました。オペアンプにはNJM2073Dを使用し、KiCADを使ってPCB設計を行いました。KiCADを使用するのは、この時が初めてで使い方に慣れていなかったため、先輩や友人にアドバイスを求めながらスピーカー作成を進めました。最も困難だったのは、KiCAD内で作成した回路の素子に、フットプリントと呼ばれる素子の形状を割り当て、現実世界の素子と対応させることでした。実際の素子に合わせるためには、地道に素子の足の長さや幅といったサイズを調べながら、フットプリントを割り当てる必要がありました。また、Autodesk 社の Fusion 360を使用してスピーカーの筐体を設計し、3Dプリンターで作成しました。結果として、必要な素子に対応するフットプリントを正確に設定し、PCBと筐体を完成させることができました。その後、完成したPCBに対応させた素子をはんだごて等を使用して回路を作成し、無事オーディオスピーカー完成する事が出来ました。この経験を通じて、地道な作業と情報収集の重要性と同時に、自分だけで作業するのではなく、周りと協力することの必要性を再認識しました。そして、困難な技術的課題にも前向きに取り組む姿勢が重要であることを学びました。
あなたが所属する組織(研究室、アルバイト先、クラブ、サークルなど)で発生した課題や問題に対して、原因分析や改善・解決策などあなた自身の思考や行動が問題解決に結びついたと考える具体的な事例を具体的に記入してください。(600文字以内)
私は、塾講師アルバイトを大学1年生から現在まで続けています。塾講師の仕事は、担当生徒の成績を上げて志望校に合格させる事です。しかし、生徒によって勉強の好悪や苦手分野の違いがあり、生徒毎に適切な授業の方法が異なるという課題があります。そこで、担当生徒とその保護者との面談を行い、苦手分野や性格を把握し、どのような授業を期待しているのかをすり合わせてきました。また、生徒が帰宅した後に他の講師や社員の方と、どのような授業を行うべきかのミーティングを行ってきました。そして月に一度、実力テストを作成し分野ごとの成績推移をグラフに記録しました。グラフにする事で、生徒自身がどの分野が苦手か一目で把握することができ、より生徒の勉強に身が入りました。結果、生徒との信頼関係を築きながら成績を伸ばし、志望校に合格させることが出来ました。そして、私自身もチーム内でのコミュニケーションを重視し、他の講師やスタッフと協力して生徒の成績向上に取り組む姿勢が身につきました。また、個々の課題や問題に対して継続的に取り組み、改善策を実行することの重要性を学びました。課題解決を行う事が出来た要因は、「情報収集力」と「情報を可視化する力」によって生徒のニーズを的確に把握し、それに応じた対応を行ったことだと考えます。
以下の年代をどのように過ごしたか総括し、どのようなところが今のあなたにつながっているか合わせて記入しなさい。(100字以内)
中学校
学級代表を3年間務め、クラスメイトが過ごしやすい環境作りに尽力しました。この経験が、私のコミュニケーション能力を向上させると共に、人々のニーズを理解して解決策を見つけようとする考え方に繋がっています。
高等学校
生徒会の役員と陸上部の副部長を務めつつ、新しい部としてギター同好会を発足させました。この経験が、主体的に自分の考えを行動に移し、集団の中で人々を取りまとめようとする動きに繋がっています。
大学・大学院
塾講師のアルバイトをしつつ、学習支援のボランティアを行いました。この経験から、自身の知識やスキルを周りの人のサポートや、人々に貢献をしようとする姿勢に繋がっています。
あなたが働くうえで大切にしたいと思う事を3つ挙げてください(50字以内)
・常に新しい技術や知識を取り入れ、日頃から商品やサービスをより良くするように考える向上心。
・失敗を恐れずに自分の能力を発揮して、継続的に取り組み続けるチャレンジ精神。
・チームメンバー間のコミュニケーションを円滑にして、仕事のパフォーマンスを向上させるような信頼関係。
任天堂のどのような所に働く場所としての魅力を感じるか簡潔に記入して下さい。(150字以内)
私が貴社に感じる魅力は2つあります。1つ目はゲーム業界最先端の環境で開発に携わる事ができる点です。2つ目は、チームとしての共同開発を行うことで様々な異なる視点やアイディアを共有し合える点です。これらの魅力は、この業界に必要な最先端技術とエンターテインメントの融合には欠かせないものだと考えます。
興味を持っている技術分野を1つ以上あげ、その技術のどのような部分に興味があるかお答えください。(600字以内)
① 半導体
理由:
私は半導体の高性能化及び小型化技術について興味があります。現在、IT化の浸透によってパソコンやスマートフォンといった、様々なスマートデバイスが普及しています。すると同時に、スマートデバイスに使用される半導体もまた、私達にとって身近な物になってきています。そして、半導体の高性能化及び小型化といった技術によって、これらのデバイスの性能が向上してきました。それはゲーム機も例外ではありません。例えば、1983年に発売されたファミリーコンピュータに、使用されていたCPUはMOS6502であり、そのプロセスは8μmです。しかし、2016年に発売されたニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータに、使用されていたCPUはR16であり、そのプロセスは28nmとなっています。これらCPUの大きさは約285倍の差があります。さらに、ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータはファミリーコンピュータに比べて、筐体のサイズが60%程度縮小しています。この例から分かるように、半導体の微細化により、ハードウェアの消費電力の低減や処理能力の向上といった高性能化だけでなく、小型化まで実現してきました。このような半導体技術の進化は、IT化や私たちの生活といった社会をさらに豊かにする可能性を秘めています。このような理由から半導体技術について興味を持っています。
②ワイヤレス給電
理由:
近年、電子デバイスの普及に伴ってワイヤレス給電技術に対する関心が高まっています。私もその中の一人であり、特にワイヤレス給電技術の将来性について興味を抱いています。初めに、このワイヤレス給電技術は、スマートフォンやその他のデバイスを頻繁に充電する必要性を軽減して、充電ケーブルやモバイルバッテリーを持ち歩くといった手間を省いてくれる可能性があります。つまり、電子デバイスの電力供給制約や、バッテリー容量や充電時間によって生じる移動制約が取り払われることが期待されます。実際に、2023年10月に行われた電気自動車実験では、充電スポットの上に車が1秒間停止するだけで、約100メートルの距離を走行するだけの充電が可能でした。このワイヤレス充電技術が実用化されれば、電気自動車の利便性が大幅に向上するだけでなく、環境に配慮された電子デバイスを開発出来る可能性が大いにあります。また、様々な産業や生活の分野で利用されることで、より便利で持続可能な未来を実現できるような魅了的な技術だと感じています。しかし、現在この技術は有線充電と比べて充電効率が低かったり、充電位置がズレると充電出来なくなるといった課題があります。私は、今後登場するそれらの課題を解決するために打ち出される解決策にも興味があります。