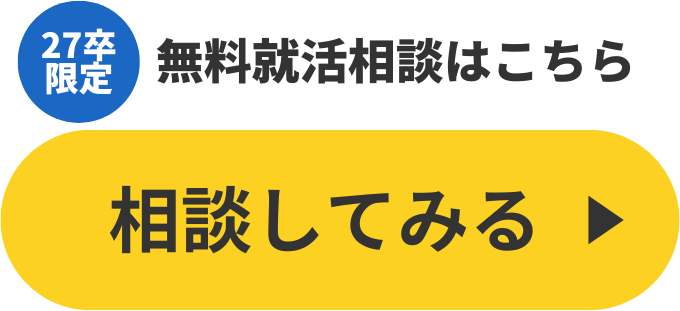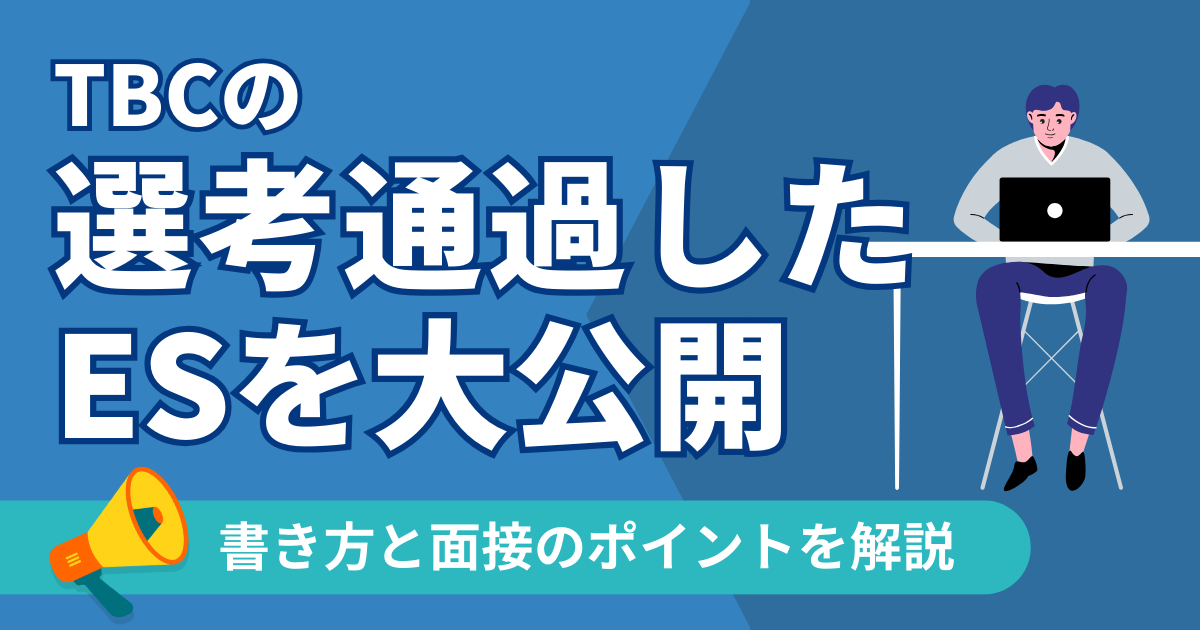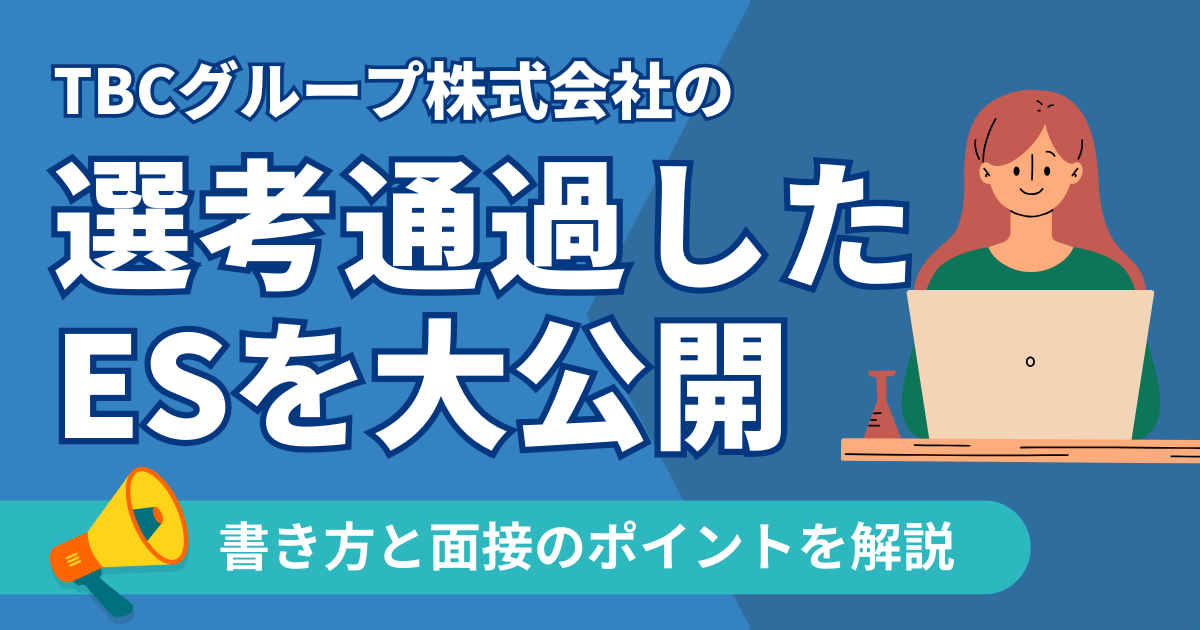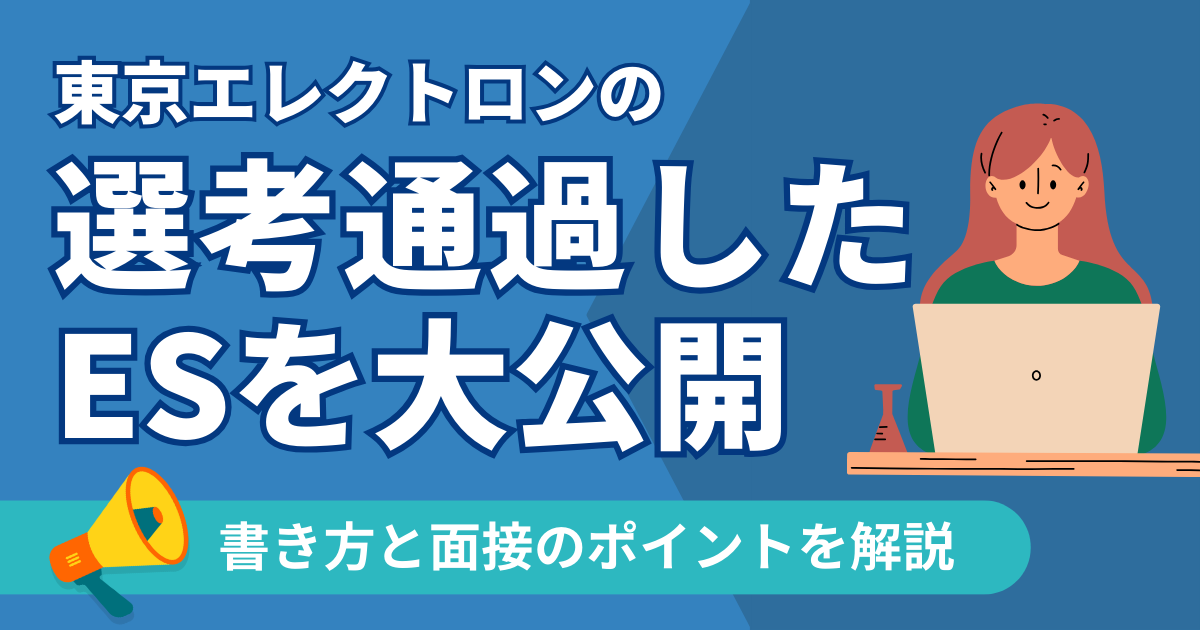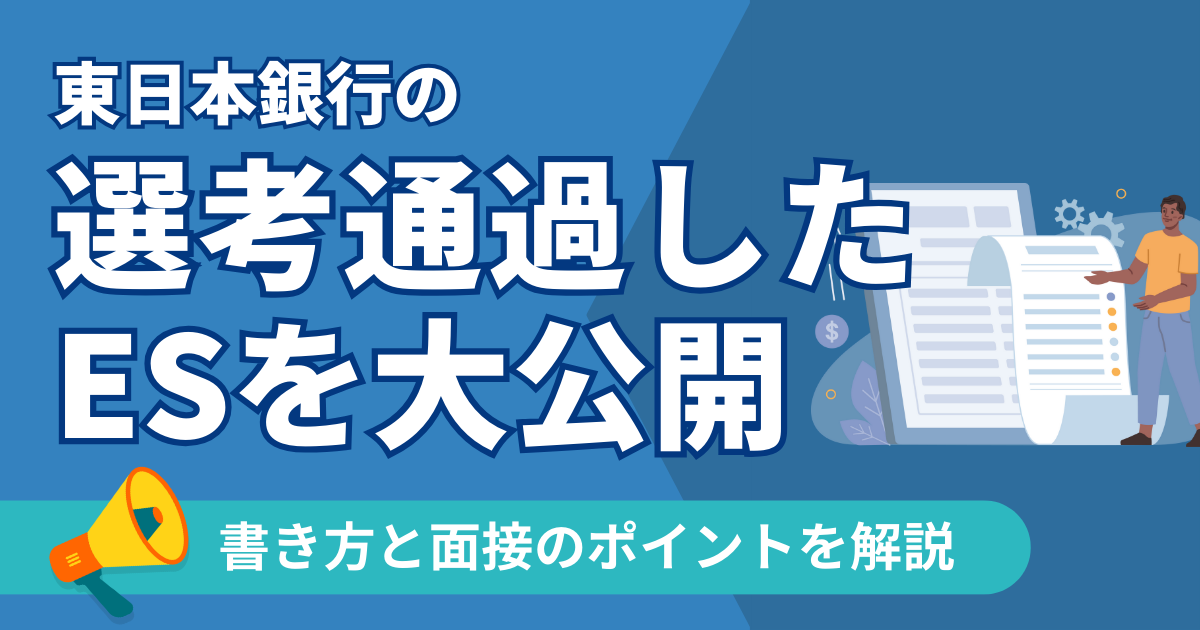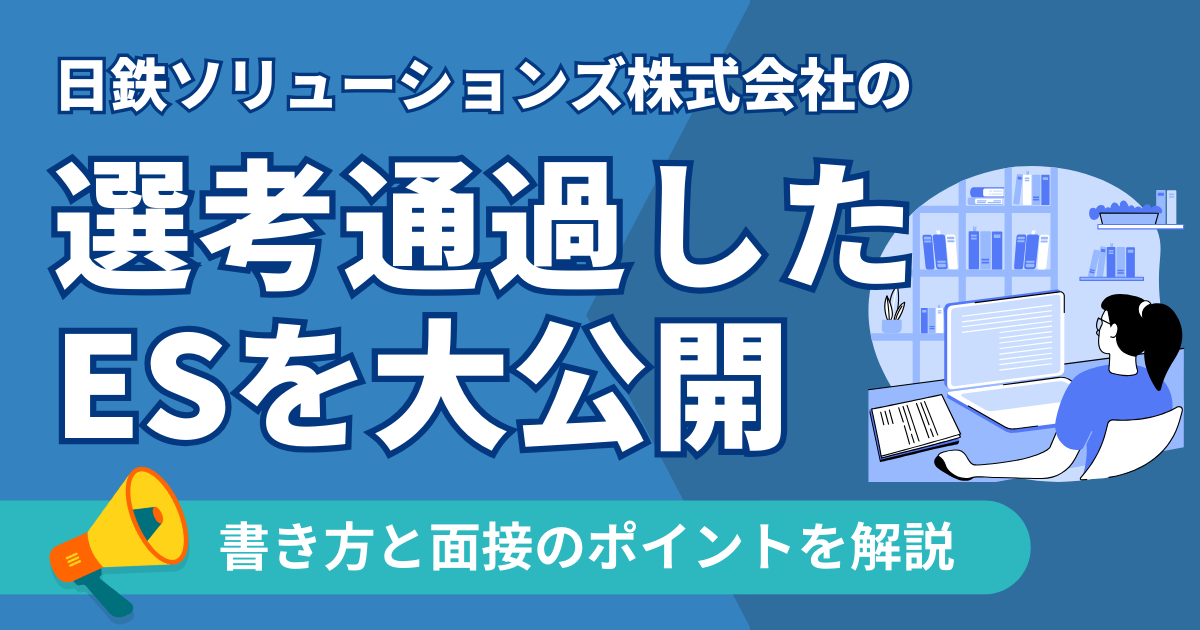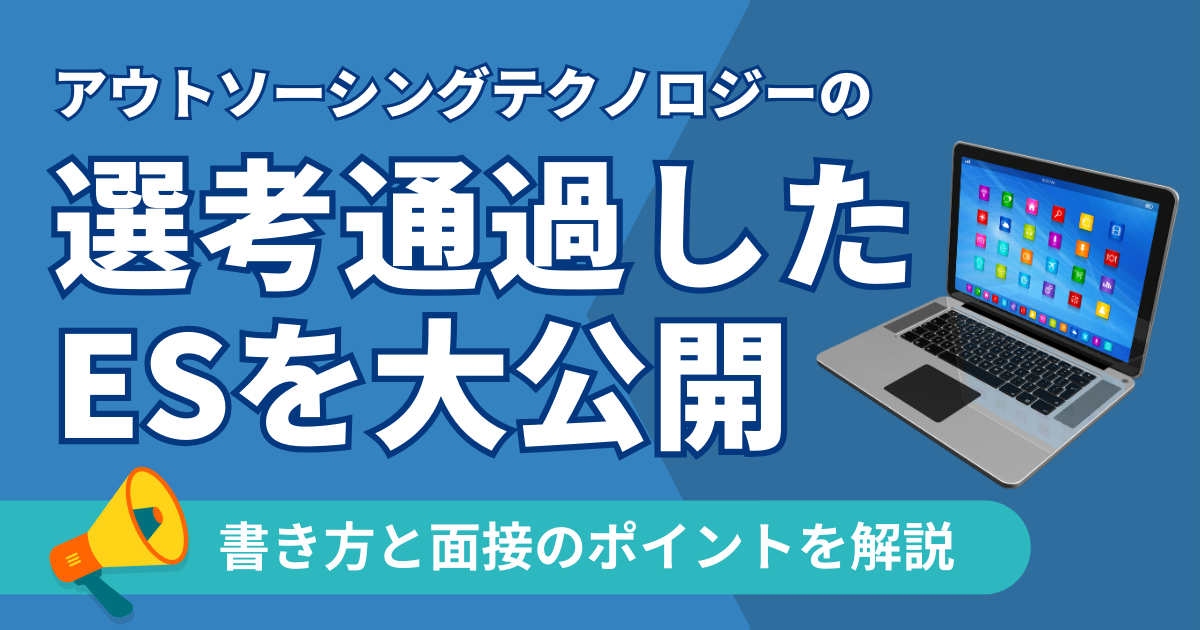大学時代に最も力を入れて取り組んだ事柄・経験を教えてください。その中で特に問題と感じたことと、あなたがどう対応したかを具体的に説明してください。(400字以内)
〇〇・〇〇・〇〇の3人で行った学部4年の卒業設計です。〇〇設計の過程で、〇〇系と〇〇系での実現可能な建築規模に対する認識の違いから、設計方針が纏まらないことが問題であると感じました。そこで私はチームを纏める立場で、以下の対応を行いました。〇〇系の2名に対して、〇〇について〇〇等を通じた数理的な理解を促しました。実例を通じた規模感の把握により、設計の実現可能性が高まると考えたためです。一方〇〇系の私は、デザイン性と耐震性が両立した空間の確保に向け、既存の手法だけでなく、〇〇構造や〇〇構造を計算により検討しました。結果は学科〇チーム中2位でした。これは、デザイン性と実現可能性の両立に成功したためと考えます。この経験から、考え方や専攻の違いによらず価値観を擦り合わせる努力の重要性を学びました。
当社で取り組んでみたいことを説明してください。(300字以内)
私は省エネやDX化等の社会的要求とお客様の快適性が両立した、駅の設計・改良工事に取り組みたいです。その理由は、駅は地域の中心であるため環境配慮等の面で模範となり、沿線人口が減少する中でお客様に快適に利用して頂くことで、生活の豊かさ向上を図る必要があると考えるためです。中でも貴社は膜屋根利用や参宮橋駅の木質化、MaaSを活用した伊勢原新駅等、環境配慮やDX化と快適性の両立に長けていると考えます。そこで、自然エネルギーの活用やMaaS等の生活サービスを融合した次世代の駅の設計、改修に携わりたく思います。その際に建築の技術的知識に加え、目標に向けチームで協働できる強みを活かし、持続可能な沿線の発展に貢献いたします。