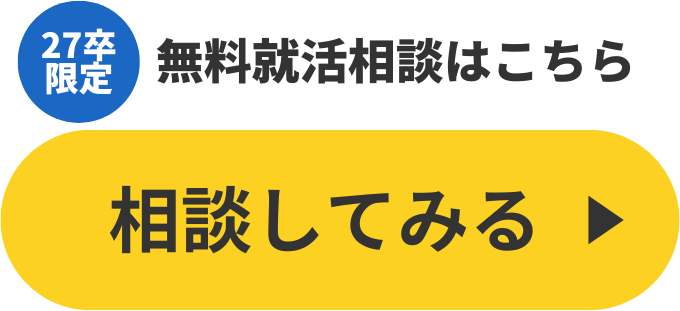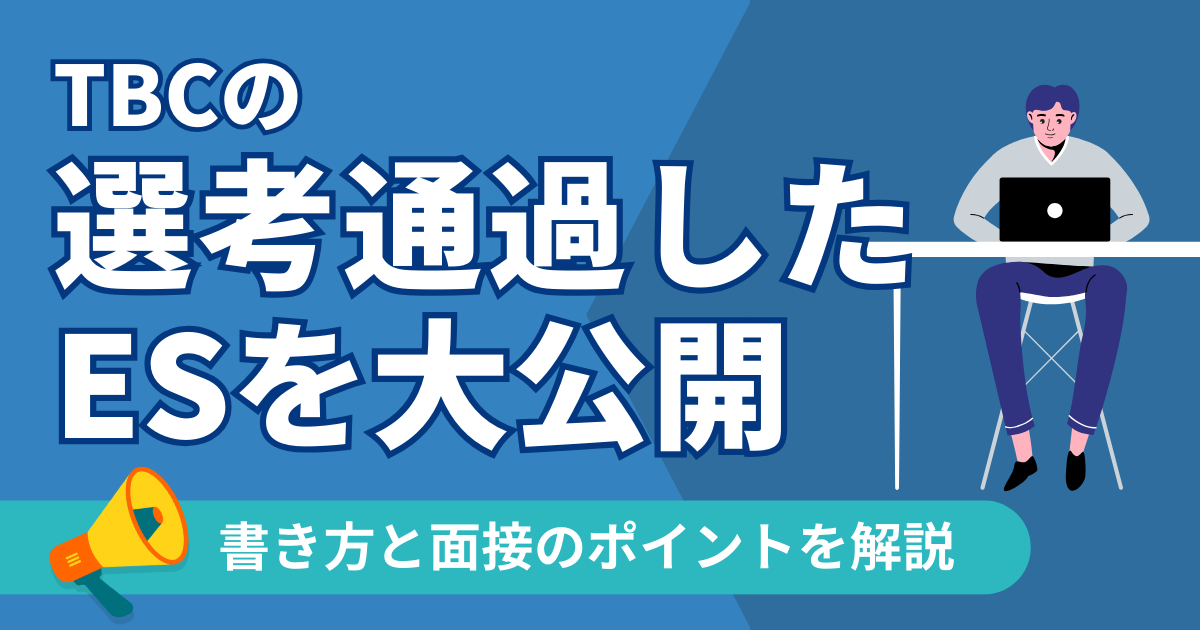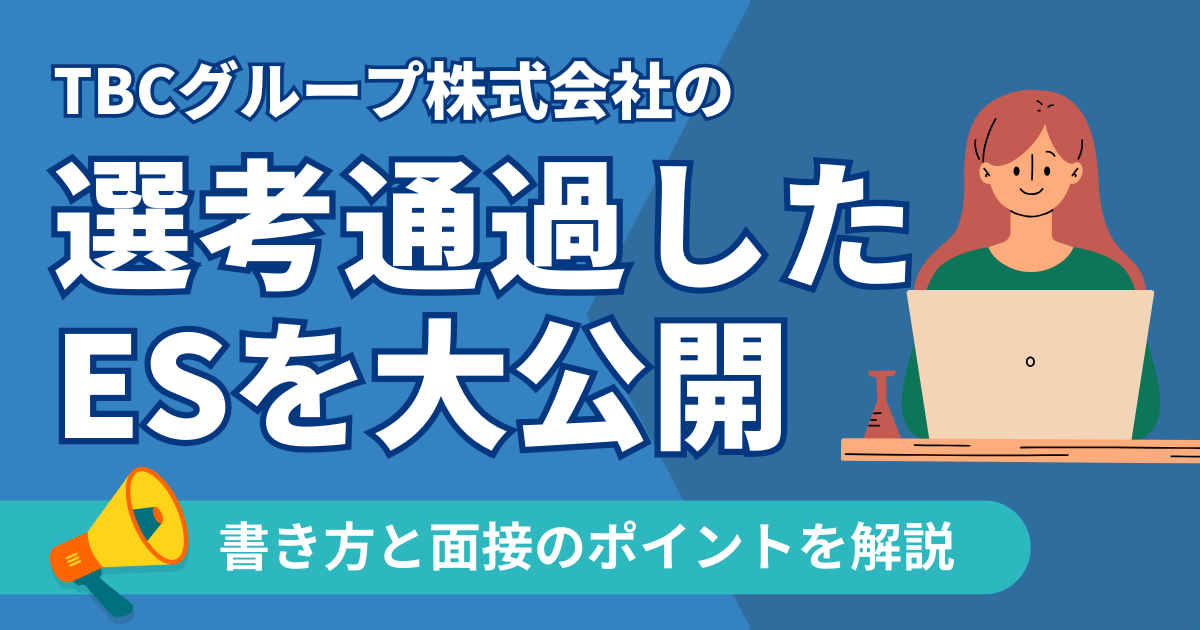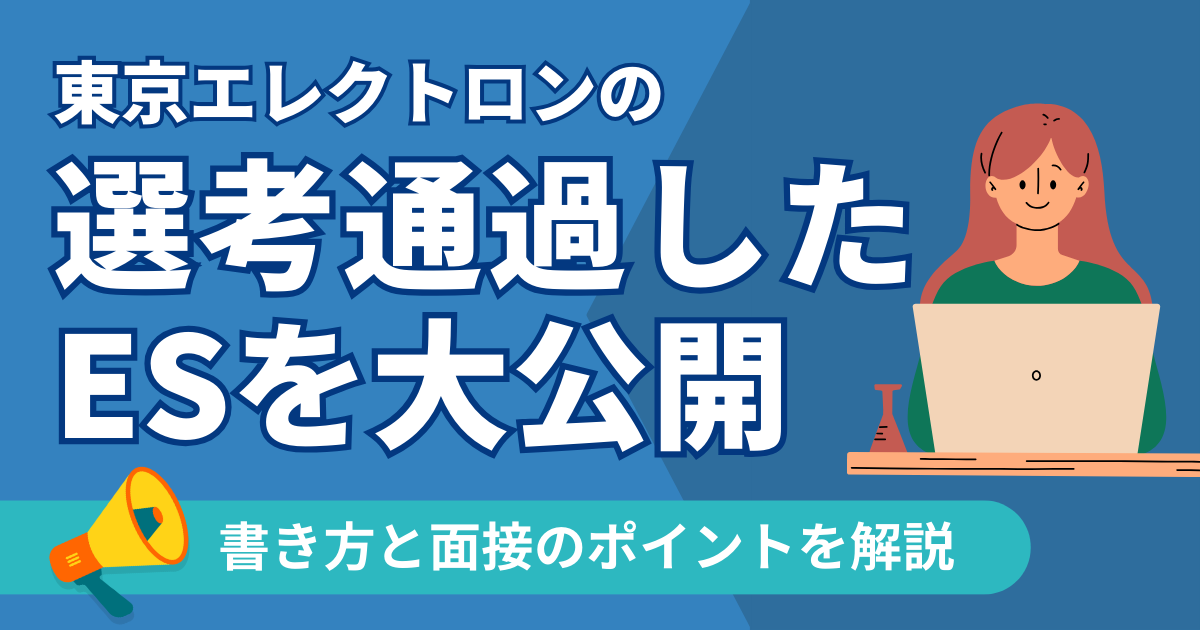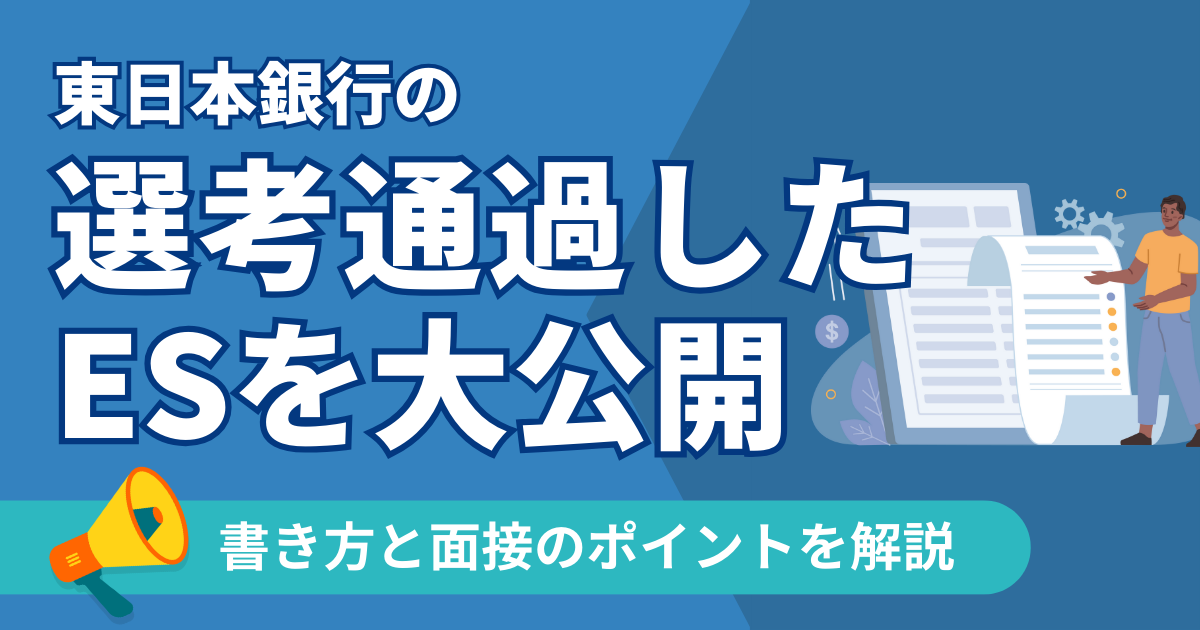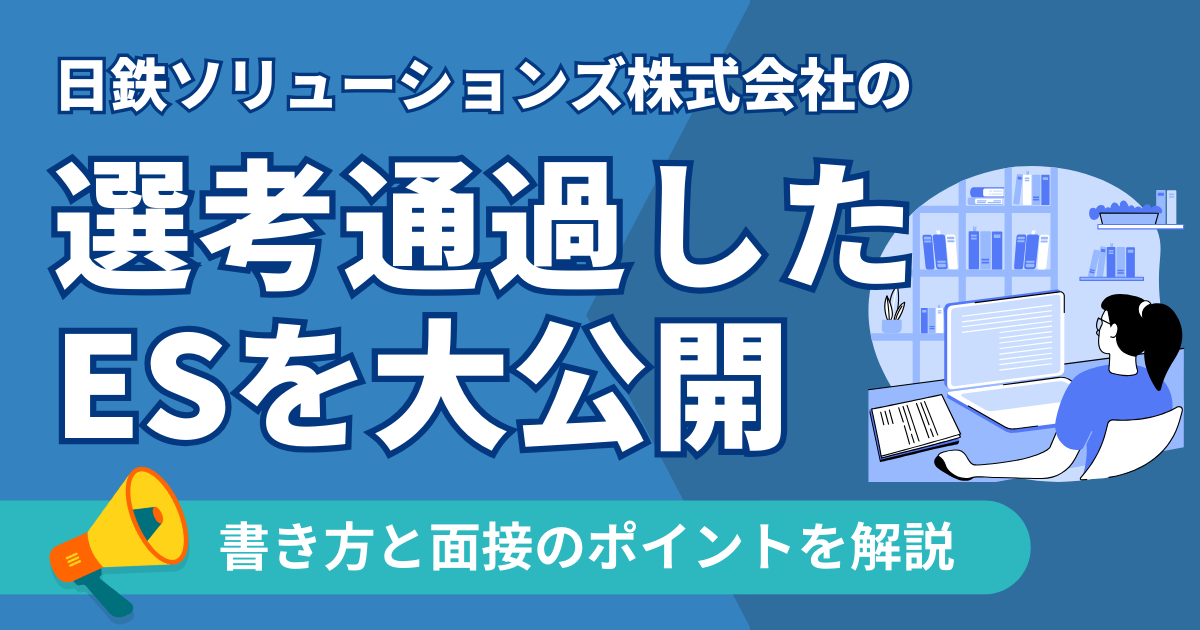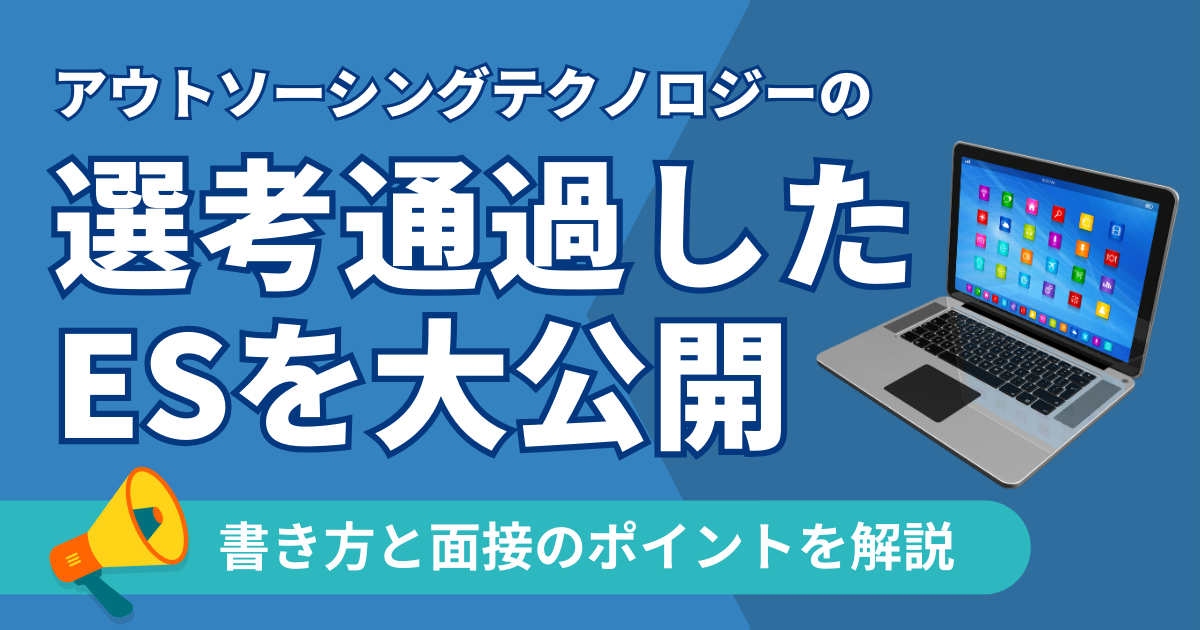自己PR
2022年8月から1年間〇〇に留学した。〇〇時代の〇〇における社会構造の解明をテーマに修士論文を執筆するためである。ヨーロッパ中心主義的な観点では、〇〇は略奪を行うヨーロッパの脅威として語られてきた。しかし、〇〇史を学んだ経験から、〇〇の活動の特異性に関心を抱いた。修士論文では、〇〇世紀の史料や〇〇で発見された遺跡の発掘物から〇〇の生活様式を分析し、彼らの社会構造を明らかにする計画である。また、〇〇の経済活動や、他民族との交流の痕跡を調査することを通して、より広範な交易ネットワークにおける〇〇の位置づけを明らかにすることを試みる。定説が真実かを確認する重要性、自ら調査し原典にあたり知識が正しいか確認すること、得られた知識により別の一面が潜んでいる可能性があること、またこれらの知見を他人に説得力をもって伝えることが重要であると留学やその後の論文執筆活動により実体験として学んだ。これらの調査手法、思考方法、語学・コミュニケーション能力、表現力などの能力が業務遂行の能力につながると考えている。
学生時代の取り組み
一番力を入れて取り組んだことは語学およびその背景となる社会への理解である。留学開始直後、私は英語で行われる授業に困難を感じていた。入念に予習と復習に励んだが、講義の内容が十分に理解できなかった。回を重ねるごとに内容が難しくなり、いよいよついていけなくなり始めた。このままでは単位取得はおろか、留学の目的すら果たせないと危機感を抱き、担当教授に現状を伝え授業についていきたいと相談した。先生は、私に毎週のリアクションペーパーを課し、いつでも質問するようにと言われた。アドバイスに従った結果、授業内容が理解できるようになった。最終的に、必要な単位を取得することができたほか、改善に向け行動を起こすことが状況を大きく変えることを学んだ。この経験を踏まえ、自らの学びを以て貴社の業務に貢献したいと考えている。
日経BPを志望した理由を教えてください
私が日経BPを志望する理由は、専門性が高く多業界とのつながりがあり、業界全体を俯瞰し客観的に分析できる強みがあるためである。一般的な業界誌とは異なり、貴社は幅広い分野にわたる専門媒体であり、そのために情報や分析がより包括的で信頼性が高いと考えている。私は2022年8月から1年間、〇〇史を学ぶために〇〇に留学した。留学先は〇〇にあり2か月の極夜やマイナス20度の寒さに直面し、当初は余りにも風土や環境が日本と異なるために気分が落ち込んだ。しかし、他の外国人留学生と勉強会やホームパーティを催し楽しい雰囲気を作り出し、積極的にコミュニケーションを取るよう努めた。この経験により、自ら行動することで、コミュニケーションが活性化し周囲との信頼関係を強固なものにできることを学んだ。自ら主体的に学ぶことで専門性を高めるとともに、異なる背景をもった人とのコミュニケーションを多くとった経験を生かしてクライアントと信頼関係を築き、貴社の広告事業に携わりたいと考えている。
入社後に配属を希望する職種・部署や、入社したらどんな業務に取り組んでみたいかを具体的に教えてください
日経BPに入社後は、セールスマーケティング部門で働きたいと考えている。市場のニーズと顧客企業の要望を把握し、それに見合った提案を行い、顧客企業の成功に貢献したい。私は、調査や分析を通じて、顧客企業のニーズを深く理解し、それをもとに効果的なマーケティング戦略を提案したり、セミナーや対談型記事広告などのイベントを企画・運営することで、顧客企業のビジネス成果を支援したいと考えている。貴社が培ってきた企業との信頼関係やAIではなく人間ならではの柔軟性を活かし、縁の下の力持ち的な立場で、顧客企業とのパートナーシップを築いていきたいと思う。
最近触れたニュース・書籍・メディア等で印象に残っているものとその理由を教えてください
ロシアのウクライナ軍事侵攻が始まってから2年が過ぎたことである。侵攻が始まった当初、ロシアの勢力拡大に驚きつつも、日本から離れた地域の話題としてどこか遠い他人事のように感じていた。しかし、留学先のノルウェーで、ウクライナへの理解を深めるための講演やウクライナ文化に触れるワークショップに参加し難民の方に出会った。また、留学を終え帰国する際、家財を引き継いでくれたのがウクライナから戦火を逃れてきた家族だった。これらの人たちと接点を持つことで、戦争によって人生設計が大きく変わった人々の存在をより身近に感じるようになった。軍事侵攻が継続されている状況から、ロシアがウクライナを併合することへの意欲の強さが見受けられ、ウクライナが敗れた場合には世界におけるロシアの脅威がさらに高まると考えられる。日本周辺の情勢を顧みると、中華人民共和国が香港や台湾で影響力を拡大し、香港ではすでに一国二制度が形骸化し民主主義体制が崩壊しつつある。中国の権力拡大は日本の安全保障においても看過することのできないリスクであるといえる。国家勢力が近隣国の住民の権利と生活を脅かしている状況は必ずしも遠い出来事ではないことを改めて実感させられる。