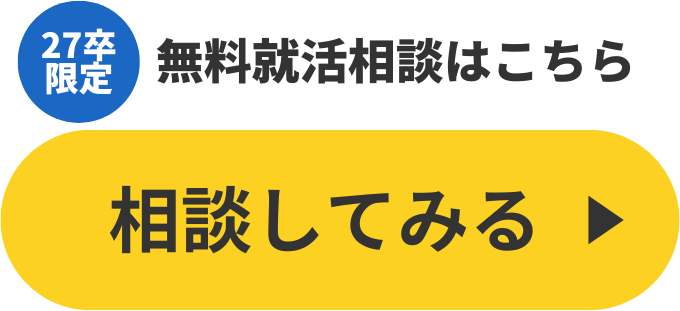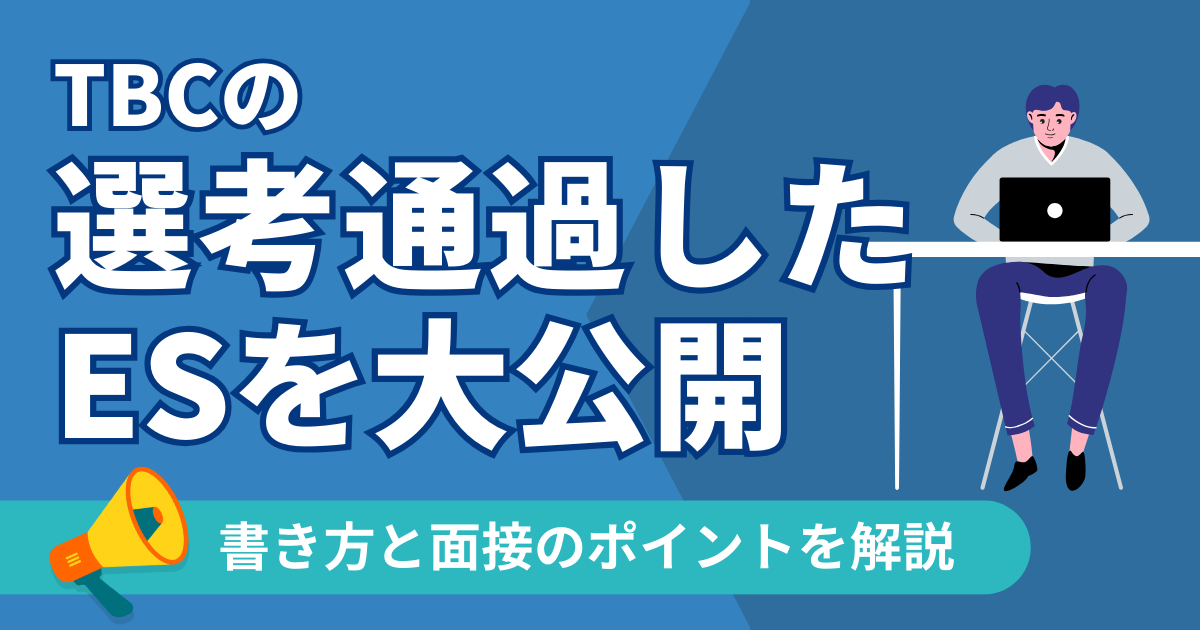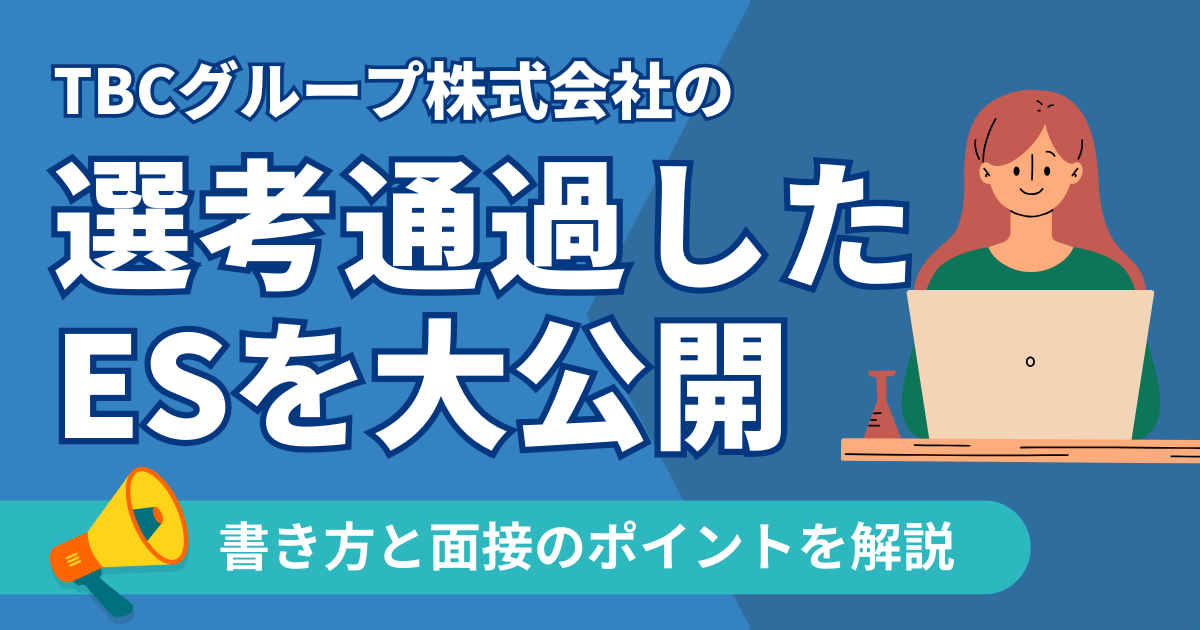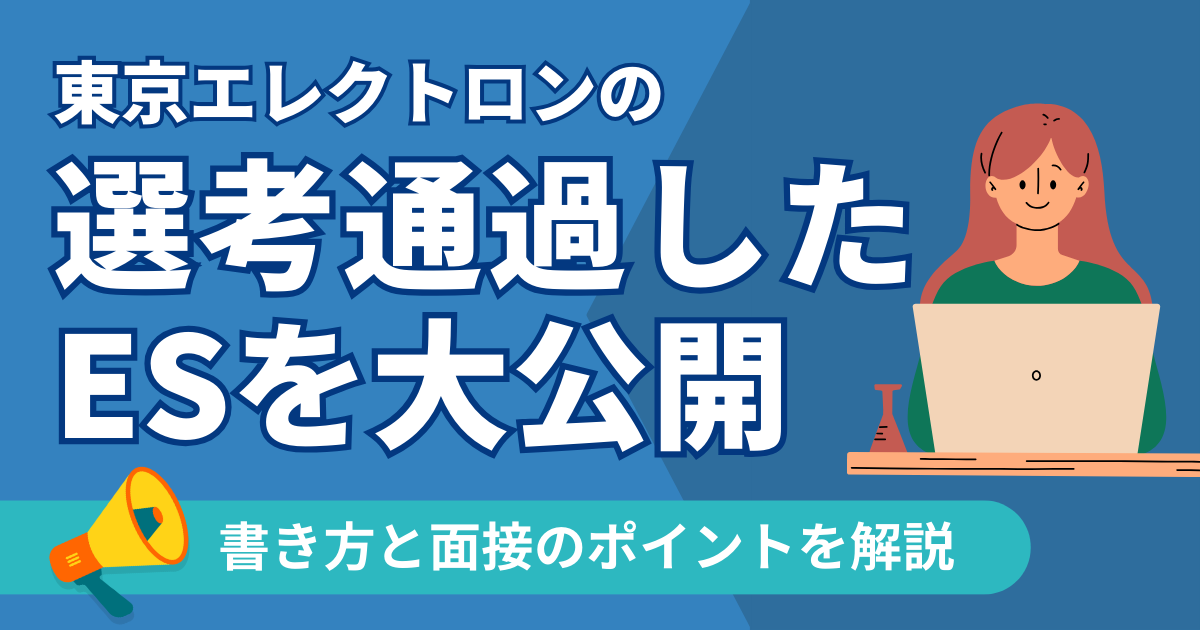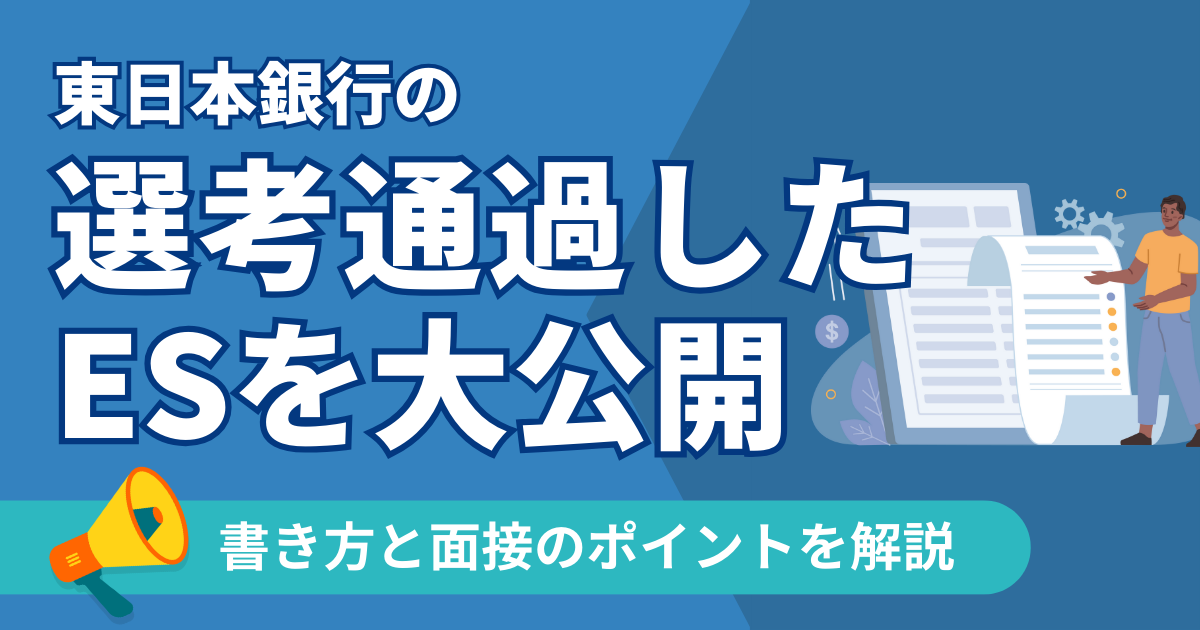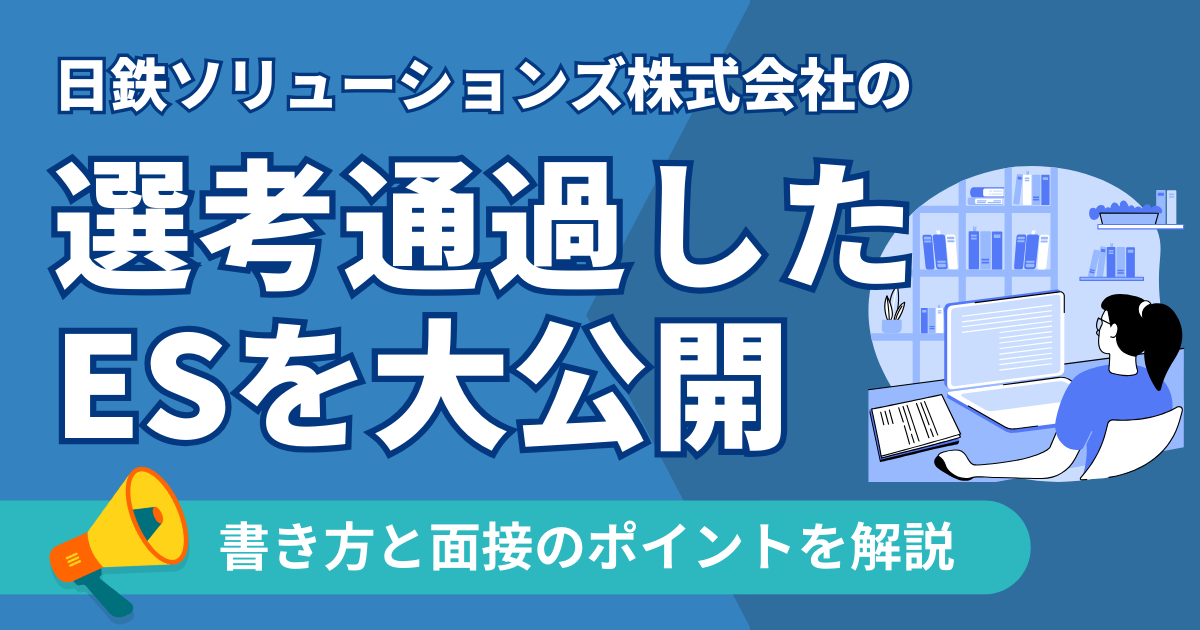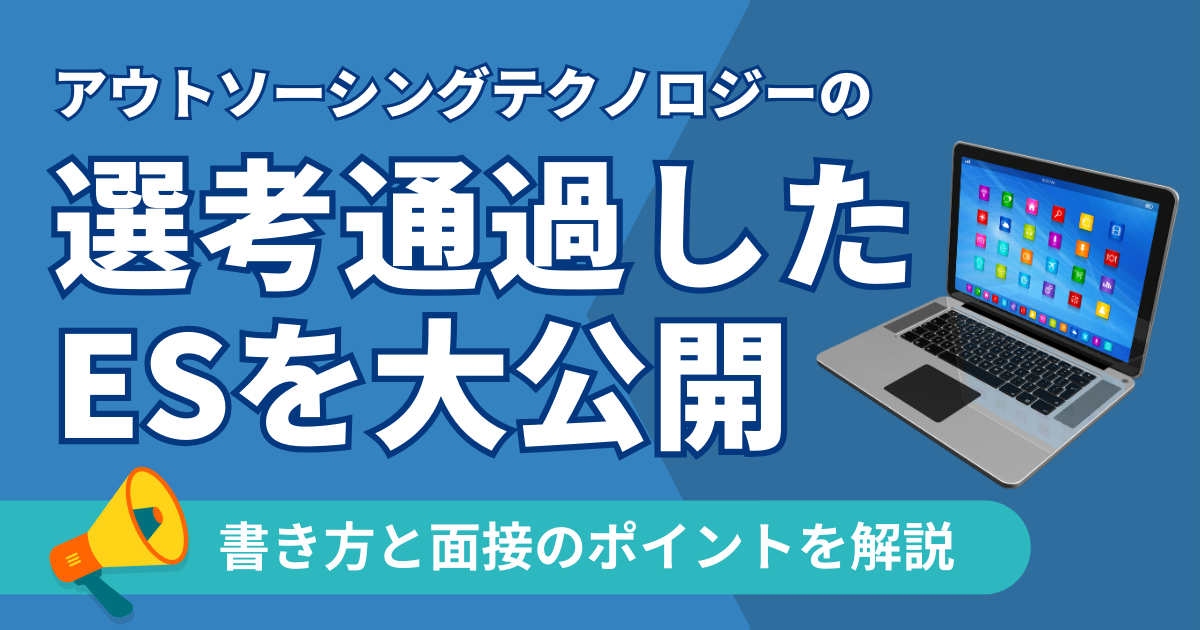25年卒
女性
桜美林大学
ES情報
学生時代や職務経験の中で「努力したきたこと」、または「自ら学び考え、行動した経験」を2つ教えてください。
・努力してきたこと
私が努力したことは勉強です。なぜなら、教師になった際に生徒のどのような質問に対しても答えられるよう、知識と教養を身につけたかったからです。まずは専門である数学の勉強に励みました。私は数学を学ぶことが好きですが、大学の授業は難易度が高く、ついていくことができませんでした。そのことが悔しく、理解できるまで証明を調べたり、教科書の問題を何回も解いたりしました。ときには同じ問題を何時間も考え、挫折しそうになった時もありました。しかしそこで諦めず、一緒に学ぶ友人の力を借りながら学び続けてきました。また、専門以外の分野でも専門と同じように勉強しました。例えばコミュニケーションの授業であれば、レポートを書くためにコミュニケーションの種類についての本を1冊読みました。不明な点があれば同じ科目を履修している友人や教授に質問して解決する努力をしました。このように勉強で努力を重ねた結果、学内の学業優秀者奨学金奨学生として採用していただくことができました。私が努力する中で学んだことは、友人や教授など他者の支援がなければ乗り越えられないこともあるということです。そのため、教師になった際も一人で抱え込まず、他の教師と協力しながら、教師として成長するために努力していく所存です。
・自ら学び考え、行動した経験
私は公立の中学校で授業補助のボランティアをしていました。始めたきっかけは、授業の流れや投げかけに対する生
徒の反応を学びたいと思ったからです。クラスの中には一人で課題をやりきることができる生徒がいる一方で、どこから手を付ければよいか分からない生徒もいました。その中で教師は、できる限り説明を短くし、生徒の考える時間を多く確保していました。また、説明の際も教師だけが話すのではなく、生徒が答えることを促していました。私は主に授業についていくことが難しい生徒をサポートしようと考えました。しかし初めは、手が止まっている生徒がいても考えているだけかもしれないと思い、中々声を掛けることができませんでした。そこで授業をしている教師がどのように声掛けをしているか、観察しました。すると、問題を解いた形跡があれば、できているところまでを褒めているということに気が付きました。そのため、この気づきを基に声掛けを実践していきました。そのことによって、生徒が安心した表情になって解き進めたり、質問をしてくれたりするようになりました。この経験によって、できていないところをサポートするだけではなく、できたところまでを褒めることも重要であることを学びました。また、生徒が聞いているだけにならないように工夫することで、生徒の集中力を持続させることができることを学びました。教師になった際にはこの経験を生かして、生徒の「できる」を増やし、個々の能力を伸ばす授業をつくります。