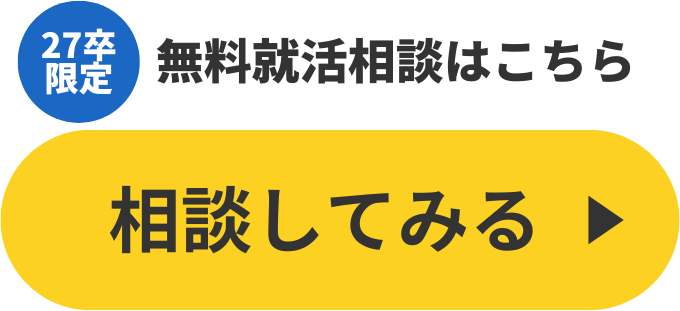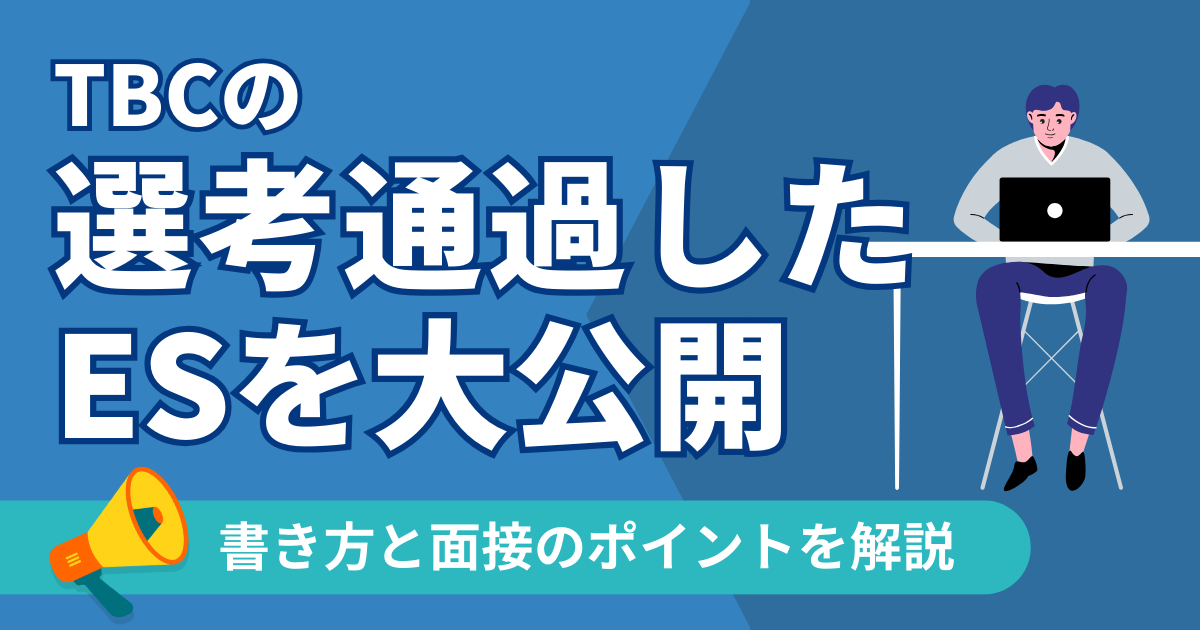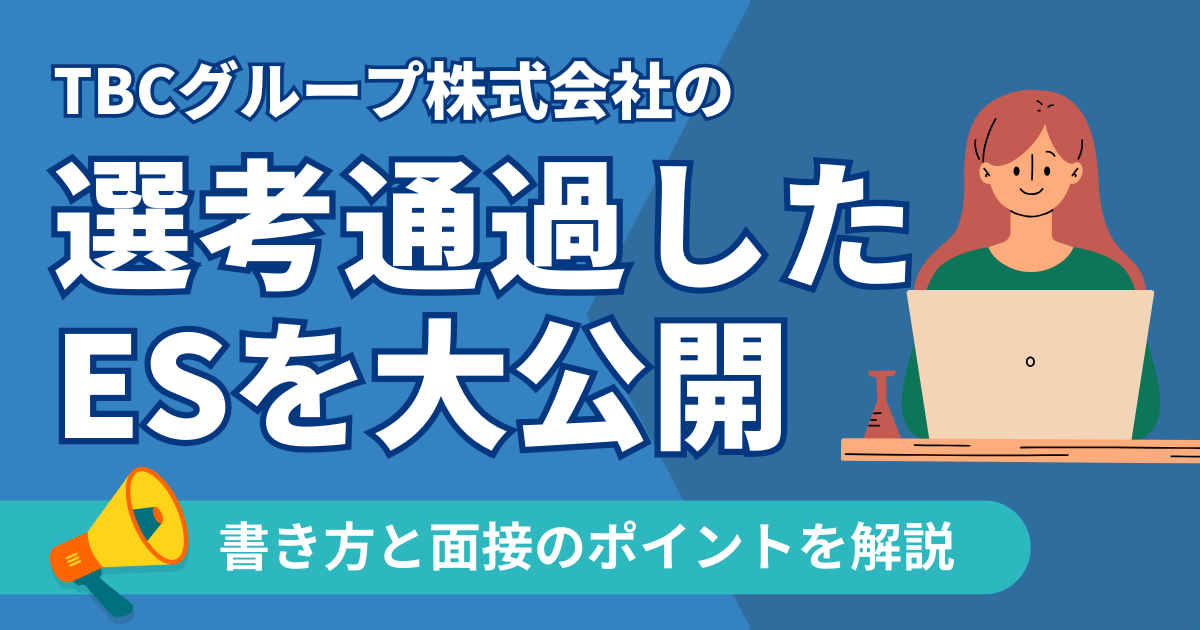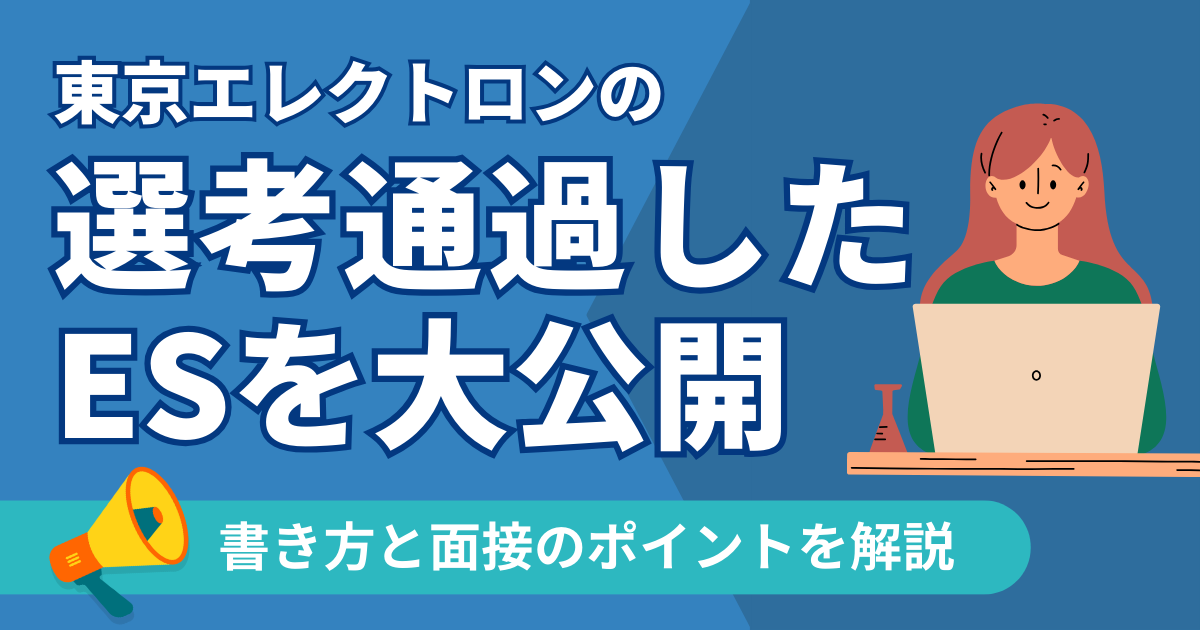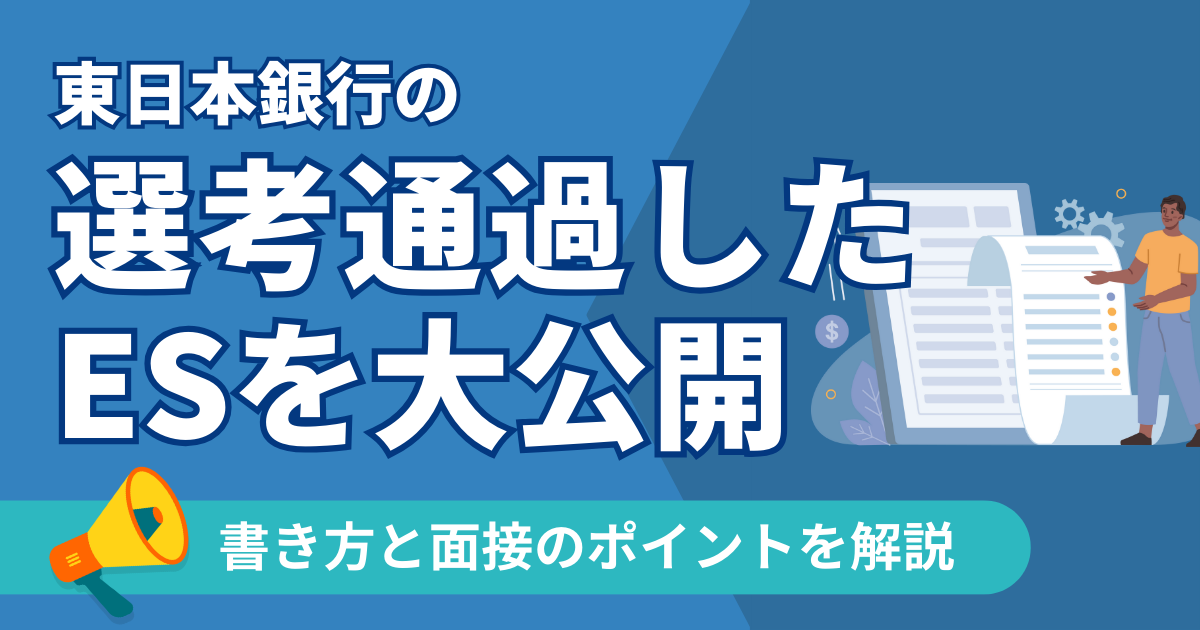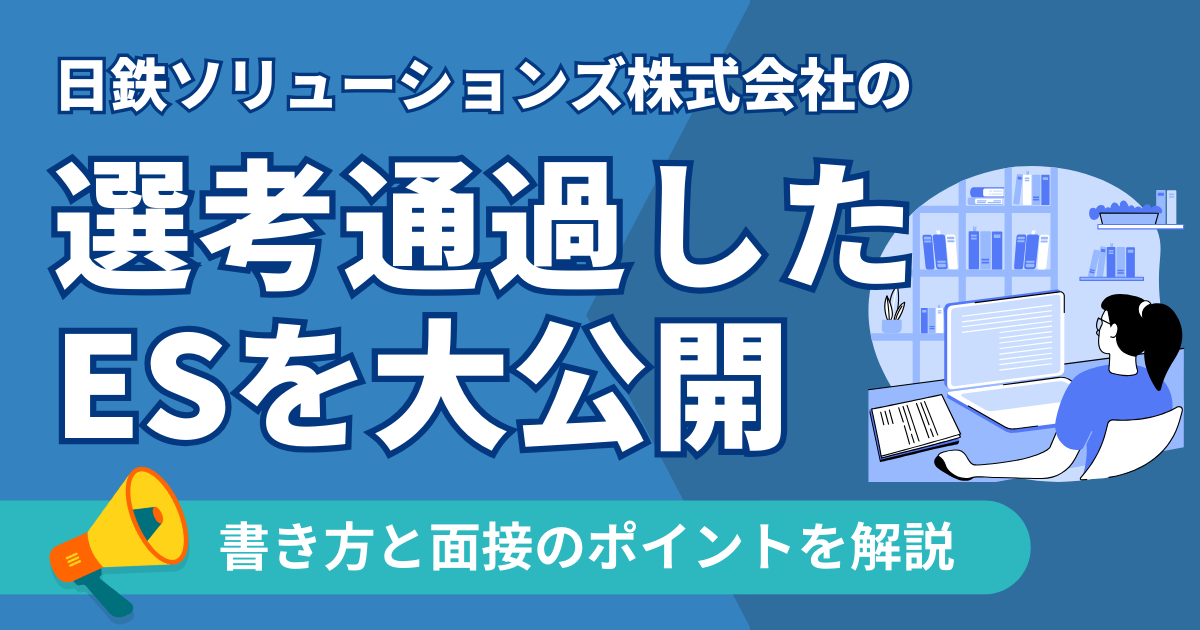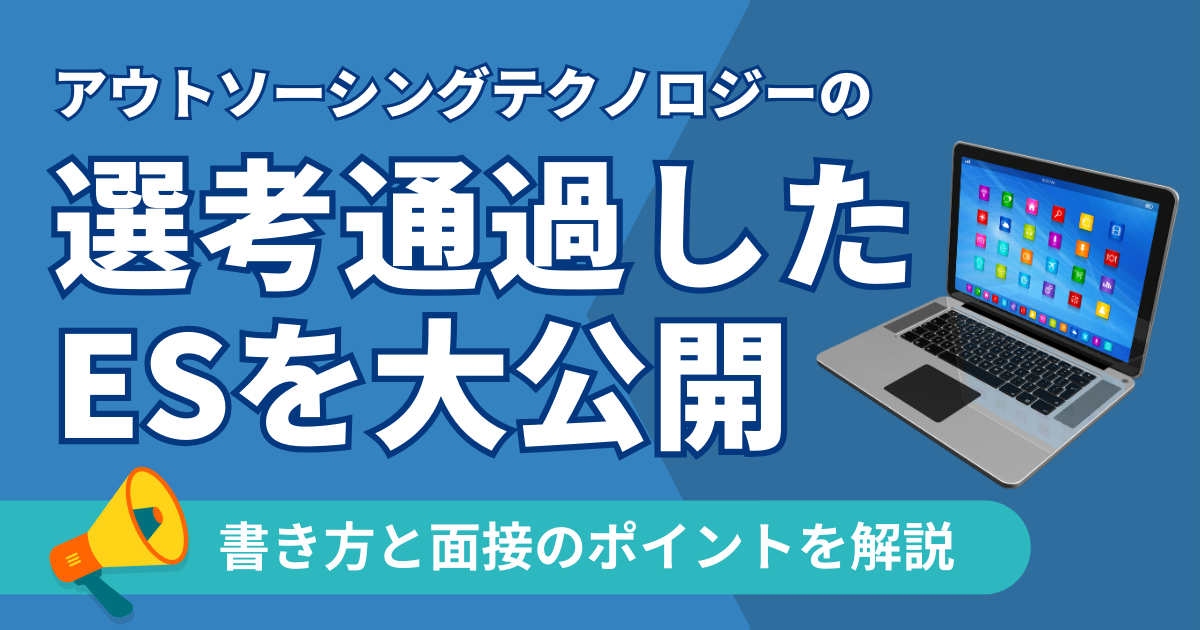26年卒
男性
九州工業大学
ES情報
志望動機(500文字以内)
私は、産業の基盤を支えるモノづくりに携わりたいという思いから、貴社を志望しました。〇〇時代に所属していた〇〇研究部の活動を通じて、モノづくりの楽しさを実感しました。特に、チームで試行錯誤を重ねながら〇〇を製作し、一台の〇〇を完成させる過程に大きなやりがいを感じました。その後、大学では〇〇学分野の研究に取り組み、モノづくりを支える機械や技術に興味を持ちました。そこから、幅広い産業で部品加工を支える「生産の源流」となる工作機械に惹かれました。
中でも貴社は、「クオリティファースト」の理念のもと、航空機や金型といった高難度加工に対応する高精度なマシニングセンタを開発しており、世界の製造現場を支えている点に魅力を感じています。さらに、設計から製造まで一貫した体制で、現場の課題に真摯に向き合い、最適なソリューションを提供している姿勢にも深く共感しました。私は開発設計の業務を通じて、お客様一人ひとりの課題に向き合いながら、精度・生産性・環境性を兼ね備えた工作機械の設計に挑戦したいと考えています。将来的には、貴社の工作機械がより多くの現場で信頼され続けるような製品開発に貢献したいです。
研究テーマが決定されている方については記載お願いします。されていない方はこれまで取り組んだ内容、取り組む予定の内容について記入してください。(500文字以内)
〇〇の〇〇除去の容易化をテーマに研究に取り組んでいます。〇〇は、複雑な形状の部品を高精度に製造できる技術として、幅広い産業で造形プロセスの自動化が期待されています。しかし、造形後の〇〇除去は現在も多くが手作業に頼っており、自動化を妨げる要因となっています。この課題に対し、私は除去が容易となる〇〇形状を検討して、解決に取り組んでいます。
特に、「除去のしやすさ」を左右する要因の特定と、その影響の分析に重点を置いています。具体的には、除去時に用いられるエネルギーの指標として割合に着目し、〇〇除去の解析を行っています。そして、得られた解析結果をもとに、各要因が除去に与える影響を定量的に評価し、最適な形状を導き出します。さらに、実際に造形・除去実験を行うことで、解析による評価の妥当性を検証します。解析と実験結果が一致しない場面もありましたが、解析条件の見直しを繰り返すことで、より現実に即したモデルを構築することができました。今後は、より複雑な形状や条件においても有効な〇〇形状の検討に取り組み、実用化に向けた精度向上を目指します。
学生時代自ら考え実践したことは何ですか、またそれから何を学びましたか?(500文字以内)
業務改善のために、自ら作業工程を分析し、効率化を図りました。調理のアルバイトでは、不器用で慎重な性格から調理に時間がかかり、周囲に迷惑をかけていました。特に、定期的に商品が変わるため、作業手順の習得に苦労し、業務全体に遅れが生じることが課題でした。
そこで、「なぜ作業が遅れているのか」を自分なりに分析しました。商品ごとの作業工程を細かく分解し、手間取っている作業を特定しました。次に、作業手順やコツをまとめた自作マニュアルを作成し、効率的な手順を繰り返し見直しました。また、先輩の動作や器具の配置を自分と比較し、動線の無駄や非効率な癖に気づくようになりました。分からない点は積極的に質問し、メモを更新しながら改善を重ねた結果、作業時間が短縮され、商品が変わっても迅速に対応できるようになりました。最終的には新人の指導も任され、マニュアルを後輩の指導にも活用できました。
この経験から、課題を曖昧なままにせず分析し、改善に取り組むことの重要性を学びました。貴社においても、直面した課題に対して主体的に取り組み、工夫と改善を積み重ねて成果につなげる姿勢を活かしていきたいと考えています。
自己PR(300文字以内)
私は、未経験の分野でも主体性をもって取り組むことができます。大学院時代、〇〇会主催の〇〇を製作し競う「〇〇グランプリ」に〇〇製作未経験のメンバーで参加しました。製作中、当初の設計では成形品に不良が発生する可能性があることが解析から判明しました。そこで私は、文献や過去の事例を参考にし、〇〇形状の改善案を検討しました。そして、解析結果をチームに共有し、議論を重ねながら設計を修正し、高精度な成形品が作れる〇〇を完成させました。その結果、入賞することができました。貴社でも、新たな技術や課題に自ら踏み込み、工作機械の進歩に貢献したいと考えています。